超高利回りアパート投資の秘密
\\\知りたい方はこちら///


監修者

株式会社Riel 代表取締役
坂口 卓己(サカグチ タクミ)
宅地建物取引士として年間57棟の販売実績を誇り、東京都渋谷を拠点に新築アパートの企画開発から資金計画、満室運営、出口戦略まで一貫支援。豊富な現場経験と最新市況データを融合し、信頼とスピードを重視したサービスで投資家一人ひとりに最適な資産形成プランを提案する不動産投資のプロフェッショナル。
⇒詳細はこちら
アパート経営を本格的な事業として捉えるなら、「建築費4,000万円」は一つの重要なベンチマークです。この予算規模になると、単なる収益物件の枠を超え、立地やターゲットに応じた多彩な戦略展開が可能になります。この記事では、4,000万円で実現できるアパートの具体的な輪郭から、詳細なコスト分析、現実的な収益予測までを徹底的にシミュレーション。あなたの事業計画を成功へと導く、確かな道筋を示します。
総予算4,000万円は、質の高いアパート建築を実現し、多様な入居者ニーズに応えるための十分な元手となります。3,000万円台の計画よりも設計の自由度が格段に向上し、戸数や間取り、構造において多彩な戦略が選択可能になるからです。木造3階建てや8戸以上のプランも視野に入り、より本格的な賃貸事業のスタートラインと言えるでしょう。まずはこの予算でどのような建物が実現可能か、その輪郭を掴むことが重要です。
4,000万円の予算規模では、木造なら3階建て・8戸、軽量鉄骨なら2階建て・6戸あたりが現実的なシミュレーションの範囲です。以下の表で、構造ごとのプランの選択肢を比較してみましょう。
建築費4,000万円の予算では、土地の立地やターゲットに応じて、建物の構造から戦略的にプランを組み立てることが可能です。以下に代表的な3つのプランを比較します。
| 構造タイプ | 戦略 | 想定プラン(階数・戸数・間取り) | 特徴・ターゲット |
| 木造 | 利回り最大化 | 3階建て・8戸(ワンルーム) | 戸数を最大限に確保し、駅近などの好立地で高い利回りを追求する。主なターゲットは利便性を重視する学生や社会人単身者。 |
|---|---|---|---|
| 軽量鉄骨造 | 家賃単価と質の両立 | 2階建て・6戸(1LDK) | 部屋の広さと質を高め、高めの家賃でも入居が見込める層を狙う。ターゲットは快適な生活を求めるカップルやDINKS。 |
| 重量鉄骨造 | 長期安定と差別化 | 2階建て・4戸(2LDK) | 柱の少ない広い空間を活かし、競合の少ないファミリー向け物件で差別化。長期入居による安定経営を目指す。 |
建築費4,000万円のアパートを計画する場合、延床面積は60~70坪(約200~230㎡)が一般的な目安となります。これを実現するためには、通常50~80坪程度の敷地サイズが必要です。なぜなら、建ぺい率や容積率といった法規制に加え、駐車場や駐輪場、アプローチ部分の確保も考慮しなければならないからです。例えば、建ぺい率60%・容積率200%の土地であれば、60坪の敷地に延床面積70坪のアパートを建てる計画も可能。土地の広さだけでなく、法規制とのバランスを総合的に判断することが計画の成否を分けます。
4,000万円の予算があれば、単身者向けの高密度プランだけでなく、ファミリー向けで競合物件と差別化するプランも十分に検討できます。予算に余裕が生まれることで、1戸あたりの面積を広くとるファミリー向けプランでも、事業の採算性を確保しやすくなるからです。例えば、都心部や駅近なら1K×8戸で収益性を最大限に追求する戦略が有効です。一方、郊外の落ち着いたエリアであれば、駐車場付きの2LDK×4戸といったプランで、長期入居が見込めるファミリー層をターゲットにする戦略も考えられます。
総予算4,000万円の費用内訳を正確に地図化(マッピング)することは、事業計画の根幹を形成します。以下の配分モデルを参考に、ご自身の計画に潜むコストを漏れなく洗い出しましょう。
| 費用項目 | 比率の目安 | 概算金額 | 主な内容 |
| ① 建物本体工事費 | 約70% | 2,800万円 | 建物の基礎や骨組み、屋根、外壁、内装、キッチン・バス・トイレといった住宅設備の工事費用。 |
|---|---|---|---|
| ② 付帯・外構工事費 | 約20% | 800万円 | 地盤改良、給排水・ガス管の引き込み、駐車場やアプローチ、フェンスなどの屋外工事費用。 |
| ③ 設計料・諸経費 | 約10% | 400万円 | 設計料、建築確認申請費、登記費用、不動産取得税、火災保険料、ローン手数料など。 |
| 合計 | 100% | 4,000万円 |
【構造別】建築費の目安と法定耐用年数
アパートの構造選びは、初期コストだけでなく、長期的な減価償却や融資期間にも影響を与える重要な要素です。以下に、主な構造の坪単価と法定耐用年数の目安を示します。
| 構造 | 坪単価の目安 (2025年時点) | 法定耐用年数 | 主な特徴 |
| 木造 (W造) | 70万円~85万円 | 22年 | コストを抑えやすく、設計の自由度が高い。日本の気候風土に合っている。 |
|---|---|---|---|
| 軽量鉄骨造 (S造) | 80万円~95万円 | 19年~27年※ | 工場で部材を生産するため、品質が安定しており工期が短い傾向にある。 |
| 重量鉄骨造 (S造) | 90万円~110万円 | 34年 | 柱が少なく、店舗併用など広々とした空間設計が可能。耐久性が高い。 |
| 鉄筋コンクリート造 (RC造) | 100万円~ | 47年 | 耐久性、耐火性、遮音性に最も優れる。法定耐用年数が長く、資産価値が落ちにくい。 |
4,000万円規模のアパート建築における本体工事費の単価は、木造で坪70~85万円、軽量鉄骨造で坪80~95万円が一つの目安です。近年の資材高騰や人件費上昇が単価を押し上げていますが、建物の仕様や設備のグレードによって価格は大きく変動します。仮に本体予算を2,800万円(4,000万円の70%)と設定すると、木造なら約33~40坪、軽量鉄骨造なら約29~35坪の建物が建築可能という計算になります。この差が戸数や一部屋の広さに直結するため、複数の会社から見積もりを取り、単価の妥当性を比較することが不可欠です。

見落としがちですが、外構やインフラなどの周辺工事費は、総予算の約20%、つまり800万円前後を見ておく必要があります。計画段階で以下の項目が漏れていないか、チェックリストで確認しましょう。はい、承知いたしました。 アパート建築の際に見落としがちな「周辺工事費」について、各項目の費用の目安を補足したチェックリストを作成します。
【周辺工事費チェックリストと費用目安】
建物本体以外にかかる周辺工事費は、土地の状況によって大きく変動します。計画段階で概算費用を把握し、余裕を持った資金計画を立てることが重要です。
※以下の金額は一般的な目安であり、土地の広さ、形状、地域、工事内容によって大きく変動します。必ず複数の業者から正式な見積もりを取得してください。
古家の解体費用
費用の目安:100万円 ~ 300万円
木造30坪程度の家屋を想定した金額です。建物の構造(鉄骨造など)や、アスベスト(石綿)の有無によって費用は大きく変動します。
地盤調査・地盤改良工事費
費用の目安:60万円 ~ 300万円以上
地盤調査自体は5万円~10万円程度ですが、調査の結果、地盤が弱いと判断された場合は地盤改良工事が必須となります。工事の規模や工法によって費用は大きく変わります。
給排水・ガス管の引き込み・更新工事費
費用の目安:70万円 ~ 200万円
前面道路に埋設されている本管から、敷地内に管を引き込む工事です。本管からの距離や、前面道路の舗装状況、自治体の規定(水道加入金など)によって費用は異なります。
外構工事費
費用の目安:150万円 ~ 600万円
駐車場のコンクリート舗装、隣地との境界ブロックやフェンスの設置、アプローチ、植栽、門柱や郵便ポストの設置など、工事の範囲と仕様によって費用は大きく変動します。
アンテナ設置工事費
費用の目安:5万円 ~ 15万円
地上デジタル放送用のアンテナ設置費用です。BS/CSアンテナも同時に設置する場合は、費用が加算されます。
建物に直接関わる費用とは別に、設計料や各種申請費用、保険料といった「ソフトコスト」として、総予算の約10%(400万円)を確保しておく必要があります。これらは事業をスタートさせる上で不可欠な経費であり、融資の対象外となることも多いため、自己資金で準備することが求められます。
【ソフトコストチェックリスト】

4,000万円のアパート建築において、融資を最大限に活用しつつも、経営の安定性を保つためには、自己資金とローンの最適なバランスを見つけることが重要です。自己資金比率を高めることで、金融機関からの信用度が上がり、有利な条件で融資を受けられる可能性が高まります。また、将来の不測の事態に備えるための体力にも繋がるため、慎重な資金計画が求められるのです。
4,000万円のプロジェクトでは、一般的に総事業費の1~2割、つまり400万円~800万円の自己資金を用意するのが理想的とされます。なぜなら、金融機関は申込者の事業への本気度やリスク許容度を自己資金の額で測る傾向があるためです。特に、前述の「ソフトコスト(諸経費)」にあたる部分は現金での支払いが必要になるケースが多いです。この最低ラインを意識しつつ、可能な限り自己資金比率を高めることが、健全なアパート経営の第一歩となります。
4,000万円規模のアパートローンでは、地域に根差した地方銀行(地銀)や信用金庫(信金)が有力な相談先となります。彼らが審査で重視するポイントは、以下の通りです。
【金融機関の主な審査ポイント】
初期投資を抑え、事業の収益性を高めるためには、国や自治体の補助金・税制優遇をテコ(レバレッジ)として最大限に活用すべきです。これらを活用することで、数百万円単位で初期費用を圧縮できる可能性があり、投資効率を大きく改善できます。例えば、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準を満たす省エネアパートに対する補助金や、子育て支援に資する共同住宅への助成金などがあります。常にアンテナを高く張り、利用できる制度は漏れなく申請することが肝要です。
はい、承知いたしました。 アパート経営における「銀行選びの重要性」について、記事の一部として使いやすいよう、要点を絞って簡潔にまとめます。

アパート経営の成功は、物件選びだけでなく「銀行選び」にも大きく左右されます。銀行は単なる貸し手ではなく、長期的な事業パートナーです。金利の低さだけで判断せず、以下の3つの視点で総合的に比較検討しましょう。
これらはキャッシュフローに直結する最重要項目です。わずか0.1%の金利差でも、総返済額は数十万円単位で変わります。また、融資期間が長ければ月々の返済は楽になりますが、ご自身の年齢や建物の構造によって最長期間は異なります。最も有利な条件を引き出すためにも、複数行との交渉は必須です。
銀行があなたの計画の「事業性」を評価してくれるか、それとも個人の「属性」だけで判断するかは大きな違いです。特に地方銀行や信用金庫は、地域の賃貸需要を理解し、事業性を親身に評価してくれる傾向があります。また、アパート経営に詳しく、長期的な視点で相談に乗ってくれる担当者と出会えるかどうかも、事業の可能性を広げる上で非常に重要です。
万が一の際にローン残債がゼロになる団信は、家族に資産を残すための重要なリスク管理ツールです。金融機関によって、基本的な保障に加えて「がん保障」や「三大疾病保障」などを付けられる場合があります。金利だけでなく、この「保障の手厚さ」もしっかりと比較し、ご自身のライフプランに合ったものを選びましょう。
銀行選びは、目先の数字だけでなく、長期的なパートナーシップを築けるかという視点が不可欠です。都市銀行、地方銀行、信用金庫など、複数の金融機関にアプローチし、あなたの事業に最も適したパートナーを見つけ出してください。
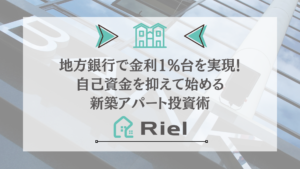
アパート経営の成功は、どれだけ精度の高い収益予測を立てられるかにかかっています。「これくらいで貸せるだろう」という希望的観測ではなく、周辺の家賃相場や競合物件を徹底的に分析し、現実的な想定家賃から事業計画を逆算する思考が不可欠です。このプロセスを丁寧に行うことで、事業のリスクを洗い出し、確実な利益計画を立てることが可能になります。
アパート経営の収益力を測る「利回り」には、大きく分けて2種類あります。広告などでよく見かける「表面利回り」だけで判断すると、実際の収益とかけ離れてしまうため、必ず「実質利回り」を計算することが重要です。
【算出の前提条件】
物件の維持にかかる経費を考慮しない、最もシンプルな利回り計算です。
【計算式】
年間家賃収入 ÷ 総事業費 × 100 = 表面利回り
【この例での計算】
320万円 ÷ 4,000万円 × 100 = 8.0%
特徴
計算が簡単で、物件の収益性を大まかに把握するのに役立ちます。ただし、実際の「手残り」とは異なります。
年間の家賃収入から、実際に運営にかかる経費を差し引いて計算する、より現実に即した利回りです。
【年間運営経費の内訳例】
【計算式】
(年間家賃収入 - 年間運営経費) ÷ 総事業費 × 100 = 実質利回り
【この例での計算】
(320万円 - 64万円) ÷ 4,000万円 × 100 = 256万円 ÷ 4,000万円 × 100 = 6.4%
特徴
物件の本当の収益力を示す数値です。投資判断を行う際は、必ずこの実質利回りを基準に検討しましょう。この例では、表面利回りとの間に1.6%もの差があることが分かります。

満室経営が永遠に続く保証はありません。空室リスクを考慮し、稼働率が変動した場合のキャッシュフローを複数のシナリオで試算しておくことが、リスク管理の基本です。
満室経営が永遠に続く保証はどこにもありません。そこで、事前に「もし空室が出たらどうなるか?」をシミュレーションし、ご自身の計画がどれくらいの空室に耐えられるのか(リスク耐性)を把握しておくことが極めて重要です。
ここでは、以下の条件で稼働率が変動した場合のキャッシュフローを試算します。
【シミュレーションの前提条件】
| 稼働率(空室数目安※) | 年間家賃収入 | 年間キャッシュフロー(税引前) | オーナーの状況 |
| 100% (空室なし) | 320万円 | 116万円 | 健全 計画通りの収益。将来の大規模修繕や繰り上げ返済のための資金を十分に蓄積できる状態。 |
|---|---|---|---|
| 90% (1戸空室) | 288万円 | 84万円 | やや注意 まだ十分な利益は出ているが、満室時よりキャッシュフローは28%減少。空室が長期化しないか注視が必要。 |
| 80% (2戸空室) | 256万円 | 52万円 | 危険水域 手残りが半分以下に。急な修繕など想定外の出費が発生すると、資金繰りが一気に厳しくなる可能性がある。 |
※8戸のアパートを想定した場合の空室数
さらに重要なのは、キャッシュフローがゼロになる「損益分岐点稼働率」を知っておくことです。
【計算式】
(年間運営経費 + 年間返済額) ÷ 年間満室家賃収入 = 損益分岐点稼働率
【この例での計算】
(64万円 + 140万円) ÷ 320万円 = 204万円 ÷ 320万円 = 63.8%
これは、稼働率が63.8%を下回ると、アパート経営が赤字になることを意味します。8戸のアパートであれば、常に5戸以上入居していれば赤字にはなりませんが、4戸以下になると持ち出しが発生する、という具体的なリスクラインが分かります。
健全なアパート経営のためには、以下の指標をチェックすることが不可欠です。
【経営の健全性チェックリスト】
理想のアパートプランを実現するためには、建築基準法や都市計画法などの法規制をクリアすることが大前提となります。土地のポテンシャルを最大限に引き出すには、これらの規制を深く理解し、それを逆算して土地選びや建物の配置計画を行う必要があります。法規制は単なる制約ではなく、その土地の特性を活かすための設計の指針と捉えるべきです。
建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)と容積率(延床面積の割合)は、アパートの規模と収益性に直結する最も重要な法規制です。例えば、容積率が高い土地ほど、同じ敷地面積でもより多くの戸数を確保できるため、収益性を高めやすくなります。土地を選ぶ際には、価格だけでなく、この容積率が自身の事業計画に見合っているかを必ず確認してください。これらの規制を読み解き、最大限に活用することが、効率的なプランニングの第一歩です。
土地には、そのエリアの環境を守るために「用途地域」が定められており、それによって建てられる建物の種類や高さが制限されます。例えば、「第一種低層住居専用地域」では、原則として3階建て以上のアパートは建てられません。一方で、「近隣商業地域」などでは、より高さのある建物を建てることが可能です。このように、用途地域と高さ制限は設計の自由度を大きく左右するため、土地の契約前に、どのような建物が建築可能かしっかりと調査する必要があります。
見落としがちですが、土地が接する「道路の幅員」や「ライフラインの整備状況」も計画に大きな影響を与えます。接道する道路の幅が狭いと、建物の高さが制限されたり、工事車両が入れずに建築コストが割高になったりする場合があります。また、敷地まで水道管やガス管が引き込まれていない場合は、その引き込み工事に数百万円の追加費用が発生することも。土地の価値は、こうしたインフラの整備状況によっても大きく変わることを覚えておきましょう。
アパート経営において、単にコストを削るだけでは、魅力のない物件になり、結果として入居率の低下を招きます。目指すべきは、無駄なコストを戦略的に削減しつつ、その分を入居者の満足度向上に直結する「価値」へと再投資することです。この「コストダウン」と「価値向上」を両立させる設計手法こそが、長期的に安定した収益を生み出す鍵となります。
コストダウンの有効な手段として、ハウスメーカーなどが提供する「規格プラン」の活用があります。しかし、これが常に最適解とは限りません。判断のコツは、土地の形状が整形地か不整形地かを見極めることです。長方形などの整形地であれば、規格プランを効率的に当てはめやすく、コストメリットを最大限に享受できます。一方、旗竿地や変形地の場合は、規格プランでは対応しきれず、結局は自由設計の方が無駄のないプランになることもあります。
高断熱・高気密といった省エネ性能の向上や、IoTを活用したスマート設備への投資は、初期費用こそかかりますが、長期的に見れば非常に高い投資効果を生み出します。省エネ性能が高い物件は、入居者の光熱費負担を軽減するため、「経済的メリット」として強力なアピールポイントになります。また、スマートフォンで玄関の施錠や家電の操作ができるスマート設備は、若い世代の入居者に強く響き、家賃を相場より高く設定できる可能性も秘めています。
専有部だけでなく、共用部に投資することも、物件の価値を高める有効な手段です。
【差別化に繋がる共用部アイデアリスト】

机上の空論ではなく、実際に4,000万円台の予算でアパート建築を成功させたオーナーの事例には、学ぶべき戦略と知恵が詰まっています。エリアの特性を的確に読み解き、限られた予算を効果的に配分することで、高い収益性を実現したケーススタディは、あなたの計画にとって最高の教科書となるでしょう。
地方都市の大学近くの土地で、ターゲットを学生に絞り込むことで成功した事例です。4,000万円の予算で、管理のしやすい木造2階建て・1LDK6戸のアパートを建築。各部屋に高速インターネットと家具家電(冷蔵庫・洗濯機)を標準装備し、親元を離れる学生の初期費用負担を軽減しました。これが保護者からの絶大な支持を集め、入学シーズン前には常に満室に。地方都市でも、ターゲットを明確にすれば高稼働は実現できるという好例です。
都心へアクセスしやすい郊外の駅徒歩5分という好立地を活かした事例です。4,000万円の予算で、軽量鉄骨造3階建て・ワンルーム8戸を建築。オートロック、宅配ボックスはもちろん、共用部にワークスペースを設置し、リモートワーカーの需要を取り込みました。駅近の利便性と充実した設備が評価され、相場より5,000円高い家賃設定でも即満室に。土地のポテンシャルを最大限に引き出した戦略が功を奏したケースです。
4,000万円の建築費に、潤沢な自己資金や追加融資を組み合わせることで、木造や軽量鉄骨造よりも資産価値の高いRC(鉄筋コンクリート)造のコンパクトマンションへとステップアップする戦略もあります。RC造は建築費こそ高くなりますが、法定耐用年数が47年と長く、金融機関から超長期の融資を受けられる可能性があります。これにより、月々の返済額を抑えつつ、より高い耐久性と資産性を手に入れることができ、長期的な出口戦略まで見据えた盤石な投資となります。
まず「誰に、どんなアパートを貸すか」という事業の核を決め、総予算と自己資金、目標利回りを設定します。土地がない場合は土地探しを始め、並行して金融機関に融資の事前相談を行い、自身の借入可能額を把握することが、計画の第一歩となります。
事業計画を元に、理想のアパートを建ててくれる建築会社を探します。複数のハウスメーカーや工務店から資料を取り寄せ、実績やプランを比較検討しましょう。3社程度に候補を絞り、具体的なプランと概算見積もりを依頼して、最も信頼できるパートナーを選定します。
選んだ建築会社と、間取りや設備などの詳細設計を詰めていきます。最終的な仕様と金額が固まったら、見積書の内容を隅々まで確認し、工事請負契約を締結します。ここでの決定が、建物の品質とコストのすべてを左右する重要な段階です。
契約後、地鎮祭などを経ていよいよ着工します。工事が始まったら任せきりにせず、定期的に現場を訪れて進捗を確認しましょう。建物の品質を確保するため、配筋検査や構造検査など、重要な工程の検査に立ち会うことも大切です。
建物が完成したら、傷や不具合がないかを確認する「竣工検査」に必ず立ち会います。問題がなければ、金融機関でローン契約(金銭消費貸借契約)を結び、残金を決済。登記手続きを済ませ、ついに建物があなたの資産として引き渡されます。
引き渡しが済んだら、家賃集金やクレーム対応を委託する管理会社を選定します。並行して、家賃を設定し、入居者の募集を開始します。最初の入居者が決まり、家賃収入が生まれた瞬間から、あなたの「アパート経営」が本格的にスタートします。
4,000万円のアパート投資は、適切な知識と準備があれば、個人の資産形成における強力なエンジンとなり得ます。成功の鍵は、曖昧な計画を具体的な数値に落とし込み、リスクを正確に把握し、信頼できるパートナーと共にプロジェクトを推進することです。本記事で得た知見を元に、まずはあなたの理想とするアパートの収支計画をシミュレーションすることから始めてください。その一歩が、夢を現実に変えるための確かな行動指針となるはずです。