超高利回りアパート投資の秘密
\\\知りたい方はこちら///


監修者

株式会社Riel 代表取締役
坂口 卓己(サカグチ タクミ)
宅地建物取引士として年間57棟の販売実績を誇り、東京都渋谷を拠点に新築アパートの企画開発から資金計画、満室運営、出口戦略まで一貫支援。豊富な現場経験と最新市況データを融合し、信頼とスピードを重視したサービスで投資家一人ひとりに最適な資産形成プランを提案する不動産投資のプロフェッショナル。
⇒詳細はこちら
建築費6,000万円という予算は、もはや単なる資産運用ではなく、本格的な「不動産事業」への挑戦を意味します。この規模になると、戸数や間取り、設備グレードの選択肢が飛躍的に広がり、エリアの特性に合わせた多彩な事業戦略を展開できます。この記事では、6,000万円で実現できるアパートの具体像から、詳細なコスト分析、融資戦略、そしてリアルな収益構造までを徹底的に解剖。あなたの事業計画を成功へと導く、確かな羅針盤となります。
建築費6,000万円は、地域やターゲットに合わせたオーダーメイドの戦略が可能な、本格的アパート事業のスタートラインです。戸数や階数、間取りの組み合わせに大きな自由度が生まれ、事業としての収益性と安定性を高いレベルで両立させやすくなります。10戸以上の規模や、異なる間取りを組み合わせた複合型プランも十分に視野に入るでしょう。まずはこの予算でどのようなアパートが実現できるのか、その全体像を具体的に描くことが重要です。
6,000万円の予算規模では、木造なら3階建て10~12戸、軽量鉄骨なら同じく3階建て8~10戸が一つの目安となります。以下の表で、構造ごとのプランの選択肢を比較してみましょう。
建築費6,000万円という予算規模では、どのようなアパート建築が可能になるのでしょうか。建物の構造によって、実現できる階数や戸数、そして事業戦略が大きく変わってきます。以下に代表的な3つのモデルプランを比較します。
| 構造タイプ | 戦略モデル | 想定プラン (階数・戸数・間取り) | 特徴と主なターゲット |
| 木造 (W造) | 利回り最大化 | 3階建て 10~12戸(ワンルーム) | コストを抑えて戸数を最大限に確保。駅近などの好立地で高い利回りを追求する。ターゲットは利便性を求める学生や社会人単身者。 |
|---|---|---|---|
| 軽量鉄骨造 (S造) | バランス追求 | 3階建て 8~10戸(1K / 1LDK) | 耐久性とプランの自由度を両立。質の高い住環境を提供し、やや高めの家賃でも入居が見込める層を狙う。 |
| 重量鉄骨造 (S造) | 安定性・差別化 | 2階建て 4~6戸(2LDK) | 柱の少ない広々とした空間を活かし、競合の少ないファミリー向け物件で差別化。長期入居による安定経営を目指す。 |
| 鉄筋コンクリート造 (RC造) | 資産価値重視 | 3階建て 6~8戸(1LDK) | 最高の耐久性と住環境で、長期にわたり資産価値を維持。高所得の単身者やDINKSをターゲットに、高家賃設定を狙う。 |
【計画のポイント】
土地の用途地域や建ぺい率・容積率といった法規制によって、建築できる階数や規模は変動します。ご自身の土地のポテンシャルと、どのような入居者に住んでほしいかを考え、最適なプランを選択することが重要です。

建築費6,000万円を投じる場合、延床面積90~100坪(約300~330㎡)規模のプランが、標準的なターゲットゾーンとなります。この延床面積が、建築コストと確保できる戸数、そして将来の家賃収入とのバランスを考慮した際に、最も効率的なボリュームになりやすいためです。例えば、延床面積90坪であれば、単身者向けの1K(約7.5坪)を12戸確保するプランが考えられます。これを実現するには、建ぺい率・容積率にもよりますが、最低でも70坪以上の敷地が必要となるでしょう。
6,000万円の予算規模であれば、単一の間取りで構成するよりも、複数の間取りを組み合わせる「ミックスプラン」が非常に有効な戦略となります。なぜなら、多様な入居者ニーズに対応することで、空室リスクを効果的に分散させ、収益の安定化を図ることができるからです。例えば、駅近の土地であれば、単身者向けの1Kを主体にしつつ、カップルや新婚向けの1LDKを数戸混ぜることで、幅広い層にアプローチできます。1階部分を防犯面に配慮したファミリー向けの2LDKにするなど、階層でターゲットを分ける設計も考えられます。
この価格帯の物件では、競合物件も質が高いため、標準的な設備に加えて、一歩進んだ付加価値で差別化を図る必要があります。
標準装備(必須クラス)
差別化(付加価値クラス)
総工費6,000万円という大きな金額を動かすには、その費用が何に、いくら使われるのかを正確に分解し、把握することが不可欠です。以下の配分モデルを参考に、ご自身の計画に潜むコストを漏れなく洗い出しましょう。
総予算6,000万円という大規模なプロジェクトを成功に導くには、まず「何に、いくらかかるのか」という費用の全体像を正確に把握することが不可欠です。予算は大きく分けて「①建物本体工事費」「②付帯工事費」「③諸経費」の3つで構成されます。この配分を理解しておくことで、資金計画の精度が格段に向上し、予期せぬ予算オーバーを防ぐことができます。
| 費用項目 | 比率の目安 | 概算金額 | 主な内容 |
| ① 建物本体工事費 | 約70% | 4,200万円 | 建物の基礎や骨組み、屋根、外壁、内装、キッチン・バス・トイレといった住宅設備の工事費用。 |
|---|---|---|---|
| ② 付帯・外構工事費 | 約20% | 1,200万円 | 地盤改良、給排水・ガス管の引き込み、駐車場やアプローチ、フェンスなどの屋外工事費用。 |
| ③ 設計料・諸経費 | 約10% | 600万円 | 設計料、建築確認申請費、登記費用、不動産取得税、火災保険料、ローン手数料など。 |
| 合計 | 100% | 6,000万円 |
【計画のポイント】
3つの費用項目のうち、最も変動しやすいのが「②付帯・外構工事費」です。土地の形状、地盤の強度、インフラの整備状況など、個別の条件によって費用が大きく変わるため、計画の初期段階で入念な調査と詳細な見積もり取得を心掛けましょう。
建物本体価格(総工費の約7割、4,200万円が目安)のコスト管理では、削るべき部分と投資すべき部分のメリハリが重要です。コストを抑えるには、外壁や屋根材などを標準グレード品から選んだり、建物の形状をシンプルな総二階にしたりする方法があります。その一方で、浮いた費用を断熱性能の向上や、入居者満足度に直結するキッチン・バスなどの設備に再投資(アップグレード)することで、物件の価値を大きく高めることが可能です。
外構・インフラ整備費(総工費の約2割、1,200万円が目安)は、土地の状況によって大きく変動し、想定外の追加費用が発生しやすい項目です。例えば、前面道路に埋設された水道管の口径が小さい場合、引き込み直しに100万円以上の費用がかかることがあります。また、地盤が軟弱であれば地盤改良工事が必須となり、これも100万円単位の出費に。これらのリスクを避けるためにも、土地の契約前に専門家による詳細な調査を行うことが極めて重要です。
建築工事費以外に必要な諸経費は、総工費の約1割、つまり600万円前後を目安に現金で準備しておく必要があります。資金計画に漏れがないよう、以下のリストで確認しましょう。
【諸経費チェックリスト】
設計事務所や建築会社に支払う「設計監理料」は、一般的に「総工事費の〇%」という料率方式で算出されます。この料率は会社によって異なり、8~15%が相場です。一方、役所に支払う「建築確認申請料」は、建物の延床面積に応じて金額が定められています。これらの費用は、事業の初期段階で発生する重要なコストです。契約前に課金方式と金額を明確に確認し、不明な点は納得がいくまで質問することが大切です。
6,000万円という大規模な投資を成功させるには、盤石な資金計画と、自身にとって最も有利な融資を引き出すための戦略が不可欠です。自己資金をどの程度用意し、どの金融機関から、どのような条件で融資を受けるか。この初期段階での判断が、事業全体のキャッシュフロー、ひいては最終的な利益を大きく左右することになります。
6,000万円のプロジェクトにおいて、安全圏と言える自己資金の目安は、総事業費の15~20%、つまり900万円~1,200万円です。金融機関は、自己資金の額を事業への本気度やリスク管理能力の指標と見なすため、この比率が高いほど融資審査は有利に進みます。また、潤沢な自己資金は、建築中の追加費用や、竣工後の突発的な修繕に備えるためのバッファーとなり、経営の安定性を大きく高める効果があります。
融資の相談先は、メガバンクだけでなく、地域の地方銀行(地銀)、信用金庫(信金)、さらにはノンバンクまで幅広く検討すべきです。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合った金融機関を選びましょう。
| 金融機関の種類 | メリット | デメリット(注意点) |
| 地方銀行・信用金庫 | 地域の事業性を評価してくれやすい、親身な対応が期待できる | 金利はメガバンクよりやや高い傾向、融資エリアが限定される |
|---|---|---|
| メガバンク | 金利が低い傾向、全国対応が可能 | 個人の属性(年収など)重視で、事業性評価の優先度は低い |
| ノンバンク | 審査がスピーディ、柔軟な融資姿勢 | 金利が最も高い傾向、手数料なども含めた総コストで比較が必要 |
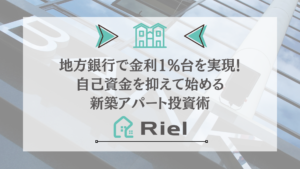
金利タイプ(固定か変動か)の選択は、長期的な返済計画に大きな影響を与えます。それぞれの特性を理解し、自身のリスク許容度に合わせて選択することが重要です。
| 金利タイプ | メリット | デメリット |
| 変動金利 | 当初の金利が低い、金利低下の恩恵を受けられる | 将来の金利上昇リスクを負う、返済額が増える可能性がある |
|---|---|---|
| 固定金利 | 返済額が一定で将来の計画が立てやすい、金利上昇の不安がない | 当初の金利が変動より高い、金利が低下しても恩恵を受けられない |
不動産事業の成功は、どれだけ精度の高いキャッシュフロー設計ができるかにかかっています。希望的観測で家賃を設定するのではなく、周辺の賃貸市場を徹底的に調査し、現実的な「想定家賃」を算出。そこから経費やローン返済を差し引き、最終的に手元にいくら現金が残るのかを逆算する。このプロセスこそが、事業の実現可能性とリスクを可視化する唯一の方法です。
広告などで目にする「表面利回り」は、あくまで参考値です。実際の収益力を測るには、運営経費を考慮した「実質利回り」を算出しなければなりません。両者の差を生む主な要因は、①管理会社に支払う管理委託費、②固定資産税・都市計画税、③火災保険料などの保険料、そして④将来のための修繕積立金です。これらの経費は、一般的に年間家賃収入の15~20%に相当します。この差を理解せずに事業計画を立てることは非常に危険です。
満室経営は理想ですが、常に実現できるとは限りません。そのため、空室リスクを織り込んだ事業計画を立てることが不可欠です。以下の試算例のように、稼働率の低下がキャッシュフローに与えるインパクトを数値で把握しておきましょう。
満室経営は理想ですが、常に実現できるとは限りません。そこで、事前に「もし空室が出たらどうなるか?」をシミュレーションし、ご自身の計画がどれくらいの空室に耐えられるのか(リスク耐性)を把握しておくことが、事業を成功させる上で極めて重要です。
ここでは、以下の条件で稼働率が変動した場合のキャッシュフローを試算します。
【シミュレーションの前提条件】
| 稼働率 (空室数目安※) | 年間家賃収入 | 年間キャッシュフロー(税引前) | オーナーの状況 |
| 100% (空室なし) | 480万円 | 184万円 | 健全 計画通りの収益。将来の大規模修繕や繰り上げ返済のための資金を十分に蓄積できる状態。 |
|---|---|---|---|
| 90% (約1戸空室) | 432万円 | 136万円 | 要注意 まだ十分な利益は出ているが、満室時よりキャッシュフローは26%減少。空室が長期化しないか注視が必要。 |
| 80% (約2戸空室) | 384万円 | 88万円 | 警戒レベル 手残りが半分以下に。急な修繕など想定外の出費が発生すると、資金繰りが一気に厳しくなる可能性がある。 |
※10戸のアパートを想定した場合の空室数
さらに重要なのは、キャッシュフローがゼロになる「損益分岐点稼働率」を知っておくことです。
【計算式】
(年間運営経費 + 年間返済額) ÷ 年間満室家賃収入 = 損益分岐点稼働率
【この例での計算】
(96万円 + 200万円) ÷ 480万円 = 296万円 ÷ 480万円 = 61.7%
これは、稼働率が61.7%を下回ると、アパート経営が赤字になることを意味します。10戸のアパートであれば、常に7戸以上入居していれば赤字にはなりませんが、6戸以下(4戸以上の空室)になると持ち出しが発生する、という具体的なリスクラインが分かります。
アパート経営のキャッシュフローを正確に把握するためには、収入から支出が引かれていく流れを可視化すると有効です。
アパート経営の収益性を正確に把握するために、家賃収入が手元に残る現金(キャッシュフロー)になるまでの流れを分解してみましょう。
全ての部屋が1年間満室だった場合の、理論上の最大収入です。
空室期間や家賃滞納による損失分。一般的に満室想定家賃の5%~10%を見込みます。
空室損失などを差し引いた、より現実的な年間収入です。
空室損失などを差し引いた、より現実的な年間収入です。
物件そのものが持つ、純粋な収益力(儲け)を示します。ローン返済を含まないため、物件の価値を測る重要な指標です。
金融機関へ支払う、年間のローン返済額(元金+利息)です。
すべての支出を支払った後、最終的にオーナーの手元に残る年間の現金です。この金額がプラスであることが、アパート経営の最低条件となります。

アパート建築は、土地のポテンシャルと法規制という制約の中で、最大のパフォーマンスを引き出すゲームとも言えます。優れたプランニングとは、建築規制を単なる障害と捉えるのではなく、むしろ設計の指針として味方につけ、その土地で実現可能な収益性を最大限に高めることに他なりません。土地選定の段階から、これらの法規制を深く理解しておくことが、事業の成否を分けます。
収益性を最大化するためには、指定された容積率(敷地面積に対する延床面積の上限)を、いかに上限近くまで使い切れるかが鍵となります。容積率をフル活用できるのは、前面道路の幅員が広く、土地の形状が整形であるといった条件の揃った敷地です。また、角地であれば建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)が緩和されるなど、ボーナス規定も存在します。土地の価格だけでなく、これらの条件も考慮して、最も投資効率の高い敷地を選ぶべきです。
建物のデザインやボリュームは、前面道路の幅員や、そこから発生する「斜線制限」(道路斜線、北側斜線など)によって大きく左右されます。例えば、前面道路が狭いと、上階にいくほど建物を後退(セットバック)させる必要があり、有効な床面積が削られてしまいます。これにより、計画していた戸数が確保できなくなることも。土地選びの段階で、これらの斜線制限がプランにどのような影響を与えるかを、建築士などの専門家と共に確認することが不可欠です。
土地には、都市計画法によって13種類の「用途地域」が定められており、それぞれ建てられる建物の種類や規模が異なります。例えば、「第一種住居地域」は、静かな住環境が保たれているため、ファミリー向けの安定した需要が見込めます。一方、「商業地域」では、駅近の利便性を活かした単身者向けの収益性の高い物件が狙えます。このように、用途地域の特性を理解し、そこで求められる賃貸ニーズに合致したアパートを計画することが、エリアマーケティングの基本となります。
限られた予算の中でアパートの競争力を高めるには、戦略的なコスト管理と、入居者の心に響く付加価値の創出を両立させる必要があります。無駄なコストは徹底的に削減し、その分を物件の魅力を高める要素へと再投資する。この賢い設計アプローチこそが、「安かろう悪かろう」ではない、真に価値のある物件を生み出すのです。
コストダウンの有効な手法として、ハウスメーカーの「規格プラン」の活用が挙げられます。しかし、すべてを規格品で固めると、没個性的な物件になりかねません。そこで重要なのが、規格プランをベースにしつつ、入居者の目に触れやすい部分だけをカスタムする視点です。例えば、エントランスのタイルや照明、各戸の玄関ドアやキッチン設備など、ピンポイントでデザイン性の高いものに変更すれば、全体の印象を大きく向上させ、費用対効果の高い差別化が図れます。
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準を満たすような高断熱・高気密の省エネアパートは、初期投資こそかさみますが、長期的に見れば非常に高いリターンが期待できます。国からの補助金が受けられるだけでなく、「光熱費が安い」という点は、入居者にとって非常に分かりやすく、強力なアピールポイントとなります。特に、昨今の電気代高騰を背景に、この訴求力はますます高まっています。これは、将来にわたって物件の競争力を維持するための、賢明な先行投資と言えるでしょう。
入居者の満足度を大きく左右するのが、日々の「生活動線」です。特に、収納と水回りの配置は、その物件の暮らしやすさを決定づける重要な要素となります。例えば、玄関横に大型のシューズインクロークを設けたり、キッチンから洗面室、浴室への動線をコンパクトにまとめたりする工夫が挙げられます。また、デッドスペースを活かしたパントリーやリネン庫の設置も喜ばれます。こうした細やかな配慮が、内見時の印象を格段に高め、入居の決め手となるのです。

机上の空論で終わらせないために、実際に6,000万円クラスの投資で成功を収めたオーナーの事例から、具体的な「勝ちパターン」を学びましょう。彼らがどのように市場を読み、どのような戦略で物件を計画し、高い収益性を実現したのか。そのリアルなストーリーは、あなたの事業計画を成功へと導くための、何よりの道しるべとなるはずです。
人口30万人の地方主要都市、駅から徒歩10分の土地での成功事例です。ターゲットを地域の有力企業に勤める単身者と定め、木造3階建て・1K9戸のアパートを約6,000万円で建築。オートロック、無料Wi-Fiはもちろん、全戸にウォークインクローゼットと広めの独立洗面台を設置し、質の高い単身生活を提案しました。これが近隣の新築物件との差別化となり、相場より高い家賃でも安定した高稼働を実現。実質利回り8%を達成しています。
都心まで電車で40分の郊外ベッドタウンでの事例です。軽量鉄骨造3階建て・ワンルーム12戸のアパートを建築。コストを抑えるため内装はシンプルにしつつ、共用部に力を入れ、宅配ボックスはもちろん、入居者専用のコインランドリーとワークラウンジを設置しました。これが、在宅勤務の多い若い世代や、洗濯機を置きたくないミニマリストに響き、竣工以来95%以上の高い稼働率を維持。共用部の付加価値で成功した好例です。
将来の社会情勢や入居者ニーズの変化に対応するため、あらかじめリノベーションしやすい「可変プラン」を採用した戦略的な事例です。例えば、隣り合う2つのワンルームの間の壁を、将来的に撤去しやすい乾式壁で施工。単身者需要が減り、カップル需要が増えた際には、壁を撤去して2つの部屋を繋げ、広い1LDKに間取り変更できるように設計しました。初期段階でこの工夫を盛り込むことで、将来の市場変化に柔軟に対応できる、息の長い物件となっています。
6,000万円という大規模なアパート投資を成功させるには、情熱だけでなく、冷静な分析と着実な実行が不可欠です。この記事を参考に、ご自身の計画が成功の軌道に乗っているか、以下の7つのポイントで自己評価してみてください。