超高利回りアパート投資の秘密
\\\知りたい方はこちら///


監修者

株式会社Riel 代表取締役
坂口 卓己(サカグチ タクミ)
宅地建物取引士として年間57棟の販売実績を誇り、東京都渋谷を拠点に新築アパートの企画開発から資金計画、満室運営、出口戦略まで一貫支援。豊富な現場経験と最新市況データを融合し、信頼とスピードを重視したサービスで投資家一人ひとりに最適な資産形成プランを提案する不動産投資のプロフェッショナル。
⇒詳細はこちら
土地からアパートを新築する投資は、高い収益性と自由な設計が魅力ですが、その裏には中古物件とは比較にならないほど多くの「特有リスク」が潜んでいます。土地の選定ミス、想定外の建築コスト、煩雑な行政手続きなど、見落としがちな落とし穴は事業計画を根底から揺るがしかねません。本記事では、土地からの新築アパート経営に潜むリスクの全体像を体系的に解説し、失敗を未然に防ぐための具体的な回避策を、専門家の視点から余すところなくお伝えします。
土地からアパートを新築する際には、土地そのもの、建築過程、そして運営開始後と、多段階にわたる特有のリスクが存在します。更地から建物を建てるプロセスは、完成済みの物件を購入する場合と異なり、非常に多くの不確定要素を含むからです。
土地から新築アパートを建てるプロセスには、大きく分けて以下の6つのリスクカテゴリーが存在します。
これらの各フェーズのリスクを事前に把握し、体系的に対策を講じることがアパート経営成功の鍵を握っているのです。

土地の購入で最も注意すべきは、目に見えない法的制限や物理的な障害です。これらは計画を根本から覆す危険をはらんでいるため、購入前の調査が欠かせません。例えば、建築基準法で定められた接道義務を満たさない土地には建物を建てられませんし、想定外の公法上の制限があれば計画通りの規模の建物が建築不可能になるケースもあります。また、過去の土地利用に起因する地中埋設物(古井戸や浄化槽など)が発見されれば、高額な撤去費用が追加で発生することになるでしょう。したがって、土地の仕入れ前には専門家による徹底した調査が不可欠です。
理想のプランを描けても、行政の許認可や近隣住民の同意が得られなければ、計画は進みません。この不確実性が大きなリスクとなります。建築は建築基準法や各種条例に厳しく規制されており、特定の開発行為には行政の許可が必要なうえ、近隣トラブルは工期に直接影響を与えかねません。例えば、一定規模以上の開発に必要な「開発許可」の取得に数ヶ月を要するケースや、日照権などを巡る近隣住民との協議が難航し、設計変更や工期遅延を余儀なくされることもあります。設計段階から行政協議を重ね、近隣への配慮を盛り込むことが、スムーズな進行の鍵を握ると言えるでしょう。
建築工事には、工期やコストが計画通りに進まないリスクが常につきまといます。特に近年では、世界的な情勢不安や円安の影響で建築資材の価格が高騰し、当初の見積もりから大幅にコストが上昇するケースが後を絶ちません。また、建設業界の人手不足を背景とした工期の遅延や、施工会社による品質のばらつきも無視できない問題です。これらのリスクは、事業の採算性を直接悪化させる要因となります。信頼できる施工会社を選定するとともに、契約内容を精査し、予備費を設けるなどの対策を講じておく必要があります。
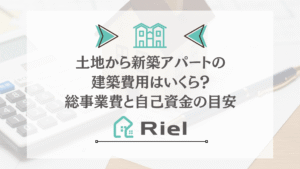
新築アパート経営の事業計画は、「想定賃料」という予測に基づいています。しかし、この想定が市場の実態と乖離していると、計画は絵に描いた餅に終わってしまいます。周辺の競合物件の供給過多や、ターゲットとする入居者層のニーズとのミスマッチにより、想定した賃料では入居者が決まらず、値下げを余儀なくされるかもしれません。また、竣工から満室になるまでのリーシング期間が想定より長引けば、その間の収入はゼロとなり、資金繰りを圧迫します。机上の空論で終わらせない、徹底したマーケティングリサーチが不可欠です。
金融機関からの融資は、アパート経営の生命線ですが、ここにも変動リスクが潜みます。融資額の評価基準であるLTV(総資産有利子負債比率)やLTC(総事業費に対する借入金の割合)は、金融機関の方針や経済状況によって変動し、想定していた額の融資が受けられない可能性があります。また、変動金利でローンを組む場合は、将来的な金利上昇が返済額を増やし、キャッシュフローを悪化させるリスクを常に念頭に置かなければなりません。土地決済から建物竣工までの「つなぎ資金」の確保も忘れてはならないポイントです。
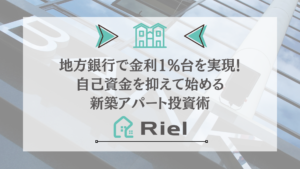
アパート経営には、税務や保険、そして自然災害といった避けられないリスクも存在します。土地と建物を所有すると毎年課される固定資産税・都市計画税の負担や、減価償却の計算方法による節税効果の違いなど、税務知識は収益に直結します。さらに、日本は地震や水害などの自然災害が多い国であり、火災保険や地震保険への加入は必須です。しかし、保険だけではカバーしきれない損害が発生する可能性もゼロではありません。事前にハザードマップを確認するなど、物理的なリスク評価も重要になります。

「デューデリジェンス」とは、投資対象の価値やリスクを精査する手続きのことです。土地から新築アパートを建てる場合、この仕入れ前の調査が事業の成否を分けるといっても過言ではありません。目に見える土地の形状だけでなく、法規制、地盤の状態、インフラの整備状況など、多角的な視点からリスクを洗い出し、一つひとつ潰していく作業が不可欠です。この段階を疎かにすると、後々取り返しのつかない問題に直面する可能性があります。
土地の安全性を確認するには、以下の3ステップで進めましょう。
過去の土地利用履歴を調べ、可能であれば地盤調査を実施し、軟弱地盤のリスクを評価します。
地盤改良などが必要な場合、どの程度の追加費用がかかるのかを事前に見積もっておきます。
その土地にどれくらいの規模の建物を建てられるかは、都市計画法や建築基準法によって厳密に定められています。まず「用途地域」を確認し、アパートの建築が可能かを確認します。次に「建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)」と「容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)」で建物の大きさが決まります。さらに、道路斜線制限や日影規制といった高さに関する制限も考慮しなければなりません。これらの規制を正確に読み解かないと、想定していた戸数を確保できず、事業計画が破綻してしまいます。
建物を建てるためには、その敷地が建築基準法上の道路に原則2m以上接している必要があります(接道義務)。前面道路の幅員が4m未満の場合、セットバックが必要となり、その部分は敷地面積に算入できません。また、前面道路が私道の場合は、所有関係や、上下水道管などを引き込む際の通行・掘削承諾が円滑に得られるかどうかの確認が極めて重要です。
 Rielからのアドバイス
Rielからのアドバイス私道に接する土地はトラブルの宝庫です。過去には、私道所有者から高額な承諾料を要求されたり、相続によって所有者が変わり話がこじれたりするケースも見てきました。「通行・掘削に関する承諾書」を書面で取得することは絶対条件です。少しでも不安があれば、購入を見送る勇気も必要です。
隣地との境界が明確になっているかは、将来のトラブルを避けるために必ず確認すべき点です。境界標がなければ、土地家屋調査士による境界確定測量が必要になります。また、隣地の塀や木の枝が敷地に越境していないか、逆にこちらの所有物が越境していないかもチェックしましょう。さらに、登記簿に記載のない地役権(他人の土地を通行できる権利など)や、古井戸、過去の建物の基礎杭、燃料タンクといった地中埋設物が存在する可能性も考慮しなければなりません。
アパートを建設するには、電気、ガス、上下水道といった生活インフラの引き込みが必須です。しかし、前面道路に配管が埋設されていなかったり、容量が不足していたりする場合があります。特に、下水道が整備されていないエリアでは、浄化槽の設置が必要となり、コストと維持管理の手間が増加します。インフラの引き込み工事費用や、水道事業者に支払う加入金なども事前に各事業者に確認し、事業費に正確に織り込む必要があります。
物理的な土地のリスク調査と並行して、その土地で本当に賃貸経営が成り立つのかというマーケティング調査が不可欠です。最寄り駅からの距離やアクセス、周辺の商業施設や公共施設の充実度といった入居者にとっての利便性を客観的に評価します。同時に、周辺エリアの競合アパートの供給状況、家賃相場、空室率を徹底的に調査し、自身の計画に無理がないかを検証してください。誰に(ターゲット)、いくらで(賃料)、どのような部屋を(商品企画)提供するのか。この戦略が土地のポテンシャルと合致しているかを見極めることが重要です。
アパート経営の事業計画は、希望的観測ではなく、常に「想定通りには進まない」という前提で策定すべきです。建築費の高騰、想定賃料の下落、金利の上昇など、様々な不確定要素を考慮したシミュレーションが不可欠です。表面的な利回り(粗利)だけでなく、より実態に近い指標を用いて収益性を判断し、複数のシナリオでストレステストを行うことで、計画の脆弱性を見抜き、リスクへの耐性を高めることができます。
事業計画の妥当性を判断する際、単純な表面利回りだけを見るのは危険です。より実態に近い収益性を測るためには、NOI(営業純利益)を用いるべきです。NOIは、満室想定賃料から空室損と運営経費を差し引いた利益であり、物件本来の収益力を示します。さらに、金融機関が融資審査で重視するDSCR(借入金償還余裕率)も確認しましょう。これはNOIが年間返済額の何倍あるかを示す指標で、1.2以上が一つの目安とされています。
事業計画の甘さを炙り出すために、感度分析は非常に有効な手法です。これは、特定の変数が変動した場合に、最終的な利益がどれだけ影響を受けるかを試算するものです。例えば、周辺に競合の新築アパートが建った場合を想定し、設定賃料を5%~10%下げたシナリオでシミュレーションしてみましょう。
【感度分析シミュレーション例】
| シナリオ | 賃料変動 | 稼働率 | 年間キャッシュフロー |
| 基本計画 | ±0% | 95% | +200万円 |
|---|---|---|---|
| 賃料下落ケース | -5% | 95% | +80万円 |
| 稼働率低下ケース | ±0% | 90% | +50万円 |
| ワーストケース | -10% | 90% | -80万円(赤字) |
自己資金1,500万円を投資した場合の具体的なシミュレーションは以下の通りです。
| 項目 | 金額 |
| ① 家賃収入 | ¥10,224,000 |
|---|---|
| ② ローン返済 | ¥4,376,077 |
| ③ ランニングコスト | ¥697,392 |
| ④ 固定資産税 | ¥550,000 |
| 年間キャッシュフロー (①-②-③-④) | ¥4,600,531 |
| 自己資金に対する年間利回り | 30.7% |
※この年間キャッシュフローは、年収600万円の手取り額に相当します。
10年間運用した後に物件を売却した場合の収益モデルです。
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 想定売却価格 | ¥116,298,000 | |
|---|---|---|
| 10年後のローン残債 | ¥96,154,100 | |
| 売却益 | ¥20,143,900 | (売却価格 - ローン残債) |
※売却価格は、新築時から家賃が9%下落し、売却時の利回りが8.0%であると想定して算出されています。
上記のシミュレーションに基づくと、10年間で得られる利益の合計は以下のようになります。
| 項目 | 金額 |
| キャッシュフロー(10年分) | ¥40,583,521 |
|---|---|
| 売却益 | ¥20,143,900 |
| TOTAL 利益 | ¥60,727,421 |
この結果、当初投資した自己資金1,500万円が、10年間で約4倍に増加する計算となります。
変動金利で融資を受ける場合、金利上昇は最大のリスクの一つです。将来の金利がどう動くかは誰にも予測できないため、予め金利が上昇しても耐えられる計画を立てる必要があります。現在の借入金利に+1.0%、さらに厳しく+2.0%を上乗せした場合でも、返済が滞らないか、キャッシュフローがどう変化するかをストレステストで確認してください。同時に、家賃収入に占めるローン返済額の割合である「返済比率」もチェックします。この比率が50%を超えてくると、赤字に転落しやすくなるため、40%台に抑えるのが理想的です。



金利のストレステストは必ず「手取りキャッシュフロー」ベースで行ってください。表面的な収支で「プラスだから大丈夫」と判断するのは危険です。税金(固定資産税、所得税など)を支払った後の、最終的に手元に残るお金が、金利上昇後もプラスを維持できるかが最も重要です。私たちは、税引き後CF(キャッシュフロー)でのシミュレーションを徹底しています。
建築費は、当初の見積もりから変動する可能性が高い費目です。特に、工事請負契約書に「建築費スライド条項」が含まれている場合、着工後に資材価格や人件費が著しく上昇した際に、施工会社から追加の費用を請求される可能性があります。契約内容を十分に確認するとともに、総事業費とは別に、建築費の10%~15%程度の予備費をあらかじめ資金計画に組み込んでおきましょう。
新築物件が竣工してから満室になるまでの期間(リーシング期間)は、家賃収入が入ってこない「持ち出し」の期間です。この期間を楽観的に見積もると、資金繰りが一気に悪化します。最低でも3~6ヶ月は満室にならない前提で資金計画を立てましょう。また、入居者募集を促進するために、不動産仲介会社に支払う広告料(AD)や、一定期間の家賃を無料にするフリーレント(FR)といった費用も、当初から経費として見込んでおく必要があります。
どれだけ立地が良く、立派な建物を建てたとしても、そのエリアの入居者ニーズに合っていなければ、空室という結果を招きます。設計・商品企画の失敗は、アパート経営における致命的なリスクです。市場調査を基に、ターゲットとなる入居者層を明確に定め、その人たちのライフスタイルや価値観に響く間取り、設備、デザインを提供することが成功の鍵となります。
アパートの収益性を最大化するためには、その土地の賃貸需要に合わせた最適な間取りの組み合わせを考える必要があります。例えば、大学が近いエリアであれば単身者向けの1K、都心に近いターミナル駅であればDINKS向けの1LDK、郊外の住宅街であればファミリー向けの2LDKといった具合です。複数の間取りを組み合わせることで、入居者層が広がり、空室リスクを分散させる効果も期待できます。


現代の入居者は、「住み心地」や「利便性」を重視します。入居者が内見時にチェックする重要ポイントを押さえた設備投資が、競合との差別化につながります。
特に以下の設備は入居決定に大きく影響します。


アパート経営では、居室以外の附帯施設も軽視できません。多くの自治体では、条例によって戸数に応じた駐輪場やゴミ置場の設置が義務付けられています。これらのスペースを計画段階で確保しておかないと、後で設計変更が必要になる場合があります。また、ゴミ置場の位置によっては、臭いや衛生面で入居者トラブルの原因となることもあります。清掃業者や入居者が使いやすい管理動線にも配慮した配置計画が求められます。
近年、住宅の省エネ性能に対する関心は非常に高まっています。断熱性能を高め、エネルギー効率の良い設備を導入することは、入居者にとっては光熱費の削減という直接的なメリットになり、物件の付加価値を高めます。国が推進するZEH(ゼッチ)水準を満たすことで、物件の競争力が高まるだけでなく、国や自治体からの補助金を受けられる可能性もあります。
行政からの許認可取得や、近隣住民への説明といったプロセスには、想定以上の時間とコストがかかることがあります。これらの「見えないリスク」を軽視していると、計画が大幅に遅延し、事業の採算性が悪化する恐れがあります。
一定規模以上の宅地造成を行う場合や、市街化調整区域内で建築を行う場合には、都道府県知事の「開発許可」が必要となり、手続きに数ヶ月から1年以上かかることもあります。また、購入した土地の地目が「畑」や「田」である場合、「農地転用」の許可申請を行わなければなりません。さらに、敷地が遺跡(埋蔵文化財包蔵地)の範囲内にある場合、工事に先立って発掘調査が必要となり、多大な時間と費用が発生する可能性も考慮しておくべきです。
建築基準法などの全国一律の法律だけでなく、各自治体が独自に定める「条例」にも注意が必要です。特に、歴史的な街並みが残る地域や、自然豊かな地域では、建物のデザイン、色彩、高さ、さらには屋外広告物に至るまで、厳しい制限を課す「景観条例」が定められていることがあります。土地を検討する段階で、必ず役所の担当窓口で、地域独自の規制がないかを確認しましょう。
アパートの建築工事は、近隣住民の生活に少なからず影響を与えます。以下のフローで進めるのがおすすめです。
建物が図面通りに、かつ高い品質で建てられなければ意味がありません。施工段階では、手抜き工事や施工ミスといった品質リスク、施工会社の倒産リスクなどが存在します。
建物の品質を確保するためには、行政が行う検査だけでは不十分な場合があります。特に、完成後は見えなくなってしまう構造躯体(基礎の配筋など)や、雨漏りの原因となる防水工事は、専門家によるチェックが非常に重要です。設計者や施工会社とは独立した、第三者の建築士に依頼して、工事の重要な節目で現場を検査してもらうことをお勧めします。



第三者検査は慎重行うべきです。もちろん誠実な施工会社がほとんどですが、現場の職人一人のミスが将来の大きな瑕疵に繋がることもあります。私たちは、お客様の資産を守るため、標準で第三者機関による複数回の現場検査を導入しています。これは、事業主にとって必須の「保険」だと考えてください。
万が一、工事の途中で施工会社が倒産してしまうと、工事は中断し、事業計画に甚大な影響が出ます。契約前に施工会社の経営状況を調査(与信調査)することが重要です。また、工事代金の支払い条件もリスク管理の観点から交渉しましょう。工事の進捗に応じて支払う「出来高払い」を基本とし、引渡し後に瑕疵が見つかった場合の担保として、工事代金の数%を一定期間支払わずに留保する「保留金」の設定も有効な手段です。
新築住宅には、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、引渡しから10年間の瑕疵担保責任が法律で義務付けられています。施工会社は、この責任を果たすため、「住宅瑕疵担保責任保険」への加入が必須です。この保険に加入していれば、万が一施工会社が倒産しても、補修費用が保険法人から支払われます。契約前に保険への加入はもちろん、保証の具体的な範囲や、引渡し後のアフターサービス体制がどのようになっているかを確認しましょう。
建物が無事に完成しても、すぐに入居者が集まり、安定した経営が始まるわけではありません。竣工後の賃貸募集と運営フェーズにも、計画通りに進まないリスクが潜んでいます。
新築物件の最初の募集賃料は、その後の経営を左右する極めて重要な決定です。高すぎれば入居者が決まらず、安すぎれば将来にわたって収益性が低下してしまいます。周辺の競合物件の賃料や設備、築年数などを徹底的に調査し、適正な価格を見極める必要があります。また、募集開始時の初期販促も重要です。仲介会社への広告料(AD)を適切に設定し、魅力を最大限に伝えるための高品質な写真を用意するなど、戦略的なリーシング活動を展開しましょう。
賃貸業界には、入居者の移動が活発になる繁忙期と、動きが鈍る閑散期があります。アパートの完成時期を、このサイクルに合わせて最適化することが、早期満室を実現するための重要な戦略です。
【賃貸市場の年間サイクル】
| 時期 | シーズン | 特徴・戦略 |
| 1月~3月 | 繁忙期(ピーク) | 学生・新社会人の動きが最も活発。この時期の完成が理想。 |
|---|---|---|
| 6月~8月 | 閑散期 | 動きが鈍化。募集に苦戦しやすく、AD/FRなどの対策が必要。 |
| 9月~10月 | 第2繁忙期 | 秋の転勤シーズン。ピークほどではないが動きがある。 |
| 11月~12月 | 準備期間 | 繁忙期に向けた募集準備を開始する時期。 |
賃貸経営の成功は、パートナーとなる管理会社の手腕に大きく依存します。管理会社を選定する際には、その「客付け力」を客観的な指標(KPI)で見極めることが重要です。例えば、広告掲載後の問い合わせ数(反響)から、実際に内見につながった割合(内見率)、そして内見から入居申込に至った割合(申込率)といった転換率のデータを開示してもらいましょう。手数料の安さだけで選ばず、結果を出せる会社を慎重に選ぶべきです。
アパート経営は、家賃収入を得るだけでなく、将来的に物件を売却することまで見据えた長期的な視点が不可欠です。しかし、購入時や運営時のことばかりに目が行き、出口戦略や、それに伴う税金、長期的な維持管理について見落としてしまうケースが少なくありません。
物件の売却価格は、最終的に買い主が利用する金融機関の評価額に大きく影響されます。金融機関の評価方法は主に、土地と建物の価値を個別に算出して合計する「積算評価」と、物件の収益性から価値を算出する「収益評価」の2つがあります。自分の物件がどちらの方法で評価されやすいかを把握しておくことは、出口戦略を立てる上で非常に重要です。
アパートを所有する形態として、個人名義で所有するか、資産管理法人を設立して所有するかという選択があります。どちらを選ぶかによって、適用される税率や経費として認められる範囲などが異なり、最終的な手残りのキャッシュフローに大きな差が生まれます。一般的に、課税所得が一定額を超える場合は、法人化した方が税制上有利になることが多いですが、法人設立・維持コストもかかります。自身の状況に合わせて専門家と相談し、最適な形を選択すべきです。
新築時は綺麗でも、建物は時間とともに劣化していきます。外壁塗装や屋上防水など、10年、15年といった周期で大規模な修繕が必要になります。この将来発生する修繕費用に備えるため、新築時から「長期修繕計画」を策定し、計画的に修繕費を積み立てていくことが不可欠です。この計画や積立額の設定にミスがあると、いざという時に資金が不足し、物件の資産価値を大きく落とすことになりかねません。
ここでは、土地から新築アパートを建てる際によく陥りがちな失敗事例と、それを未然に防ぐための具体的な回避策をご紹介します。
価格が安いため旗竿地を購入したが、通路部分(竿部分)が想定以上に広く、有効に使える敷地面積が小さくなってしまった。結果、計画していた戸数を建てられず、収支計画が成り立たなくなった。
【回避策】
土地の購入前に、必ず専門家に依頼して、通路部分や私道負担部分を除いた「有効敷地面積」を算出し、その上で建築可能な建物のボリュームを正確に把握することが不可欠です。
見た目では分からなかった地盤の弱さにより、数百万円の想定外の地盤改良工事費が発生。予備費で吸収できず、事業計画全体の採算性が大きく悪化してしまった。
【回避策】
土地の売買契約を結ぶ前に、地盤調査を実施させてもらうのが最も確実です。それが難しい場合でも、近隣の工事データを取り寄せたり、ハザードマップで液状化リスクを確認したりするなど、可能な限りの事前調査を行いましょう。
「新築だからこれくらいの賃料は取れるはずだ」という希望的観測で賃料を設定した結果、全く入居者が決まらない。完成後も空室が埋まらないまま数ヶ月が経過し、慌てて賃料を大幅に下げざるを得なくなった。
【回避策】
複数の地元の賃貸仲介会社にヒアリングを行い、現実的な募集賃料の相場を徹底的に調査します。自身の計画(間取り、設備など)を伝え、プロの視点から「いくらなら決まるか」という客観的な意見を求めることが重要です。
ケースバイケースですが、一般的な目安として、市街化区域内の農地転用(届出)であれば1~2ヶ月程度、市街化調整区域の農地転用(許可)や開発許可が絡む場合は、半年から1年以上かかることも珍しくありません。計画段階で十分な期間を見込んでおくことが重要です。
工事請負契約の内容によります。契約書に「物価変動等による請負代金の変更(スライド条項)」といった条項が含まれている場合、施工会社からの増額請求に応じる義務が生じる可能性があります。一度契約を締結すると、一方的な見直しは困難なため、契約前の交渉が鍵となります。
火災保険への加入は必須です。これに加えて、地震保険への加入も強く推奨されます。補償額は火災保険の保険金額の30%~50%の範囲で設定するのが一般的です。また、ハザードマップなどを確認し、水災リスクが高いエリアであれば、火災保険の水災補償を手厚くする必要があります。補償内容と保険料のバランスを考え、専門家と相談しながら最適なプランを設計しましょう。