超高利回りアパート投資の秘密
\\\知りたい方はこちら///

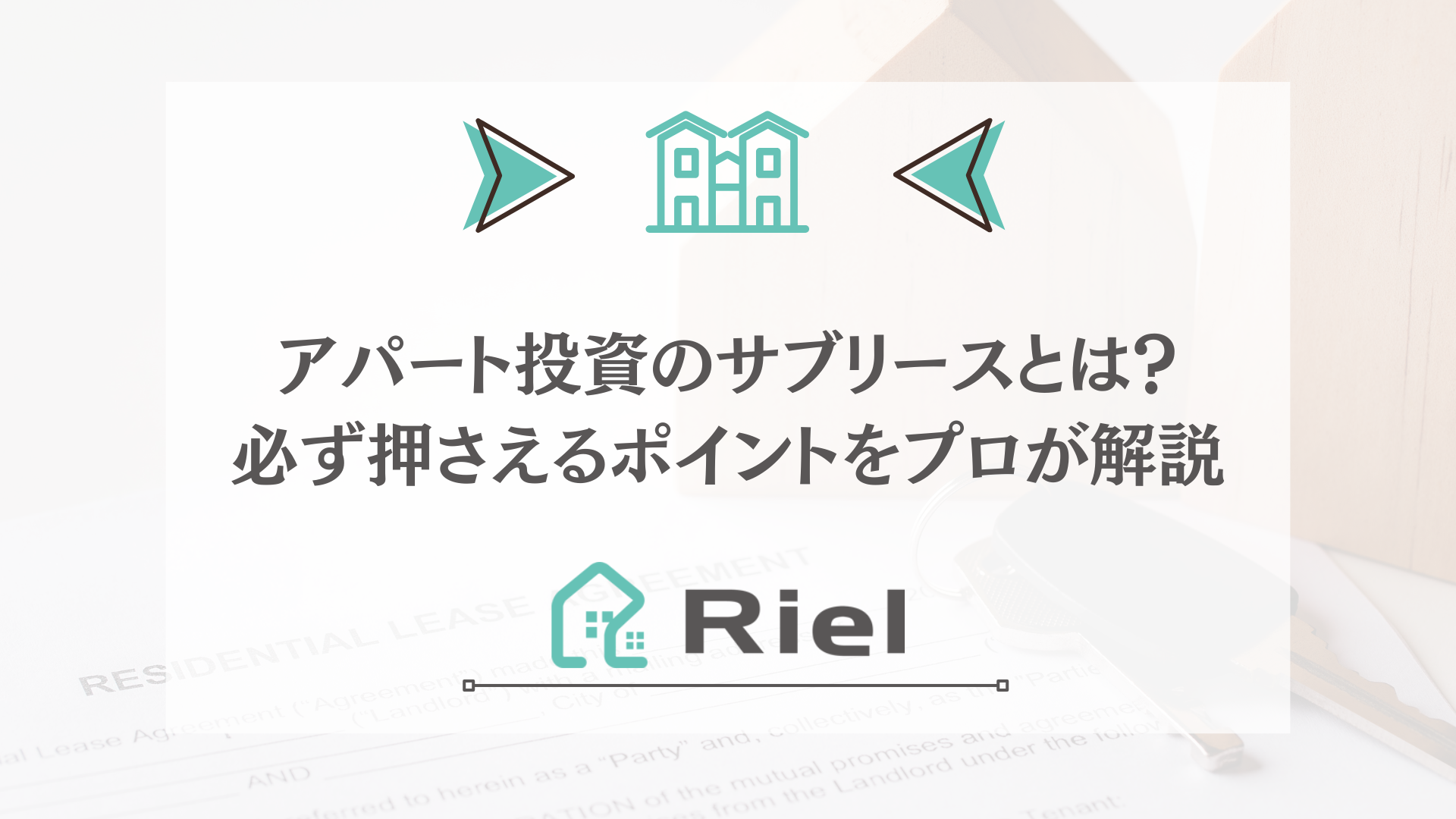
監修者

株式会社Riel 代表取締役
坂口 卓己(サカグチ タクミ)
宅地建物取引士として年間57棟の販売実績を誇り、東京都渋谷を拠点に新築アパートの企画開発から資金計画、満室運営、出口戦略まで一貫支援。豊富な現場経験と最新市況データを融合し、信頼とスピードを重視したサービスで投資家一人ひとりに最適な資産形成プランを提案する不動産投資のプロフェッショナル。
⇒詳細はこちら
新築アパート経営を始める際、「サブリース(家賃保証)」は非常に魅力的な選択肢に映ります。空室や滞納のリスクなく、安定した収入が得られるというイメージが強いでしょう。しかし、その仕組みや契約内容を正しく理解しないまま安易に選択すると、将来思わぬトラブルに繋がることも。本記事では、新築オーナー様が必ず押さえるべきサブリースの全貌を、Q&A形式で徹底的に解説します。
サブリースとは、不動産会社がオーナー様のアパート全室をまとめて借り上げ(一括借上げ)、それを入居者に転貸する仕組みです。オーナー様は入居者の有無にかかわらず、不動産会社から毎月一定の賃料を受け取れます。この仕組みにより、空室や家賃滞納のリスクを不動産会社に移転できるのが最大の特徴と言えるでしょう。
サブリースとマスターリースは、一つの取引における契約関係の違いを指す言葉です。まず、オーナー様と不動産会社が結ぶ「一括借上げ」の契約をマスターリース契約と呼びます。そして、その不動産会社が実際に入居者と結ぶ「転貸」の契約がサブリース契約です。オーナー様が直接関わるのはマスターリース契約であり、この契約内容が収益を左右するため、正確な理解が不可欠となります。
「家賃保証」という言葉は、オーナー様への賃料支払いを保証するものであり、アパートの空室がゼロになるわけではありません。実際の空室リスクは、マスターリース契約を締結した不動産会社が負います。しかし、この保証は絶対ではありません。多くの契約には、経済状況の変動や近隣相場の下落を理由に、保証賃料を見直すことができる「賃料改定条項」が含まれています。保証は永続的なものではないと認識することが重要です。
サブリースは、手間をかけずに安定した経営を目指せる一方、収益性の面で制約が生じる諸刃の剣です。特に新築アパートでは、そのメリットとデメリットが顕著に現れます。ご自身の投資スタイルや目的と照らし合わせ、この制度が本当に最適なのかを慎重に判断することが、後悔しないための第一歩となります。
| 項目 | メリット(オーナーにとっての長所) | デメリット(オーナーにとっての短所) |
| 収益安定性 | 空室・滞納に関わらず収入が安定 | 満室時より収益が下がる(手数料) |
|---|---|---|
| 管理の手間 | 募集やクレーム対応の手間がゼロ | 経営の自由度が低い(家賃設定など) |
| 将来のリスク | 資金計画が立てやすい | 家賃減額や中途解約のリスクがある |
サブリース契約で最も重要なのが「賃料改定条項」です。「30年一括借上げ」と謳っていても、賃料が30年間固定されるわけではありません。法律上も、不動産会社は賃料の減額を請求する権利を持っています。この条項を正しく理解し、将来の収支を予測することが、サブリースで失敗しないための鍵です。
 Rielからのアドバイス
Rielからのアドバイス「賃料改定」はサブリースで最も重要なポイントです。私たちはオーナー様に、不動産会社から提示されたシミュレーションだけでなく、「2年ごとに必ず2%ずつ賃料が下がる」という最悪のケースを想定した独自のシミュレーション作成を推奨しています。その上でなおキャッシュフローが健全に回るかどうかが、契約すべきかの判断基準になります。
契約書でまず確認すべきは、賃料改定の頻度です。一般的には「2年ごと」に見直しを行う契約が多くなっています。また、改定の際に「下限を設けない」という契約も少なくありません。契約時には、改定の具体的な条件や、過去の実績としてどの程度賃料が変動したかなどを、担当者へ具体的に確認することが重要です。安易に「大丈夫だろう」と考えるのは非常に危険です。
将来の収支シミュレーションを作成する際は、必ず賃料の下落を織り込むべきです。楽観的な計画は経営破綻に直結します。具体的な下落率としては、2年ごとに2〜3%、10年で10%〜15%程度の下落を想定しておくと、より現実的な計画になります。新築時の賃料が最も高く、その後は緩やかに下落していくという不動産の原則を、シミュレーションに反映させることが不可欠です。
サブリースの手数料は「保証率」や「借上げ料率」という言葉で表現されます。例えば「保証率90%」なら、手数料は10%です。この料率は一般的に10%〜20%が相場ですが、数字の表面だけを見て判断すると、隠れたコストを見逃す可能性があります。保証される範囲や別途費用について、細部まで確認が必要です。
「保証率95%」のような好条件に見える場合、その保証対象が「家賃のみ」で、共益費や駐車場代、町内会費などが含まれていないケースがあります。仮に家賃6万円、共益費5千円の部屋で家賃のみが保証対象だと、実質的な保証率は88%程度まで下がってしまいます。保証される収入の範囲がどこまでなのか、契約書で明確に確認することが重要です。
サブリース契約の月額手数料とは別に、日常清掃費や消防設備点検費、入居者更新時の事務手数料などが「別途費用」としてオーナー様負担になっている場合があります。これらの費用は年間で見ると数十万円になることもあり、収益性を大きく圧迫します。月々の手数料以外に、どのような費用が自己負担となるのかをリストアップして確認しましょう。
サブリース契約では、転貸する際の募集賃料(入居者が支払う家賃)の決定権は、基本的に不動産会社側にあります。オーナー様が「もっと高い家賃で募集してほしい」と思っても、自由に決めることはできません。この賃料設定の考え方を理解しておくことは、後の賃料改定交渉においても重要なポイントとなります。
不動産会社がオーナー様へ保証賃料の減額を求める際は、その根拠を示す必要があります。具体的には、近隣の類似物件の募集賃料一覧(レントロール)や、成約事例などの客観的なデータ(エビデンス)です。オーナー様としても、これらの資料の妥当性を判断できるよう、日頃から自身の物件周辺の家賃相場を把握しておくことが、交渉の場で不利にならないために重要です。
賃料にはいくつかの種類があり、区別が必要です。「原契約賃料」はオーナー様と不動産会社が最初に決めた保証賃料。「再契約賃料」は改定交渉後に合意した新しい保証賃料です。一方、「実勢賃料」は不動産会社が実際に入居者から得ている賃料のことで、これは公表されない場合がほとんどです。この実勢賃料と保証賃料の差額が、不動産会社の利益となります。
建物の維持管理に関わる費用負担の線引きは、サブリース契約で最もトラブルになりやすい点の一つです。契約書に負担区分がどう明記されているか、一言一句確認することが重要です。「管理は全てお任せ」という言葉を鵜呑みにすると、後で高額な請求書が届くことになりかねません。
| 発生原因 | 負担者 | 具体例 |
| 入居者の故意・過失 | サブリース会社 | 壁に穴を開けた、設備を壊した |
|---|---|---|
| 経年劣化・通常損耗 | オーナー | 日焼けによる壁紙の黄ばみ、畳の擦れ |
| 主要設備の故障 | オーナー | 給湯器、エアコンの寿命による故障 |
| 大規模修繕 | オーナー | 外壁塗装、屋上防水 |



「原状回復」の費用負担は要注意です。特に「通常損耗」の範囲は曖昧になりがちです。私たちは、契約書に国交省のガイドラインに準拠する旨を一文入れてもらうよう交渉することをお勧めしています。これにより、万が一トラブルになった際も、客観的な基準に基づいて話し合いを進めることができ、オーナー様が不当な費用を負担させられるリスクを軽減できます。
一度結んだサブリース契約を、途中でやめたくなるケースも想定しておくべきです。しかし、サブリース契約は借地借家法に基づいているため、貸主であるオーナー様からの解約には高いハードルが設定されています。契約書に記載された解約条件を、契約前に必ず理解しておきましょう。
オーナー様からの中途解約には、通常3ヶ月〜6ヶ月前の解約通知に加え、高額な違約金(保証賃料の数ヶ月分〜1年分など)が定められていることがほとんどです。逆に、不動産会社側からの解約は、比較的短い通知期間で、違約金なしに可能な場合も。この契約の非対称性は、消費者庁も注意喚起しています。
万が一解約した場合、その後の運営方法を考えておく必要があります。
▼サブリース解約後の管理移行 3ステップ
新築アパートを建てる際の融資審査において、サブリース契約はプラスにもマイナスにも影響します。金融機関がこの仕組みをどう評価するのか、また、将来の売却(出口戦略)にどう関わるのかを知っておくことは、事業計画の精度を高める上で欠かせません。
金融機関は、サブリースによる収入の安定性を評価する一方で、その保証賃料が将来下落するリスクも当然考慮します。そのため、審査の際には保証賃料の満額ではなく、80%〜90%程度に掛け目をして収益性を評価することが一般的です。サブリースだからといって、必ずしも融資が有利になるわけではないことを理解しておく必要があります。
サブリース契約が付いたまま物件を売却する場合、安定したインカムを求める買主にとっては魅力的に映る可能性があります。しかし、より高い収益性を求める買主からは、手数料分だけ利回りが低い物件と見なされ、敬遠されることも。また、サブリース契約の引継ぎを嫌がる買主もいるため、一般的には市場価格より安くなる傾向があります。
サブリース契約は、税務上の取り扱いも通常の賃貸経営とは異なる点があります。特に消費税の扱いは、オーナー様が課税事業者である場合に注意が必要です。税金の知識不足は、手取りキャッシュフローの計算を大きく狂わせる原因となります。
入居者が支払う居住用の家賃は非課税ですが、オーナー様が不動産会社から受け取る保証賃料は「事業」への対価と見なされ、消費税の課税対象となります。オーナー様が課税事業者の場合、受け取った保証賃料に含まれる消費税分を国に納める義務が生じます。この点を考慮せずに利回り計算をすると、後で納税資金に困ることになりかねません。
修繕費は、その内容によって一括で経費計上できる「修繕費」と、資産として減価償却していく「資本的支出」に分かれます。この判定は税務上の専門知識を要するため、自己判断は危険です。サブリース契約でオーナー様負担とされた修繕がどちらに該当するのか、必ず税理士などの専門家に確認し、適切な会計処理を行うことが節税の第一歩です。
「新築だからすぐ満室になる」と考えがちですが、ここにサブリースの落とし穴が潜んでいる場合があります。特に、建物完成直後の入居者募集期間の取り扱いは、契約書でしっかり確認しないと、当初の想定とキャッシュフローが大きくズレる原因となります。
契約によっては、竣工後1ヶ月〜3ヶ月程度の期間を「免責期間」とし、その間は家賃保証が適用されない場合があります。つまり、入居者が決まらなければ、その間のオーナー様の収入はゼロです。また、入居付けを促進するための広告料(AD)やフリーレントの費用が、別途オーナー様負担になっていないかも確認が必要です。
そもそもサブリース会社は、入居付けが難しいと判断した物件とは契約を結びません。逆に言えば、サブリースに頼らなくても満室経営が可能な、競争力の高い物件を企画・建築することが最も重要です。賃貸需要の強い立地を選び、ターゲット層に響く間取りと設備を導入することで、竣工後スムーズに満室稼働を実現し、有利な条件で交渉を進めることができます。
サブリースに関するトラブルは、その多くが契約内容に対する「誤解」や「思い込み」から生じています。ここでは、実際にあったトラブル事例を元に、事前に知っておくべきポイントと、それを回避するための具体的な対策を解説します。
「当初10年間は賃料を固定」といった契約でも、契約書の隅に「ただし、経済情勢の著しい変動があった場合は、協議の上で見直しができる」といった条項が記載されていることがあります。これにより、当初の説明とは異なり、賃料が減額されるケースは少なくありません。口頭での説明だけでなく、契約書の文言が全てであると認識することがトラブル回避の基本です。
「共用部の電球交換くらいはやってくれるだろう」といった思い込みは禁物です。契約書に明記されていない業務は、原則として保証されません。費用の負担区分や業務範囲について、少しでも疑問があれば、契約前に必ず書面で確認を取りましょう。「言った・言わない」の争いを避けるため、合意事項はすべて議事録や覚書として形に残すことが、自身を守ることに繋がります。
サブリース契約書は専門用語が多く、読むのが大変ですが、ここで手を抜いてはいけません。特に、以下に挙げるような、オーナー様にとって一方的に不利な条項が含まれていないか、契約締結前に必ずチェックしてください。一つでもあれば、契約を見直すか、他の会社を検討すべき危険信号です。
▼危険信号!契約前に必ず確認したい条文リスト



契約書にサインする前の最終チェックとして、「もしこの条文について質問したら、担当者は明確に説明できるか?」と自問してみてください。もし担当者が言葉を濁したり、曖昧な説明に終始したりする場合は、その会社が契約内容を誠実に履行しない可能性があります。担当者の対応そのものが、会社の信頼性を測るリトマス試験紙です。
サブリースは、数あるアパートの管理形態の一つに過ぎません。手間やリスク、収益性のバランスを考え、自身ですべて行う「自主管理」や、不動産会社に一部業務を委託する「一般管理」と比較し、ご自身の状況に最も適した方法を選ぶことが大切です。
| 比較項目 | サブリース | 一般管理 | 自主管理 |
| 収益性 | 低 | 中〜高 | 高 |
|---|---|---|---|
| 安定性 | 高 | 中 | 低 |
| 管理の手間 | 極小 | 小 | 大 |
| 経営の自由度 | 低 | 中 | 高 |
| 空室リスク | 無 | 有 | 有 |
私たちRielは、サブリースを「思考停止で頼る」ものではなく、「戦略的に使いこなす」ための選択肢の一つだと考えています。そのためには、何よりもまず、サブリースに依存しなくても十分に通用する、競争力の高いアパートを企画・建築することが大前提となります。
私たちは、徹底した市場調査に基づき、長期的に賃貸需要が見込める立地を厳選します。その上で、入居者から選ばれ続けるデザイン性の高い間取りや、最新の設備を導入することで、物件そのものの収益力を最大化します。このような物件であれば、サブリースを利用する際も、有利な条件で交渉を進めることが可能になります。
オーナー様が不利な契約を結ぶことがないよう、私たちは契約前にチェックすべきポイントをまとめた「条件交渉テンプレート」をご提供しています。また、サブリースを利用した場合と、一般管理で運営した場合の、賃料下落や空室リスクを織り込んだ10年単位の詳細な収支シミュレーションを複数パターンご提示し、お客様が納得のいく意思決定をできるようサポートします。
最終的にサブリースを選ぶべきかどうかは、オーナー様の状況や投資目的によって異なります。以下に、それぞれのタイプをまとめました。ご自身がどちらに近いか、客観的に判断してみてください。
サブリースが向いている人
サブリースが向いていない人
最後に、サブリースに関して特によく寄せられる細かい質問について、Q&A形式で簡潔にお答えします。
はい、どちらも可能です。自主管理や一般管理で運営していた物件を、後からサブリース契約に切り替えることはできます。逆に、サブリースを解約(契約条件による)し、一般管理や自主管理に移行することも可能です。ただし、いずれの場合も不動産会社の審査や条件交渉が必要となります。
長期空室が続いた場合、契約更新時に大幅な賃料減額を要求されるか、最悪の場合、契約解除に至る可能性があります。また、地震や火災などで建物が大きな被害を受け、賃貸が不可能な状態になった場合は、多くの契約で家賃保証が免責(停止)される条項が含まれています。保険への加入は必須です。
入居者の連帯保証は、不動産会社が責任を負います。入居者から預かった敷金は、一旦不動産会社が管理し、退去時の原状回復費用に充当されます。また、入居者が支払う契約更新料は、基本的には不動産会社の収益となり、オーナー様には分配されないことがほとんどです。契約書でこれらの金銭の帰属を必ず確認しましょう。