超高利回りアパート投資の秘密
\\\知りたい方はこちら///


監修者

株式会社Riel 代表取締役
坂口 卓己(サカグチ タクミ)
宅地建物取引士として年間57棟の販売実績を誇り、東京都渋谷を拠点に新築アパートの企画開発から資金計画、満室運営、出口戦略まで一貫支援。豊富な現場経験と最新市況データを融合し、信頼とスピードを重視したサービスで投資家一人ひとりに最適な資産形成プランを提案する不動産投資のプロフェッショナル。
⇒詳細はこちら
アパート投資を始める際、多くの人が最初に悩むのが「法人名義でやるべきか、個人名義のままがいいのか」という問題です。税金の仕組みや融資の受けやすさが大きく変わるため、この選択は将来のキャッシュフローに直結します。本記事では、あなたの所得や物件規模、そして将来の目標に合わせて、どちらが最適なのかを判断できるよう、税制・融-資・運営の観点から両者を徹底比較し、分かりやすく解説していきます。
アパート投資において、法人と個人のどちらが有利かは一概には言えません。なぜなら、投資家自身の状況によって最適解が大きく異なるからです。重要なのは、「所得」「保有年数」「物件規模」という3つの軸で、ご自身の状況を客観的に分析すること。これらの要素を組み合わせることで、あなたにとって有利な形態が見えてきます。まずはこの判断基準をしっかりと理解しましょう。
最適解は、これら3つの要素の組み合わせで決まります。所得が高くなるほど個人の累進課税が不利に働き、法人の一律な税率が有利になる傾向があります。また、長期保有を前提とするなら、減価償却の調整がしやすい法人の方がキャッシュフローを設計しやすくなります。さらに、物件規模が大きくなれば、個人の信用力だけでは融資が難しくなり、事業として評価される法人名義の方が有利に進められるケースが増えるでしょう。ご自身の投資プランを具体的に描き、3つの軸でシミュレーションすることが重要です。
自身の立場によって、法人化を検討する目的やメリットは異なります。例えば、高所得のサラリーマン大家であれば、給与所得と不動産所得の損益通算による所得税の圧縮や、将来の法人税率の低さを目指すことが主な目的になります。一方で、専業大家は事業拡大のための融資獲得や信用力向上、共同経営の場合は出資比率の明確化や円滑な事業承継が法人化の大きな動機となるでしょう。自身のゴールから逆算し、法人と個人のどちらが手段として適しているかを考えることが大切です。
法人と個人には、大きく分けて「税金の仕組み」「融資の受けやすさ」「運営の自由度」という3つの違いがあります。まずは以下の比較表で全体像を掴んでください。
| 比較項目 | 個人 | 法人 |
| 税金 | 所得税・住民税(最大55%の累進課税) | 法人税等(実効税率 約25〜34%) |
|---|---|---|
| 赤字繰越 | 3年間 | 10年間 |
| 減価償却 | 強制償却 | 任意償却(限度額内) |
| 経費の範囲 | 必要経費 | 損金(役員報酬・退職金など範囲が広い) |
| 融資評価 | 個人の属性(年収・勤務先)が中心 | 事業の継続性・収益性が中心 |
| 社会的信用 | 個人に依存 | 法人格として高い |
このように、適用される税金が個人の「所得税」から法人の「法人税」に変わるだけでなく、金融機関が評価するポイントも変化します。また、経費の範囲や赤字の繰越期間など、運営面のルールも法人の方が有利な点が多く見られます。これらの違いを正しく理解することが、最適な選択への第一歩となるのです。
最大の違いは、個人に適用される「超過累進課税」と、法人に適用される「比例税率(※一部軽減税率あり)」です。個人の所得税は所得が増えるほど税率が最大45%まで上がりますが、法人税の税率は利益の大小にかかわらずほぼ一定です。また、個人の不動産所得の赤字は給与所得など他の所得と相殺(損益通算)できますが、法人の場合は法人の事業全体の利益と相殺することになります。経費の考え方も、個人事業の必要経費より法人の方が損金として認められる範囲が広いのが特徴です。
金融機関からの評価は、個人では「個人の属性」、法人では「事業の継続性や収益性」がより重視されます。個人で融資を受ける際は、勤務先や年収、自己資金といった個人の返済能力が審査の中心です。一方、法人では事業計画の妥当性や決算内容が厳しく評価される傾向にあります。事業が軌道に乗り、良好な決算を組むことができれば、個人としての与信枠とは別で融資を受けられる可能性が広がり、より大規模な投資へとステップアップしやすくなるでしょう。
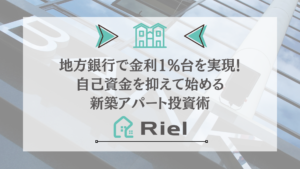
法人は減価償却と赤字繰越の自由度が高く、戦略的なキャッシュフロー管理が可能です。個人では減価償却が強制的に毎年計上されますが、法人は任意で償却額を調整できます(償却限度額の範囲内で)。また、事業で生じた赤字(欠損金)を翌年以降の黒字と相殺できる期間も、個人は3年間なのに対し、法人は10年間と長くなっています。大規模修繕などで大きな赤字が出た場合でも、法人であれば長期間にわたって税負担を平準化させることが可能です。
運営面では、法人は決算期を自由に設定でき、経費として認められる範囲も広がります。個人の事業年度は1月〜12月に固定ですが、法人は繁忙期を避けるなど任意に決算月を選択可能です。また、役員である自身や家族への給与、生命保険料の一部、退職金なども経費にできる点は大きなメリットでしょう。ただし、法人化すると役員報酬の額にかかわらず健康保険・厚生年金への加入が義務付けられ、社会保険料の負担が発生する点は注意が必要です。
税金面での有利不利を判断する上で最も重要なのが、個人の所得税・住民税と、法人の法人税等の実効税率の比較です。課税所得が一定のラインを超えると、所得に応じて税率が上がる個人の税負担が、ほぼ一定の税率である法人の税負担を上回ります。この分岐点が、法人化を検討する一つの目安となるでしょう。ご自身の所得が将来的にどの水準に達するかを見据えることが重要です。
一般的に、課税所得が900万円を超えると、個人の税率が法人の実効税率を上回り始め、法人化を検討する価値が出てきます。これは、所得税率が33%(課税所得900万円超)となり、住民税率約10%と合わせると税負担が43%を超えるためです。この水準は法人の実効税率(約25%〜34%)を大きく上回ります。ご自身の給与所得と不動産所得などを合算した「課税所得」がこのラインに達するかどうかが、最初の判断基準となるでしょう。
資本金1億円以下の中小法人の場合、実効税率は約25%〜34%が目安となります。実効税率とは、法人税だけでなく、地方法人税、法人住民税、事業税などを合計した実質的な税負担のことです。注意点として、所得800万円以下の部分には軽減税率が適用されること、そして赤字であっても発生する「法人住民税の均等割」(最低でも年7万円程度)が存在することを覚えておきましょう。単純な税率比較だけでなく、こうした固定コストも考慮する必要があります。

不動産投資では、初年度の経費増や大規模修繕などで赤字が発生することもあります。この赤字をいかに有効活用できるかが、法人と個人で異なります。特に、赤字を翌年以降の黒字と相殺する「繰越控除」の仕組みは、長期的なキャッシュフローに大きな影響を与えるため、その違いを正しく理解し、戦略的に活用することが求められます。
個人の場合、不動産所得の赤字は、給与所得や事業所得など他の黒字の所得と相殺(損益通算)できます。これにより、確定申告で所得税や住民税の還付を受けられる可能性があります。これは特に、投資初期のサラリーマン大家にとって大きなメリットです。ただし、損益通算してもなお残った赤字を繰り越せる期間は3年間と定められています。この期間内に黒字化できないと、赤字を活かしきれないまま消滅してしまう点に注意が必要です。
法人の場合、赤字(欠損金)は最大10年間繰り越すことが可能です。これにより、大規模修繕などで一時的に大きな赤字が出ても、翌年以降の黒字と長期間にわたって相殺し、法人税を圧縮できます。さらに、複数の法人を所有している場合、グループ法人税制を活用して、一方の法人の赤字と他方の法人の黒字をグループ全体で通算することも可能です(一定の要件あり)。これは個人にはない、法人ならではの戦略的な節税手法といえるでしょう。
減価償却は、建物の取得費用を法定耐用年数にわたって分割して経費計上する会計処理です。実際にお金は出ていきませんが、帳簿上の利益を圧縮し、税金を抑える効果があります。この減価償却の扱いが個人と法人で異なるため、キャッシュフローの最適化戦略にも違いが生まれます。特に法人の持つ柔軟性は、経営の自由度を高める上で大きな武器となります。
個人事業主の場合、減価償却は「強制償却」であり、毎年必ず定められた計算方法で経費計上しなければなりません。利益が少ない年でも容赦なく償却が進むため、利益の調整弁として使うことは不可能です。一方で、減価償却によって税負担が減り、手元に現金が残りやすくなる効果(キャッシュフローの創出)は確実に得られます。税負担を抑えつつ、創出された現金を繰り上げ返済や次の投資にどう回していくか、計画的な資金運用が求められます。
法人では、減価償却は「任意償却」です。これは、法律で定められた償却限度額の範囲内であれば、その期に計上する減価償却費の金額を0円から限度額まで自由に調整できることを意味します。例えば、利益が多く出た期は限度額まで償却して節税し、融資を受けたい期はあえて償却費を計上せず利益を大きく見せ、決算書の評価を高める、といった戦略的な対応が可能です。この柔軟性が、利益調整と融資対策を両立させる鍵となります。
アパート投資の成功は、いかに有利な条件で融資を受けられるかに大きく左右されます。融資を受ける際の名義が個人か法人かによって、金融機関の審査の視点や評価方法が異なります。個人の属性が重視されるのか、法人の事業性が評価されるのか。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合わせた資金調達戦略を立てることが、事業拡大のスピードを決定づけるでしょう。
法人名義で融資を受ける場合、金融機関は代表者個人の属性に加えて、「事業としての収益性・継続性」を重視します。そのため、説得力のある事業計画書や、複数年の事業運営で作成された信頼性の高い決算書が極めて重要になります。コツとしては、税理士などの専門家と連携して質の高い決算書を作成し、自己資本比率を高めるなど財務内容を健全に保つことです。これにより、個人としての与信とは別の「法人格」としての信用が構築され、より大きな規模の資金調達が可能になります。
特に投資の初期段階や、小規模な物件から始める場合、個人名義の方が融資手続きがシンプルでスピーディーに進むことがあります。特に、上場企業勤務や公務員など、個人の属性が高い場合は、その信用力を最大限に活かせます。しかし、落とし穴もあります。それは、物件規模が大きくなるにつれて、個人の与信枠だけでは限界が来ることです。また、不動産投資ローンが個人の他のローン(住宅ローンなど)の審査に影響を与える可能性も考慮しておく必要があります。
アパート投資は長期にわたる事業です。そのため、将来の相続や事業承継まで見据えた出口戦略を初期段階から設計しておくことが賢明です。この点において、法人は個人に比べて多くのメリットを持ちます。資産を「不動産」そのものではなく「自社株式」という形で所有することにより、分割や承継がスムーズに行えるようになるからです。
法人化した場合、アパートなどの不動産は法人が所有し、オーナーはその法人の「株式」を所有する形になります。相続や贈与の対象が、分割しにくい不動産そのものではなく、1株単位で分割可能な株式となるため、複数の相続人に公平に資産を分配しやすくなります。また、暦年贈与の非課税枠(年間110万円)を活用して、毎年少しずつ株式を子や孫へ計画的に移転させていく「生前贈与」もスムーズに行えるため、将来の相続税対策として非常に有効です。
個人名義のアパートは、所有者が亡くなると遺産分割協議が完了するまで相続人全員の共有財産となり、家賃収入の管理や大規模修繕などの経営判断が滞るリスクがあります。一方、法人所有であれば、オーナー(株主)が亡くなっても会社の経営は継続されます。株式の承継者が決まるまでの間も、代表取締役などの役員が業務を執行できるため、入居者対応や家賃管理といった事業運営を止めることなく、安定した経営を続けられるのです。
「いつ法人化するのが最も得策か?」これは非常に重要な問いです。早すぎれば設立・維持コストが負担となり、遅すぎれば本来得られたはずの節税メリットを逃してしまいます。法人化のベストタイミングは、個々の状況によって異なりますが、いくつかの判断基準を知っておくことで、適切な時期を見極めることが可能になります。
一般的に、法人化を検討すべきタイミングの目安として、まず「課税所得900万円超」が挙げられます。これは個人の所得税・住民税率が法人の実効税率を上回る分岐点です。次に「不動産収入(家賃収入)1,000万円超」も一つの基準。この規模になると消費税の課税事業者になる可能性があり、法人化による節税スキームを検討する価値が出てきます。また、物件規模としては「2棟目、3棟目の購入を検討するタイミング」で、融資戦略として法人化を考えるケースが多く見られます。
最初から大規模な投資を計画している場合や、将来的に事業拡大を明確に見据えている場合は、1棟目の購入時から法人で始めるという選択肢も有効です。これにより、初めから法人としての実績を積み上げることができ、次の融資にも繋がりやすくなります。ただし、注意点として、設立・維持コストが初年度から発生すること、そして個人に比べて融資審査のハードルが高くなる可能性があることを理解しておく必要があります。十分な自己資金と綿密な事業計画が不可欠です。
ここまで様々な比較をしてきましたが、ご自身の状況に当てはめて具体的にイメージすることが大切です。ここでは、代表的な3つのケースを取り上げ、法人と個人のどちらが向いているかのチェックリストを早見表形式でまとめました。ご自身の状況と照らし合わせながら、最適な選択肢を考えてみましょう。
このケースでは、まず給与所得と不動産所得を合算した「課税所得」が900万円を超えるかどうかが大きな分岐点です。超える場合は、個人の高い税率を避けるために法人化が有利に働く可能性が高いでしょう。また、将来的に物件を買い増していく意欲があるか、家族に給与を支払って所得を分散させたいか、といった点も考慮材料になります。まずは個人で始め、所得が増えたタイミングで法人成りする「2段階戦略」も有効な選択肢です。
すでに専業で、複数棟のアパートを保有・運営している、またはこれから目指す場合は、法人化のメリットを最大限に享受できる可能性が高いです。法人格としての信用力を高めることで、金融機関からの追加融資が受けやすくなり、事業拡大のスピードを加速させられます。また、役員報酬の活用による所得コントロール、退職金の準備、10年間の欠損金繰越など、個人事業にはない多様な節税・経営戦略を駆使できるため、法人設立を積極的に検討すべきでしょう。
新築アパート投資の初期や、中古物件で大規模修繕を計画している場合など、意図的に赤字を出すケースでは、その活用法がポイントです。サラリーマン大家であれば、個人のまま給与所得と損益通算して所得税の還付を受けるのが得策です。一方で、他に事業所得がある場合や、家族に役員として業務を手伝ってもらい所得を分散させたい場合は、法人化が有効です。法人であれば、役員報酬という形で計画的に所得を分散し、世帯全体での手取り額を最大化することが可能になります。
法人化には多くのメリットがある一方で、無視できないデメリットも存在します。節税や信用力向上といった華やかな側面に目を奪われがちですが、設立・維持にかかるコストや事務的な負担増といった現実的な側面も直視しなければなりません。ここでは、実務レベルで法人化のメリットとデメリットを具体的に検証し、総合的な判断ができるように整理します。
法人化を決断した場合、具体的にどのような手続きを踏めばよいのでしょうか。以下のロードマップに沿って流れを理解し、必要であれば司法書士や税理士といった専門家のサポートを得ることで、スムーズに進めることが可能です。
▼法人設立までの最短ロードマップ
法人化を検討する上で、具体的なコストの把握は欠かせません。事前にコストを正確に見積もることで、「思ったより手残りが少なかった」という事態を防ぐことができます。
▼設立費用(初期費用)
▼ランニング費用(年次コスト)
アパート投資は、家賃収入を得るインカムゲインだけでなく、物件を売却した際のキャピタルゲイン(譲渡益)も重要な収益の柱です。そして、この売却時の税金の計算方法も、個人と法人では大きく異なります。
個人が不動産を売却した場合、保有期間によって税率が大きく異なります。一方、法人の場合は保有期間に関わらず、他の利益と合算して法人税が課されます。以下の表で違いを確認してください。
| 保有期間 | 個人の売却益にかかる税率 | 法人の売却益にかかる税率 |
| 5年以下(短期譲渡) | 約39% | 他の所得と合算して法人税率(約25〜34%) |
|---|---|---|
| 5年超(長期譲渡) | 約20% | 他の所得と合算して法人税率(約25〜34%) |
したがって、短期で売却を繰り返すような投資スタイルであれば法人が、長期でじっくり保有してから売却する場合は個人の方が税務上有利になる可能性があります。
売却時の税務上の論点は、保有期間による税率の違いだけではありません。例えば、法人の場合、不動産の売却損を他の事業の黒字と相殺できるため、損失が出た場合のリスクヘッジがしやすいというメリットがあります。また、個人から法人へ不動産を移転(売却)する際には、不動産取得税や登録免許税といった流通税が再度かかることや、適正な価格で取引しないと税務上の問題が生じる可能性があることなど、法人化に伴う特有の論点も理解しておく必要があります。
法人化を検討する中で、多くの人が抱きがちな誤解や疑問があります。ここでは、特に質問の多い2つのポイントについて、Q&A形式で分かりやすく解説し、よくある誤解を解消していきます。
これは必ずしも本当ではありません。家族を役員にして給与(役員報酬)を支払うことで、所得を分散し世帯全体での税負担を軽減できるのは事実です。しかし、そのためには、その家族が実際に役員としての業務を行っている「勤務実態」が必要です。また、業務内容に見合わない不相当に高額な給与は、税務署から経費として認められない(損金不算入)リスクがあります。名義だけの役員に給与を支払うことは脱税と見なされる可能性があるので注意しましょう。
法人のお金(預金)は、あくまで会社という別人格の資産であり、社長個人のお金ではありません。社長が個人的な目的で会社のお金を引き出すと、それは会社から社長への「貸付金」や「役員賞与」と見なされます。貸付金であれば会社は利息を受け取る必要がありますし、役員賞与と認定されれば会社の経費にならず、社長個人の所得税・住民税の対象となり、結果的に二重で課税されることになりかねません。公私混同は厳禁です。
ここまで、アパート投資における法人と個人の違いを多角的に比較してきました。税金、融資、運営、相続など、考慮すべき点は多岐にわたります。最終的にどちらを選ぶべきかは、あなたの現在の状況と将来の目標によって決まります。
30秒でわかる!法人化かんたん診断
あなたの状況に一番近いものはどれですか? YESかNOで答えるだけで、あなたに合った選択肢が見えてきます。
質問① 課税所得は900万円を超えそうですか?
(ご自身の給与所得 + アパートの年間利益)
質問② 2棟、3棟と規模を拡大していきたいですか?
質問③ まずは1棟、小規模から試してみたいですか?
診断の結果、少しでも「法人化」の選択肢が頭に浮かんだ方は、次のアクションへ進みましょう。税理士などの専門家へ相談し、ご自身の具体的な数値に基づいた「法人化シミュレーション」を依頼するのが最適な一手です。
税理士などの専門家に相談に行く前に、以下の情報を準備しておくと、より具体的で的確なアドバイスがもらえます。
▼専門家への相談前に準備するものリスト
これらの資料を基に、あなただけの最適なプランを専門家と一緒に作り上げていきましょう。