超高利回りアパート投資の秘密
\\\知りたい方はこちら///

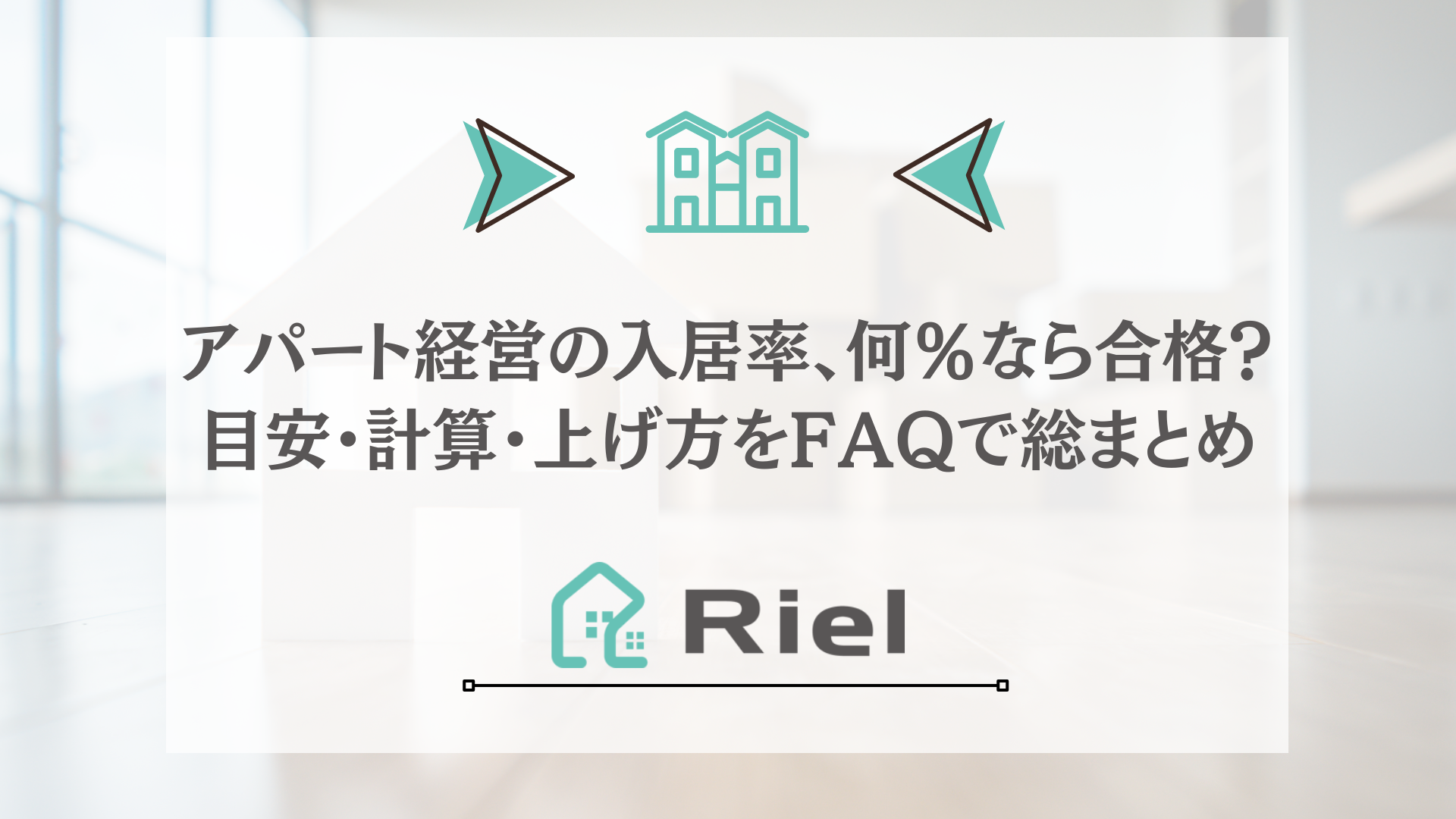
監修者

株式会社Riel 代表取締役
坂口 卓己(サカグチ タクミ)
宅地建物取引士として年間57棟の販売実績を誇り、東京都渋谷を拠点に新築アパートの企画開発から資金計画、満室運営、出口戦略まで一貫支援。豊富な現場経験と最新市況データを融合し、信頼とスピードを重視したサービスで投資家一人ひとりに最適な資産形成プランを提案する不動産投資のプロフェッショナル。
⇒詳細はこちら
アパート経営を始めるにあたり、「利回り」と同じくらい、いえ、それ以上に重要な指標が「入居率」です。入居率は、あなたの経営の健全性を映し出す鏡であり、毎月のキャッシュフローに直結する生命線と言えます。本記事では、アパート経営の成功を左右する「入居率」について、その目安、正しい計算方法、そして空室を最速で埋めるための具体的な改善策まで、私たちRielが実践するノウハウをFAQ形式で徹底的に解説します。
アパート経営の成功は、高い入居率を維持できるかにかかっています。入居率は事業の安定性を測る最も基本的な指標であり、この数字が低ければ、どれだけ高い利回りを計画していても絵に描いた餅でしかありません。まずは、入居率の定義と、私たちが目指すべき「良い入居率」の目安について、基本的な知識を整理します。
「入居率」とは、アパートの総戸数に対して、現在入居されている戸数の割合を示す指標です。一方「空室率」はその逆の数字です。これらと似て非なる「稼働率」は、厳密には「家賃が発生している割合」を指します。例えば、入居が決まっていてもフリーレント期間中なら、入居率は100%でも稼働率(収益)は低い、といったケースです。まずは、最も分かりやすい「入居率」を基本指標として押さえましょう。
はい、承知いたしました。
「入居率」「空室率」「稼働率」の3つの指標について、アパート経営のオーナー様にとってなぜ重要なのか、その違いが経営にどう影響するのかを、テーブル形式で詳しく解説します。
「入居率」「空室率」「稼働率」 詳細解説テーブル
この3つの指標の最大の違いは、「入居率」と「空室率」が【物理的な状態】を示すのに対し、「稼働率」は【経営的・収益的な状態】を示す点にあります。
| 用語 | 読み方 | 指標の意味 | 測るもの | 具体的な計算例(10戸中1戸が「フリーレント1ヶ月」で入居中) | オーナーにとっての重要性 |
| 入居率 (にゅうきょりつ) | 物理的な入居割合 | 「部屋が物理的にどれだけ埋まっているか」 | 物件の人気度・客付け力 | 10戸 ÷ 10戸 = 100% 【解説】 フリーレント中であっても、契約が結ばれ部屋は埋まっているため、物理的な「入居率」は100%(満室)とカウントされます。 | 管理状態の把握に使う。 「満室」と聞くと安心しがちだが、これだけ見ていると「満室なのに手取りが少ない」という事態を見逃す。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空室率 (くうしつりつ) | 物理的な空室割合 | 「部屋が物理的にどれだけ空いているか」 (入居率の裏返し) | 物件の空き状況 | 0戸 ÷ 10戸 = 0% 【解説】 物理的に空いている部屋はゼロのため、空室率は0%となります。 | 経営の危険信号として使う。 この数字が上昇し始めたら、家賃設定や募集戦略に問題がある可能性が高い。 |
| 稼働率 (かどうりつ) | 収益的な稼働割合 | 「家賃収入がどれだけ発生しているか」 | 物件の「本当の収益力」 | 9戸分の家賃 ÷ 10戸分の家賃 = 90% 【解説】 10戸中1戸はフリーレント(家賃0円)のため、その月の収益に貢献しているのは9戸のみ。したがって、収益ベースで見た「稼働率」は90%となります。 | オーナーのキャッシュフローに直結する最重要指標。 「入居率100%(満室)」という言葉に満足せず、フリーレントや家賃滞納を加味した「稼働率」で、実際の収益を正確に把握することが経営の鍵。 |
アパート経営における「良い入居率」の一般的な目安は、年間平均で95%以上です。なぜなら、多くのアパートローン返済計画や収支シミュレーションは、5%程度の空室(1年のうち約18日)をあらかじめ見込んで組まれているからです。もし入居率が90%を下回る状態が続くと、ローンの返済や固定資産税の支払いがキャッシュフローを圧迫し、経営は赤字に陥る危険性が高まります。私たちは、安定経営のラインとして95%、優良経営の証として98%以上を常に目指しています。
入居率の目安は、建物の築年数によって大きく異なります。新築(築1〜2年)であれば、市場で最も競争力が高いため、入居率は98%〜100%を維持するのが当然の目標です。一方、築15年を超えた「築古」物件になると、新築物件との競合により、そのままで高い入居率を維持するのは難しくなります。適切な家賃設定やリフォームを施した上で、90%〜95%を維持できていれば優良と言えるでしょう。新築時の高い入居率に安心せず、将来の低下に備えることが重要です。
はい、入居率は季節によって大きく変動します。不動産業界には、新入生や新社会人の移動が集中する1月〜3月という「繁忙期」が存在します。この時期は需要が供給を上回るため、空室は急速に埋まります。逆に、4月〜8月は「閑散期」となり、引越し需要が激減します。この時期に空室が発生すると、次の入居者が決まるまで数ヶ月を要することも珍しくありません。安定した入居率とは、この繁忙期に満室を達成し、閑散期に退去をいかに防ぐか、という運営技術の結果なのです。
はい、収益の安定化にとって、入居率の高さは最も重要な要素です。アパート経営の売上は「家賃単価 × 戸数 × 入居率」で決まります。どれだけ家賃単価を高く設定しても、入居率が80%であれば、売上は想定の2割引です。一方、家賃単価が相場通りでも、入居率が98%で安定していれば、毎月のキャッシュフローは極めて予測しやすく、安定します。この「収益の予測可能性」こそが、アパート経営の最大の魅力であり、その根幹を支えるのが高い入居率なのです。
入居率という言葉は簡単ですが、その「測り方」を間違えると経営判断を誤ります。例えば、月末時点の数字だけを見るのか、年間の平均で見るのかで、数字は全く変わってきます。経営者として、自物件の状況を正確に把握するための、正しい計算方法と把握のコツを身につけましょう。
最も正確な入居率の計算式は、「戸数」ベースではなく「日数」ベースで計算する「賃室稼働日数」を用いる方法です。
計算式: 年間入居率 = 年間の総入居日数 ÷ (総戸数 × 365日)
例えば、10戸のアパートで1室が30日間空室だった場合、
( (9戸×365日) + (1戸×335日) ) ÷ (10戸×365日) = 99.1% となります。
もし年の途中でアパート(10戸)が竣工した場合、分母となる「総戸数 × 365日」も、竣工日からの日数で日割り計算します。この日数ベースでの把握が、最も正確な経営実態を示します。
これらは目的によって使い分けるのが最適です。まず「月次」は、現場の空室状況を把握し、募集活動をチェックするための指標です。次に「四半期」は、繁忙期や閑散期といった季節変動の影響を含め、対策の効果を測定するために使います。そして最も重要なのが「年間」です。これは、最終的な事業の収益性を確定させ、金融機関への報告や次年度の事業計画を立てるための「経営指標」となります。
【入居率を測る目的とアクション】
| 指標(期間) | 見る目的(役割) | レポートの呼称 | 具体的なチェック項目 | オーナーが取るべきアクション(例) |
| 月次 (マンスリー) | 現場の状況把握 | オペレーション指標 (戦術の実行確認) | ・月末時点の入居率・空室戸数 ・当月の家賃滞納の有無 ・空室の募集反響数、内見数 ・退去予告の件数 | 【即時対応】 ・反響が少なければ、管理会社に「広告(AD)の追加」や「写真の変更」を指示する。 ・内見があるのに決まらなければ、「フリーレント」や「家賃1,000円調整」を指示する。 |
|---|---|---|---|---|
| 四半期 (クォータリー) | 季節変動を含めた 効果測定 | 戦術指標 (戦略の見直し) | ・3ヶ月間の平均入居率 ・繁忙期(1-3月)に満室にできたか ・閑散期(4-8月)の落ち込みはどうか ・前年同期との比較 ・広告費やリフォーム費用の投資対効果 | 【戦略の見直し】 ・繁忙期に満室を逃した場合、閑散期に向けた「大きな対策(家賃見直し、敷礼ゼロ)」を決定する。 ・次の繁忙期に向けた「リフォーム計画」を立てる。 ・管理会社の変更を検討する。 |
| 年間 (アニュアル) | 最終的な事業収益の 確定 | 経営指標 (事業成果の確定) | ・年間平均入居率(日数ベース) ・年間の総家賃収入、諸経費(管理費、修繕費、税金等 ・最終的なキャッシュフロー(手取り) ・当初計画(シミュレーション)との差異 ・実質利回りの確定 | 【経営・財務判断】 ・確定申告を行う。 ・実績に基づき、次年度の「収支予算」を作成する。 ・金融機関に「経営報告」を行い、追加融資(次の物件購入)や借り換え(リファイナンス)の交渉を行う。 |
両方の視点を持つことが不可欠です。「物件ごと」の入居率を詳細に見ることで、問題のある物件を早期に特定できます。例えば、全体の入居率が95%でも、A物件100%、B物件90%であれば、B物件に深刻な問題が隠れていることが分かります。一方、「ポートフォリオ全体」の入居率は、経営全体の安定性を示します。B物件が90%でも、他でカバーできていれば、キャッシュフローは安定します。
【入居率の「ミクロ」と「マクロ」視点】
アパート経営の成功には、虫の目(ミクロ)と鳥の目(マクロ)の両方が不可欠です。ミクロ視点で「個別の問題」を潰し、マクロ視点で「経営全体」の舵を取る。この使い分けが安定したキャッシュフローを生み出します。
| 視点 | 役割・わかること | 具体的なチェック項目 | この視点から取るべきアクション(例) | 陥りがちな「罠」(この視点だけだと…) |
| 物件ごと (ミクロ) | 問題点の早期特定 個別の物件や部屋が抱える問題(家賃、管理、設備)を具体的に把握する。 | ・特定の1室の空室期間(例:A棟101号室が90日空室) ・特定の物件の入居率(例:B棟だけ80%) ・近隣の競合物件の最新の家賃・設備 ・特定の部屋へのクレーム(例:201号室の水漏れ) | 【戦術的な短期改善】 ・A棟101号室の家賃を3,000円下げる。 ・B棟に「ネット無料」を導入する。 ・201号室の即日修理を管理会社に厳命する。 ・反響が悪い部屋の広告写真を撮り直す。 | 「木を見て森を見ず」 1室の空室を焦るあまり、高額なリフォーム(50万円)を打つなど、過剰な投資(費用対効果の悪化)をしてしまう。 全体最適を見失う。 |
|---|---|---|---|---|
| 全体 (マクロ) | 経営全体の安定性確認 保有する全物件(ポートフォリオ)の平均的な健全性や、キャッシュフローの総額を確認する。 | ・全物件合計の平均入居率(例:5棟50室中 96%) ・全物件合計の月間キャッシュフロー(手取り) ・ローン返済比率(全体) ・年間の収益(確定申告ベース) | 【戦略的な中長期判断】 ・ポートフォリオ全体でローンの借り換え(リファイナンス)を検討する。 ・赤字のB棟を売却し、優良なC棟に入れ替える。 ・安定したキャッシュフローを元手に、次の物件(6棟目)の融資を打診する。 | 「森を見て木を見ず」 全体の入居率が96%と良好なため、B棟が80%で赤字を垂れ流していることを見逃してしまう。 「平均の罠」に陥り、個別の問題点の発見が遅れる |
入居率は、表面利回りと実質利回りのギャップを生む最大の要因です。「表面利回り」は、多くの場合「満室想定(入居率100%)」で計算されます。しかし、実際の経営では必ず空室が発生します。一方、「実質利回り」は、家賃収入から諸経費を引いて計算しますが、この「家賃収入」自体が入居率に左右されます。例えば、入居率が90%なら、満室想定の家賃収入より10%も売上が減るため、実質利回りは劇的に悪化します。高い表面利回りよりも、現実的な入居率に基づいた実質利回りを重視すべきです。
 Rielからのアドバイス
Rielからのアドバイスアパート経営で最も恐ろしいのは、「入居率10%低下=手取り10%低下」ではないことです。ローン返済や税金・管理費などの「固定費」は一切減りません。売上が10%減った結果、手元に残るキャッシュフローが30%〜50%も減少するケースは珍しくありません。これがアパート経営のレバレッジの怖さであり、私たちが「入居率95%以上」に徹底的にこだわる理由です。
入居率95%という目標(KGI)を達成するためには、そこに至るプロセス(KPI)の管理が不可欠です。私たちが重視するKPIは、まず「空室期間(募集期間)」で、退去発生から45日以内の成約を目指します。この期間を短縮するため、募集開始後の「反響数(ポータルサイトからの問い合わせ数)」を週次でチェックします。反響が少なければ「家賃設定」か「広告写真」に問題ありと判断します。反響はあるのに「成約率(内見からの申込率)」が低ければ、室内の状態や仲介会社の営業力に問題ありと切り分け、即座に対策を打ちます。
一口に入居率95%と言っても、その難易度はエリアや間取りによって全く異なります。需要の厚い都心のワンルームと、需要の限られる郊外のファミリータイプとでは、目指すべき入居率の前提も、打つべき対策も変わります。ここでは、物件の属性に応じた入居率の考え方を解説します。
需要の「量」と「質」が異なるため、前提も変わります。「都市部」の駅近物件は、単身者やDINKSなど入居希望者の絶対数が多く、需要は常に旺盛です。そのため、高い入居率(97%以上)を維持することが前提となります。一方、「郊外」は、入居者層(ファミリーや車通勤者)が限定され、一度空室になると次の入居者が見つかるまでの期間が長引く傾向があります。そのため、年間の入居率目標は90%〜95%と現実的に設定し、それ以上に「一度入居したら長く住んでもらう(退去率を下げる)」戦略が重要になります。
【エリア別:入居率の前提と経営戦略 詳細解説テーブル】
アパート経営の戦略は、需要の「量」と「質」が全く異なる「都市部」と「郊外」で、根本的に変える必要があります。都市部は「回転率」を前提としたスピード勝負、郊外は「定着率」を重視した安定性勝負となります。
| エリア | 需要の特徴 | 主なターゲット | 入居率の考え方・戦略 | 最重要KPI(経営指標) | 空室時の主な対策 |
| 都市部 (例:山手線沿線、主要駅徒歩7分以内) | 需要が常に旺盛 ・賃貸需要の絶対量が多い。 ・単身者、DINKS中心で、入居者の入れ替わりが激しい(回転率が高い)。 | 高所得単身者、 共働きカップル(DINKS)、 法人契約 | 短期決戦型(回転率重視) ・退去は多い前提で、いかに「早く埋めるか」が全て。 ・退去コスト(原状回復、広告料)は必要経費と割り切る。 ・常時97%以上の高い入居率維持を目指す。 | 募集期間(空室日数) (例:退去から30日以内の成約) | ・仲介会社へのAD(広告料)増額 ・1,000円単位での家賃調整 ・写真の撮り直しなど広告強化 (スピード重視) |
|---|---|---|---|---|---|
| 郊外 (例:バス便エリア、急行通過駅) | 需要が限定的 ・特定のターゲット(ファミリー、車通勤者、近隣の学生)に限られる。 ・一度空室になると、次の入居者が見つかるまで時間がかかる。 | ファミリー層、 車通勤者、 近隣の大学・工場の関係者 | 長期安定型(定着率重視) ・一度入居したら「いかに長く住んでもらうか」が全て。 ・退去を減らし、原状回復費や広告料の発生を抑える。 ・年間平均で90%〜95%を堅守する。 | 平均入居期間 (例:4年以上) 退去率 | ・退去防止(更新料の割引、クレームへの迅速対応) ・駐車場の完備や間取りの広さを強くアピール ・地域の不動産屋との関係強化 |


はい、間取り(=ターゲット層)によって「退去率」が異なるため、入居率の考え方も変わります。ワンルーム・1Kは、学生や単身社会人がメインターゲットのため、需要は厚いですが、卒業・就職・転勤・結婚といったライフイベントで退去が頻繁に発生します。高い入居率を維持するには、この「高い回転率」を前提としたスピーディな募集活動が必須です。一方、1LDK(カップル)や2LDK以上(ファミリー)は、入居期間が5年〜10年と長くなる傾向があります。一度満室になれば、数年間100%の入居率が続くことも珍しくありません。
【間取り別:入居率の特性と経営戦略 詳細解説テーブル】
間取り(=ターゲット)が変われば、経営スタイルも変える必要があります。1Kは「短期・回転型」のビジネス、1LDK以上は「長期・安定型」のビジネスと認識することが、経営戦略の第一歩です。
| 間取り | メインターゲット | 入居率の特性(回転率) | 入居期間(目安) | 収益(CF)の特徴 | 経営戦略の要点(KPI) |
| 1K (ワンルーム) | 学生・単身社会人 | 回転型(退去率:高) ・需要の絶対数は最も多い。 ・卒業、就職、転勤、結婚など、ライフイベントでの退去が頻繁に発生する。 | 2年〜4年 | ・キャッシュフローは不安定になりがち。 ・退去の度に「原状回復費」「広告料」が頻繁に発生し、手取り(実質利回り)を圧迫する。 | 【募集スピードが命】 ・空室期間の短縮(例: 45日以内)が最重要KPI。 ・繁忙期(1-3月)に満室にできるか。 ・仲介会社へのAD(広告料)投入を惜しまない。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1LDK / 2LDK (ファミリータイプ) | カップル・新婚・ファミリー | 安定型(退去率:低) ・需要は1Kより限定的。 ・一度入居すると、子供の学区や住環境を変えたくないため、長く住む傾向が強い。 | 4年〜10年 | ・キャッシュフローは安定しやすい。 ・退去が少ないため、原状回復費や広告料の発生が稀。 ・一度満室になれば、数年間「入居率100%」が続くことも多い。 | 【退去防止が命】 ・平均入居期間の長期化が最重要KPI。 ・クレームへの迅速対応、共用部の清掃など「管理の質」で満足度を高める。 ・更新料の割引などで長期入居を促す。 |
ターゲットごとに、入居率達成の「勝負どころ」が異なります。「学生」ターゲットの場合、何よりも1月〜3月の繁忙期に満室にできるか、その「繁忙期決定率」が全てです。ここを逃すと1年間空室になるリスクもあります。「単身社会人」は、通年で移動需要があるため、「空室発生から成約までの日数(募集期間)」をいかに短縮できるかが指標となります。「ファミリー」は、前述の通り、入居率そのものよりも「平均入居期間」を重視すべきです。入居期間を2年から4年に延ばせれば、退去に伴うコスト(原状回復費、広告料)が半減し、収益性は劇的に改善します。
アパート経営の成功は、ターゲットの特性に合わせた「正しいKPI(重要業績評価指標)」を追いかけることから始まります。学生相手に「平均入居期間」を追っても意味はなく、ファミリー相手に「募集スピード」だけを追っても経営は安定しません。ターゲットごとに、どこに注力すべきかを解説します。
| ターゲット | 最重要KPI(経営指標) | 目標数値(目安) | なぜ、それが最重要なのか?(理由) | KPI達成のための具体的アクション(例) |
| 学生 | 繁忙期決定率 (1〜3月の成約率) | 100% | ・学生の引越し需要はこの3ヶ月間に異常に集中する。 ・この「合格発表~入学式」の波を逃すと、次の入居者が見つかるのは1年後(次の繁忙期)になる危険性が極めて高い。 ・1年間の空室は、経営における最大の損失となるため。 | ・新築の場合、竣工時期を1月〜2月に厳守する。 ・前年12月から「大学の生協」「学生専門サイト」へ先行して広告を出す。 ・「ネット無料」「敷金・礼金ゼロ」で、親御さんが負担する初期費用を徹底的に抑える。 |
|---|---|---|---|---|
| 単身社会人 | 募集期間(空室日数) | 45日以内 (退去発生〜申込まで) | ・通年で移動需要はあるが、転勤・転職・結婚などによる退去も頻繁に発生する(=回転率が高い)。 ・1日の空室でも確実に損失(家賃÷30日)が発生するため、スピードが収益(キャッシュフロー)に直結する。 ・空室期間が延びるほど、収益性が悪化する。 | ・退去予告が出た瞬間に(退去前でも)募集を開始する(先行募集)。 ・仲介会社への「AD(広告料)」を相場より上乗せ(例: 2ヶ月分)し、紹介の優先順位を上げてもらう。 ・「独立洗面台」「宅配ボックス」など、ターゲットに刺さる設備で差別化する。 |
| ファミリー | 平均入居期間 (退去率の低減) | 4年以上 (できれば6年以上) | ・1LDKや2LDKは、1Kに比べ需要が限定的で、一度空室になると次の入居者が見つかるまでの募集期間が長引く傾向がある。 ・退去1回あたりの原状回復コストも高額になりがち。 ・したがって、募集の速さよりも「退去させない(長く住んでもらう)」ことが、コスト削減と収益安定化に直結する。 | ・クレーム(騒音・水漏れ)や設備故障に迅速・丁寧に対応する(管理の質)。 ・共用部の清掃を徹底し、住環境の満足度を高く維持する。 ・「更新料の割引/免除」や「謝礼(ギフト)」で、長期入居者に感謝を示し、継続入居を促す。 |


入居率に対して「決定的」な影響を与えます。特に単身者向け物件において、「駅距離(徒歩分数)」は入居者が検索サイトで最初に入力する絞り込み条件であり、徒歩10分を超えると反響数は激減します。「通勤通学動線(主要駅へのアクセス)」も同様に重要です。また、「生活インフラ(帰り道にあるスーパー、コンビニ)」は、日々の暮らしやすさに直結するため、内見時の成約率を大きく左右します。立地の不利は、家賃を大幅に下げる以外でのリカバリーが難しく、土地選定の段階で入居率の8割は決まってしまうと言っても過言ではありません。
非常に効果的ですが、諸刃の剣でもあります。「ペット可」物件は、供給が少ないため、一度決まれば相場より高い家賃でも成約しやすく、退去率も低い傾向があります。しかし、匂いや傷、騒音といったトラブルのリスクを伴います。「楽器可」も同様に、音大生や趣味層というニッチな需要を確実に取り込めますが、高度な防音設計が必須です。これらの「属性緩和」は、通常の募集で苦戦する立地や築古物件において、明確な差別化戦略として採用する価値がありますが、リスク管理(厳格な規約、割増の敷金など)とセットで検討すべきです。
入居率が低下した際、ただ待っていても事態は好転しません。問題点を「募集条件」「賃料」「商品力」の3つに切り分け、スピーディに対策を打つ必要があります。空室は1日ごとに損失を生み出す「穴の空いたバケツ」です。その穴を最速で塞ぐための具体的な改善策を解説します。
反響が少ない場合、家賃本体を下げる前に、入居者の「初期費用」と仲介会社の「モチベーション」を見直すべきです。見直すべきは以下の点です。
これらの「一時的な費用」で決まるなら、家賃という「永続的な収入」を下げるより遥かに合理的です。
賃料は、入居者が最も敏感に比較するポイントです。重要なのは「競合より1,000円でも安く、魅力的に見せる」価格設定です。例えば、SUUMOなどで検索した際、近隣の同等物件が80,000円なら、79,000円に設定するだけで検索結果の「7万円台」のカテゴリに入り、反響が倍増することがあります。逆に、設備で圧倒的に勝っているなら「相場+3,000円」でも決まります。感覚で決めず、必ず競合の募集賃料を調査し、戦略的な価格(値付け)を行うことが成約率に直結します。
「原状回復」は、壁紙を白に戻すなど、マイナスをゼロにする作業です。これだけでは入居は決まりません。入居率を上げるには、ゼロをプラスにする「差別化リフォーム」が必要です。線引きは「入居者の記憶に残るか」です。例えば、ただの白い壁紙を、一面だけ「アクセントクロス(色付きの壁紙)」に変える。古いインターホンを「モニター付きインターホン」に交換する。これらは数万円の投資ですが、内見時の印象を劇的に改善し、「ここに住みたい」という動機付けに強く“刺さる”改善策となります。
費用対効果が抜群に高いのは、「入居者が自分で導入すると面倒だが、無いと不便なもの」です。その筆頭が以下の3点です。


反響(問い合わせ数)は、掲載コンテンツの質で「10倍変わる」と言っても過言ではありません。入居者はまず、ポータルサイトの写真と間取図だけで「内見に行くか行かないか」を判断します。暗く、狭く見える写真や、情報が古い間取図は、それだけで候補から除外されます。明るい日に広角レンズで撮影した鮮明な写真、収納のサイズまで分かる詳細な間取図、そして「VR内見」のように、オンラインで室内を体験できるコンテンツは、反響率を飛躍的に高めます。広告コンテンツへの投資は、最も安価で効果的な空室対策です。
仲介会社の営業担当者は、あなたの物件の「販売員」です。彼らが「売りやすい」情報を提供することが成約への近道です。単に「空室なので決めてください」ではなく、以下の3点をセットで伝えるべきです。
彼らがお客様に説明しやすい「武器」と「実利」を提供することが、決まりやすい営業のコツです。
入居者の三大不安である「防犯・防音・断熱」への対策は、退去率の低下(=入居率の維持)に直結します。
これらの対策は、入居者の「安心・快適」に繋がり、長期入居を促します。
空室が発生した場合、その損失は1日単位で蓄積していきます。家賃8万円なら、1日の損失は約2,600円です。重要なのは、対策の「費用対効果」を冷静に判断し、「スピード感」をもって実行することです。空室期間の長期化は、あらゆる対策コストを上回る最大の損失源となります。
私たちは「1ヶ月」がデッドラインだと考えています。もし退去から1ヶ月経っても反響すらない場合、その物件は市場の相場からズレています。家賃1ヶ月分の損失(例:8万円)が発生した時点で、その8万円を「対策費用」として投資すべきです。例えば、ADを1ヶ月分上乗せする、フリーレント1ヶ月をつける、家賃を3,000円下げる(年間36,000円の損失)。これらは全て、もう1ヶ月空室が続く損失(8万円)よりも安価な対策です。傷が浅いうちに、コストを投じてでも決めにいくスピード感が重要です。



空室が発生した瞬間から、オーナーの「損失」は1日単位で発生します。家賃8万円なら1日約2,600円です。1ヶ月空室が続けば8万円の損失が確定します。その「8万円」は、次の1ヶ月も空室が続くリスクを回避するための「対策予算」です。ADを上乗せする、家賃を2,000円下げる。これらは全て「損失の最小化」のための投資です。判断の遅れが、損失を雪だるま式に増やすことを肝に銘じてください。
優先順位は、まず最低条件を整え、次に価格を見直し、最後に商品力を上げる、という手順を踏みます。
反響が少ない時は、以下の手順で「診断」し、原因を切り分けます。
チャネルは、ターゲットに応じて使い分けるのが最も効率的です。それぞれの役割を理解しましょう。
アパートの募集は、ターゲット層が最も多く集まる「池」で「最適な釣り糸」を垂らすことが鉄則です。各チャネル(媒体)の特性を理解し、コストと効果を最大化する使い分けを解説します。
| チャネル(媒体) | 目的・メインターゲット | 強み(メリット) | 弱み(デメリット・注意点) | オーナーが取るべきアクション(戦略) |
| ポータルサイト (SUUMO, HOME’S 等) | 【主戦場】 全ターゲット層(特に学生、社会人、カップル)への広範な露出。 | ・圧倒的な集客力と認知度。 ・詳細な絞り込み検索(駅距離、設備)が可能で、ニーズが明確な層に届く。 | ・広告掲載料(コスト)が高い。 ・競合物件も大量に掲載されており、埋もれやすい(価格競争になりがち)。 | ・掲載料を惜しまず、仲介会社に上位表示を依頼する。 ・「写真の質と枚数」に徹底的にこだわる(暗い写真は論外)。 ・仲介会社が魅力的なキャッチコピーを書いているかチェックする。 |
|---|---|---|---|---|
| 現地募集(看板) | 【地域密着】 近隣からの住み替え層(ファミリー、同棲準備)、たまたま通りかかった人。 | ・低コスト(看板製作・設置代のみ)。 ・エリアを限定して探している「今すぐ客」や「潜在層」に直接アピールできる。 | ・リーチできる範囲が極めて限定的(物件の前を通る人のみ)。 ・天候に左右される。 ・詳細な情報(室内の写真など)を伝えられない。 | ・「満室御礼」の看板を出すまでは、大きく目立つ看板を設置する。 ・「駐車場あり」「〇〇小学校区」など、その場で強みが伝わる情報を大きく記載する。 ・QRコードを載せて詳細なWebページに誘導する。 |
| Instagram (SNS) | 【ブランディング】 デザイン性の高い物件のファン獲得。特定の価値観を持つ層(例:ヴィンテージ好き、ミニマリスト)。 | ・視覚(写真・動画)で物件の「世界観」や「理想の暮らし」を強力に訴求できる。 ・ハッシュタグで潜在層にリーチ可能。 ・ファン化すれば「指名で」入居が決まる。 | ・即効性が低い(日々の運用が必要)。 ・「条件(家賃・駅距離)」で探す層には届きにくい。 ・運用の手間とセンスが必要。 | ・建築時に「写真映え」するスポット(例:アクセントクロス、造作洗面台)を意図的に作る。 ・ターゲットが憧れるような「暮らし方」を写真で提案する。 ・即時満室を狙うメインチャネルではなく、長期的な空室対策と位置づける。 |
| 自社サイト (オーナーHP) | 【コスト削減】 広告費の削減、直接募集。複数棟オーナーのリピーター(ファン)獲得。 | ・ポータルサイトへの広告費(コスト)を削減できる(=利益率向上)。 ・掲載情報に制限がなく、オーナーの「想い」や「こだわり」を自由に伝えられる。 | ・集客力がほぼゼロ。 (SEO対策が必須だが難易度が高く、時間もかかる)。 ・サイトの構築・維持にコストと手間がかかる。 | ・1棟目のオーナーが手を出すべきではない。 ・複数棟を運営し、管理会社への依存度を下げたい段階で検討する。 ・ポータルサイトと併用し、「自社サイトからの申込なら特典あり」と誘導する。 |
はい、特に「学生」や「新社会人」など、月々の支払い能力はあるが「貯蓄が少ない」ターゲット層に対して、極めて有効な施策です。敷金・礼金・前家賃など、入居時の初期費用は家賃の4〜5ヶ月分にもなり、これが払えずに契約を諦めるケースは少なくありません。この初期費用を「クレジットカード決済可」にしたり、「分割払い」に対応したりするだけで、入居希望者の間口は大きく広がります。オーナー側の負担(決済手数料)も僅かであり、導入しやすい入居率改善策の一つです。
入居率は、目先の収益性(キャッシュフロー)だけでなく、将来の「融資(事業拡大)」や「出口戦略(売却)」の成否にも決定的な影響を与えます。金融機関も投資家も、あなたの物件の「入居率」という実績(数字)で、あなたの経営手腕を判断するからです。
入居率は、実質利回りとキャッシュフローに「ダイレクト」に効きます。実質利回りの計算式は((家賃収入×入居率)-諸経費)÷物件価格 です。入居率が10%下がれば、家賃収入は10%減少します。しかし、ローン返済や管理費、固定資産税といった「諸経費」は一切減りません。そのため、売上が10%減ると、手残りの「キャッシュフロー」は20%、30%と、それ以上に激減します。入居率のわずかな低下が、経営の根幹を揺るがすインパクトを持っているのです。
はい、金利上昇局面では、入居率の目標目安を「より高く」変えるべきです。なぜなら、金利が上昇すると、ローンの返済額(=支出)が増加するからです。支出が増える以上、それを補うためには「収入(家賃)」を増やすか、「損失(空室)」を減らすしかありません。家賃を上げるのが難しい市況であれば、空室期間を1日でも減らし、入居率を95%から97%、98%へと高める努力(=損失の徹底的な圧縮)が、キャッシュフローを維持するための最も重要な防衛策となります。
金融機関は、あなたの「経営者としての実績」を非常に厳しく評価します。1棟目の新築時は「事業計画書(=理想)」で評価されますが、2棟目以降の追加融資審査では、必ず1棟目の「稼働実績(=現実)」の提出を求められます。もし1棟目の入居率が80%台で低迷していれば、「このオーナーに任せても計画通りに返済できない」と判断され、融資は否決されるでしょう。逆に、計画通り95%以上を維持していれば、「優秀な経営者」として、より良い条件(低金利・高額)での融資が期待できます。
売却価格に対して「決定的」なインパクトを与えます。収益物件の価格は、その物件が生み出す純収益(NOI)を、利回り(キャップレート)で割戻して算出されます(価格 = NOI ÷ 利回り)。NOIは(家賃収入 × 入居率 - 経費)です。つまり、入居率が低い物件はNOIが低く、売却価格はNOIに比例して安くなります。購入希望の投資家にとって、満室(入居率100%)で稼働している物件は、最も安心できる「優良資産」であり、高値でも買われます。入居率は、あなたの資産価値そのものなのです。


はい、サブリース(一括借上)は、入居率の変動リスクを「完全に回避する」ための手段です。サブリース会社がオーナーから全室を借り上げ、入居率に関わらず毎月一定の賃料(通常、満室家賃の80%〜90%)を保証してくれるからです。これにより、収益は安定しますが、満室時の最大収益(100%)は得られなくなります。入居率のブレという「リスク」を、10%〜20%の「コスト」を払って専門業者に移転する取引とも言えます。日々の運営の手間を省きたい方には有効な選択肢です。


高い入居率を達成する「攻め」の戦略も重要ですが、一度入居した方に長く住んでもらう「守り」の戦略(退去抑制)は、それ以上に収益安定に貢献します。退去が1件減れば、原状回復費も広告料も発生しません。その鍵を握るのが、日々の「管理体制」です。
退去理由の多くは、家賃や立地といった「ハード面」よりも、管理対応への不満といった「ソフト面」にあります。退去を防ぐには、入居者の「小さな不満」を「大きな不満」になる前に察知し、解決するコミュニケーションが不可欠です。例えば、定期的な共用部の清掃報告や、季節の挨拶、近隣情報の掲示など、オーナー(管理会社)の「目配り」を感じてもらうことが重要です。「この管理会社(オーナー)はしっかりしている」という安心感が、満足度向上と長期入居に繋がります。
クレーム対応や設備故障は、「スピード」が命です。対応の遅れは、入居者満足度を最も低下させる要因となります。私たちが設定するSLA(サービスレベルの目安)は、まず「一次対応(受付と状況確認の連絡)」は24時間以内。特に「緊急対応(水漏れ、お湯が出ない等)」は、即日〜翌日中での解決を目指します。「通常対応(建具の不具合等)」であっても、1週間以内には何らかのアクション(修理日程の確定)を行うべきです。この迅速な対応こそが、信頼関係の基盤となります。
更新時は、退去を防ぐ「最大のチャンス」です。日本では、よほどの好景気でない限り、既存入居者への「家賃改定(値上げ)」は退去の引き金になりやすく、悪手となることが多いです。むしろ、退去されて発生するコスト(空室期間、原状回復、広告料=家賃の3〜4ヶ月分)を考えれば、「更新料を半額(またはゼロ)」にする、「ささやかなギフト(数千円のクオカード等)を贈る」といったインセンティブ(優遇策)を提供する方が、遥かに合理的です。「長く住んでくれてありがとう」という姿勢を見せることが、最も効果的な退去抑制策となります。
入居者の満足度、ひいては内見者の「第一印象」は、共用部の状態で決まります。エントランスにチラシが散乱していたり、ゴミ置き場が荒れていたり、掲示板が古い情報で埋まっていたりすると、「この物件は管理されていない」という強烈なマイナスイメージを与えます。逆に、共用部が常に清潔に「清掃」され、季節の花が飾られ、「掲示物」が整理されている物件は、入居者のモラルも向上し、内見者にも「大切にされている物件だ」という安心感を与えます。共用部管理は、コストではなく「投資」です。
管理会社を「月額手数料の安さ(例:家賃の3% vs 5%)」だけで選ぶのは、最も危険な選択です。手数料が安くても、空室を3ヶ月も埋められない管理会社が、最大のコスト(空室損失)を生むからです。手数料よりも重要な評価軸は、以下の3点です。
手数料が5%でも、1ヶ月で満室にしてくれる会社は、3%で3ヶ月かかる会社より遥かに優秀です。



管理会社を「月額手数料」だけで選ぶのは、アパート経営で最もよくある失敗の一つです。本当のコストは「空室」です。月額5%でも1ヶ月で空室を埋めるA社と、月額3%でも3ヶ月かかるB社。どちらがオーナー様の利益になるかは明白です。B社は手数料が安い代わりに、2ヶ月分の家賃を丸ごと失わせています。私たちは「客付けのスピード」と「退去させない管理力」こそが、管理会社の最大の価値だと考えます。
アパート経営の入居率は、竣工後に「運用で上げる」ものではありません。私たちRielは、土地を選定し、建物を計画する「着工前」の段階で、高い入居率を「設計する」という発想を最も重視しています。入居率は、運ではなく技術で作り出すものなのです。
私たちは、土地の価格以上に「賃貸需要の強さ」を厳しく審査します。入居率を設計する上で、立地は最も変更不可能な要素だからです。
【Riel式 土地選定チェックリスト】
これらの基準をクリアしない土地は、どれだけ安くても「入居率を設計できない土地」として、私たちは選びません。
土地の需要源を特定したら、次はその「ターゲット」に100%合致した「間取り」を設計します。これが空室リスクを回避する最短ルートです。例えば、土地選定で「〇〇病院の看護師需要が強い」と判断すれば、一般的な1K(22㎡)ではなく、夜勤明けの快適性を追求した「広めの1K(28㎡)、WIC付、独立洗面台・浴室乾燥機完備」という間取りを設計します。このように、ターゲットの解像度を極限まで高め、そのニーズに完全に応える「専用商品」を作ることで、競合に対する圧倒的な優位性を確保します。
私たちは、新築アパートが数年後に「築古」になることを見据え、長期的に競争力を維持できる設備・仕様を「標準パッケージ」として組み込んでいます。なぜなら、建築時に組み込む方が、後からリフォームするより遥かに低コストで導入できるからです。具体的には、「高速インターネット無料」「宅配ボックス」「TVモニター付きドアホン」「システムキッチン(2口コンロ)」「アクセントクロス」などを標準仕様としています。これらは「あれば嬉しい」ではなく「無ければ選ばれない」時代になっており、これらを標準装備することが、将来の入居率低下を防ぐ「ワクチン」となるのです。
引用:国土交通省「賃貸住宅市場の動向」
私たちは、建物が完成してから募集を始めるような、悠長なことはしません。竣工時満室(初期リーシングの成功)こそが、事業のスタートダッシュを決める最大の鍵だからです。そのために、竣工の3ヶ月前から「募集設計」を開始します。高品質なCGパースや図面を作成し、近隣の全仲介会社を訪問して「仲介網」を構築。「この物件は〇〇が強みです」「ADは〇ヶ月出します」と徹底的に営業します。この「先行営業」というプロセス(型)を踏むことで、建物の「引渡し」時点で、既に入居申込が50%以上入っている状態を作り出すのです。
私たちが手掛けた埼玉県の某新築アパート(1K・12戸)の実例では、お引渡しからわずか2ヶ月半(繁忙期)で満室を実現しました。その「再現可能なポイント」は、以下の3点です。
この「需要の発見」と「需要に合わせた戦略」こそが、満室経営を「設計」するプロセスなのです。