超高利回りアパート投資の秘密
\\\知りたい方はこちら///

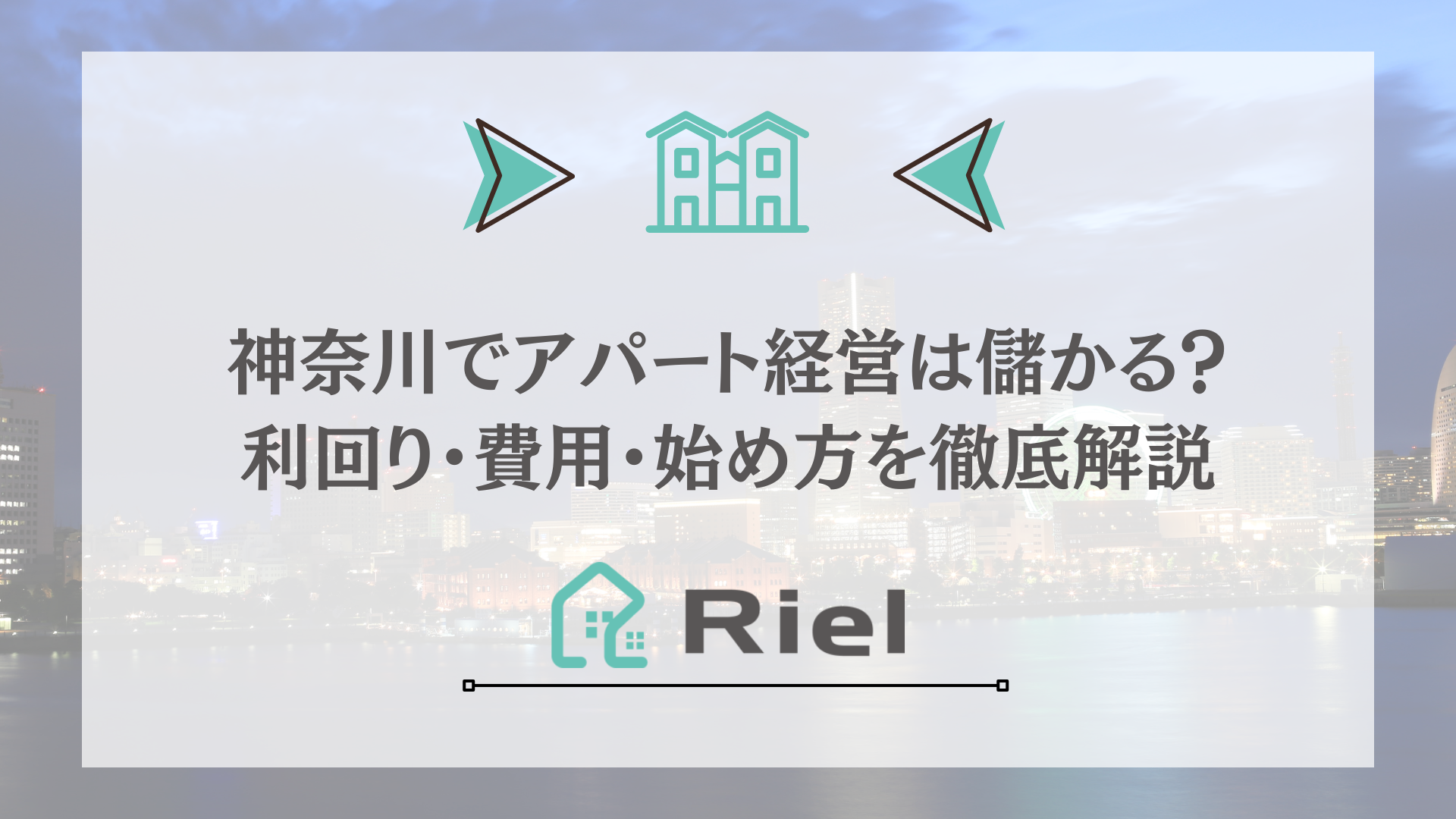
監修者

株式会社Riel 代表取締役
坂口 卓己(サカグチ タクミ)
宅地建物取引士として年間57棟の販売実績を誇り、東京都渋谷を拠点に新築アパートの企画開発から資金計画、満室運営、出口戦略まで一貫支援。豊富な現場経験と最新市況データを融合し、信頼とスピードを重視したサービスで投資家一人ひとりに最適な資産形成プランを提案する不動産投資のプロフェッショナル。
⇒詳細はこちら
「神奈川でアパート経営を始めたいが、本当に儲かるのか?」そのように悩んでいませんか。神奈川県のアパート経営は、東京に次ぐ日本第2位の人口を背景にした強固な賃貸需要があり、初心者でも堅実なリターンが狙える優良市場です。しかし、成功には戦略が不可欠です。本記事では、利回りや費用の実情から、新築初心者が成功するための戦略まで、アパート経営のプロ㈱Rielが徹底解説します。
神奈川県でのアパート経営は、東京とはまた異なる独自の特徴を持っています。結論から言えば、市況の理解と適切な戦略があれば「儲かる」可能性は非常に高い市場です。土地代や建築費は高額ですが、それを上回る圧倒的な賃貸需要が存在します。まずは初心者が知るべき神奈川市場の基本と実情を正しく把握しましょう。
神奈川の賃貸市場は、日本第2位の人口(約920万人)という強固な需要に支えられています。その理由は、横浜市・川崎市という巨大な経済圏が県内に存在すること、そして東京へのアクセスが良く巨大なベッドタウンでもあるという「二重の需要」があるためです。特に川崎市は東京への通勤者に、横浜市や湘南エリアは独自の勤務・通学者に支えられており、単身者からファミリーまで幅広い需要が絶えません。
引用:神奈川県統計センター
神奈川のアパート経営が魅力的なのは、東京に準じて高い家賃水準を維持できる点にあります。全国平均と比較して家賃相場は非常に高く、これが収益性の基盤となります。特に横浜市・川崎市の主要駅周辺では、高い家賃でも入居者が決まるのが神奈川市場の強みです。また、入居率も非常に高い水準で安定しています。適切な立地と物件であれば、入居率は95%以上を維持することも珍しくありません。空室期間が短いため、計画通りのキャッシュフローを実現しやすい環境だと言えるでしょう。
神奈川(首都圏)と地方のアパート経営は、投資の性質が大きく異なります。地方は土地代が安いため高利回りに見えますが、空室リスクも高くなります。一方、神奈川は利回りが低めに見えますが、需要が安定しているため堅実な経営が可能です。それぞれの特徴を理解し、ご自身の投資スタイルに合った市場を選ぶことが重要です。
| 比較項目 | 神奈川(首都圏) | 地方 |
| 初期費用(土地代) | 高い | 低い |
|---|---|---|
| 表面利回り | 低め | 高め |
| 空室リスク | 低い(人口流入・高密度) | 高い(人口減少) |
| 家賃下落リスク | 低い | 高い |
| 資産価値 | 高く、安定 | 変動しやすい |
 Rielからのアドバイス
Rielからのアドバイス神奈川市場は「ローリスク・ミドルリターン」の典型です。地方の「ハイリスク・ハイリターン」とは対極です。「東京ほどの超高額投資は避けたいが、地方のような空室リスクは取りたくない」という方に神奈川は最適です。まずはこの「市場の違い」を認識することが第一歩です。
神奈川でのアパート経営を具体化するには、「数字」の理解が欠かせません。利回りはもちろん重要ですが、それ以上に「いくら投資し、最終的に手元にいくら残るのか」という収益モデルの把握が成功の鍵です。特に新築の場合、初期費用は高額になりますが、長期的な視点でのシミュレーションが重要となります。
利回りの数字だけを見て「中古の方が儲かる」と判断するのは早計です。新築は表面利回りが低く見えがちですが、融資や修繕の面で圧倒的に有利だからです。特に初心者は、修繕リスクが低く、融資期間を長く設定できる新築の方が、結果的にキャッシュフロー(手残り)が安定するケースが多々あります。長期的な安定収益を狙うなら、新築のメリットを最大限に活かすべきです。
| 比較項目 | 新築 | 中古 |
| 表面利回り | 低め | 高め |
|---|---|---|
| 融資期間 | 長い(最長可) | 短い(耐用年数による) |
| 金利 | 優遇されやすい | やや高め |
| 修繕リスク | 低い(当面不要) | 高い(即時必要な場合も) |
| キャッシュフロー | 安定しやすい | 変動しやすい |
神奈川で新築アパートを建てる場合、初期費用は大きく3つに分類されます。総額が大きくなるため、自己資金をどれだけ用意できるかが最初の関門です。特に「諸経費」は物件価格以外に現金で必要となるケースが多いため、見落とさないよう注意しましょう。
アパート経営で最も重要な指標は「キャッシュフロー(CF)」、つまり手残りの現金です。表面利回り(年間家賃収入 ÷ 物件価格)だけを見てはいけません。以下の流れで、必ずCF(手残り)がプラスになる計画を立ててください。
このCFがマイナスになる計画は非常に危険です。弊社(Riel)では、10年後、20年後の家賃下落や修繕費も考慮した、現実的なシミュレーションをご提示しています。



初心者が陥りがちなのが「表面利回り」の罠です。神奈川の人気エリア(例:武蔵小杉、横浜駅周辺など)で新築表面利回り7%超といった物件は、何かしらのリスク(駅から遠すぎる、法規制が厳しい等)を抱えている可能性が高いです。Rielでは、利回りの数字だけを追うのではなく、長期的に安定した「キャッシュフロー」が残る堅実な事業計画を最優先にご提案します。
初期投資の大きさを懸念される方も多いですが、神奈川にはそれを補って余りある明確なメリットが存在します。東京に準ずる「安定性」と「資産性」こそが、神奈川でアパート経営を始める最大の動機となります。なぜプロの投資家が神奈川を選ぶのか、その理由を3つの側面に分けて解説します。
神奈川で経営する最大のメリットは、空室リスクの低さです。日本の総人口は減少していますが、東京圏(神奈川県含む)への人口流入は続いています。特に神奈川県は、東京への通勤利便性から選ばれるだけでなく、県内(横浜・川崎など)の企業も多いため、賃貸住宅のメインターゲットである若年層・単身者が集まり続けています。需要が供給を上回る状況が続いているため、立地選定を間違えなければ、長期にわたり安定した入居率を維持できるのです。
神奈川は、多様な人々が集まる県です。そのため、賃貸ニーズも非常に多様化しています。土地から新築で設計する(Rielの得意分野です)場合、そのエリアのニーズに最適化した物件を供給できるため、競合との差別化が容易です。


アパート経営は家賃収入(インカムゲイン)だけでなく、出口戦略(キャピタルゲイン)も重要です。神奈川県、特に横浜市・川崎市の主要駅周辺の土地は、資産価値が非常に高く、景気変動の影響を受けにくい実物資産です。価値が下がりにくいため、将来的に売却する際も買い手が見つかりやすく、インフレ対策としても有効に機能します。また、アパート(貸家)は相続税評価額を大幅に圧縮できるため、相続対策として活用されるケースも非常に多いのが特徴です。





神奈川の資産価値の高さは、金融機関からの「融資」においても有利に働きます。担保評価が高く出るため、より良い条件(低金利・長期間)での融資が期待できるのです。これは、地方物件では得難い大きなメリットであり、アパート経営の成功確率を直接的に高める要因となります。
もちろん、神奈川でのアパート経営にはメリットばかりではありません。最大のハードルは、東京に準ずる「コストの高さ」です。このデメリットを正しく認識し、事前に対策を講じることが、神奈川での成功に不可欠です。ここでは、初心者が直面する3つの大きな壁について解説します。
神奈川でアパート経営を始める際の最大のデメリットは、初期投資の大きさです。特に横浜・川崎の人気エリアの土地価格は全国トップクラスであり、建築コストも資材高騰や人件費上昇の影響を受け続けています。地方であれば数千万円で始められるケースでも、神奈川では数億円規模になることも珍しくありません。そのため、必然的に自己資金も多く必要となり、金融機関からの融資審査のハードルも高くなります。
神奈川の物件は、地方に比べて利回りが低くなる傾向があります。これは「利回り=家賃収入 ÷ 物件価格」で計算されるためです。神奈川は家賃も高いですが、それ以上に物件価格(特に土地代)が高額になります。計算式の分母が極端に大きくなるため、結果として利回りは低く(例:新築で4.5%~6.5%程度)見えがちです。しかし、これは「安定性」とのトレードオフです。利回りが低くても、空室リスクが低く安定経営が見込めるのが神奈川市場の特徴だと割り切る必要があります。


アパート経営には、家賃収入以外のコストもかかります。神奈川は土地の評価額が高いため、毎年課税される「固定資産税」や「都市計画税」の負担も地方より重くなります。これらの税金は、たとえ満室でも空室でも発生する固定費です。税金の支払いを考慮せずにキャッシュフローを計算すると、手残りが想定より大幅に少なくなる危険性があります。事前のシミュレーション段階で、これらのランニングコストを正確に把握しておくことが極めて重要です。



コスト高というデメリットは、裏を返せば「参入障壁の高さ」を意味します。誰もが簡単に参入できないからこそ、一度優良な物件を建てれば、競合が増えにくく、長期的に安定した経営が可能になります。Rielは、この高いハードルを越えるための「土地仕入れ」と「融資戦略」のプロフェッショナルです。
神奈川と一口に言っても、エリア特性は千差万別です。初期投資を抑えつつ安定したリターンを狙うには、綿密なエリア選定が欠かせません。横浜駅や武蔵小杉駅周辺は魅力的ですが、初心者が高利回りを狙うには戦略が必要です。主要都市と郊外エリアの可能性について解説します。
初心者が利回りと安定性を両立させるなら、この2大都市の「主要駅から1~2駅離れたエリア」や「急行停車駅」が狙い目です。
2大都市以外にも優良な投資先は多く存在します。土地価格が比較的抑えられるため、高い利回りを狙いやすいのが魅力です。
アパート経営の成功は「立地」で9割決まると言っても過言ではありません。初心者が土地を選ぶ際は、必ず「入居者目線」で以下のポイントをチェックしましょう。





「良い土地」は、ネットや不動産屋の店頭には出てきません。Rielは、地域の不動産業者との密な連携や独自のネットワークにより、公開前の「未公開土地情報」を日々収集しています。利回りの取れる土地を仕入れる「情報力」こそが、Rielの最大の強みです。
神奈川市場は魅力的ですが、誰でも簡単に成功できるわけではありません。競争が激しいからこそ、明確な戦略が求められます。特に土地から新築で始める場合、その自由度を活かした戦略が成功の鍵を握ります。弊社(Riel)が実践する、神奈川で成功確率を高める5つの戦略をご紹介します。
アパート経営の利回りは、ほぼ「土地の仕入れ値」で決まります。弊社が「土地からの新築」にこだわるのは、それが利回りを最大化する最善策だからです。建売アパートや中古物件には、販売業者の利益や中間マージンが上乗せされています。しかし、土地を直接仕入れ、そこに自社で最適な設計・建築を行えば、余計なコストを徹底的に排除できます。結果として、総投資額を抑えることができ、新築でありながら高い実質利回りを実現することが可能になるのです。
空室を防ぐには、そのエリアの「賃貸ニーズ」に100%合致した物件を作ることが重要です。例えば、学生街でファミリー向けの間取りを作っても入居者は見つかりません。土地から設計するメリットは、こうしたミスマッチを防げる点にあります。単身者が多いエリアなら1K、DINKsが多いなら1LDK、というように最適化します。また、ありきたりなデザインではなく、外観や内装にデザイン性を持たせ、競合より「選ばれる」物件を作ることで、長期的な家賃下落を防ぎ、安定経営に繋げます。
アパート経営は「融資」がすべてと言っても過言ではありません。自己資金だけですべてを賄う人は稀であり、いかに有利な条件(低い金利、長い期間)で融資を引けるかが、キャッシュフローに直結します。金利が0.5%違うだけで、総返済額は何百万円も変わります。初心者が単独で金融機関と交渉するのは困難ですが、弊社(Riel)のような実績豊富な会社は、多くの金融機関と強固な関係を築いています。お客様の属性に合わせ、最も有利な条件を引き出すサポートができるのが、専門企業と組む大きなメリットです。
アパートは「建てて終わり」ではありません。満室経営を維持するための「管理・募集」が極めて重要です。建物管理(清掃、メンテナンス)が杜撰だと、物件はすぐに劣化し、退去に繋がります。また、退去者が出た際に、いかにスピーディーに次の入居者を見つけられるか(リーシング力)が収益を左右します。信頼できる管理会社を選び、地域の仲介業者と良好な関係を築き、インターネット募集(ポータルサイト)にも力を入れるなど、空室を未然に防ぎ、迅速に埋める仕組みを構築することが必須です。
アパート経営は「事業」です。勘やどんぶり勘定ではなく、データに基づいた経営判断が求められます。建築時に「この家賃なら儲かるはずだ」という甘い見通しを立てるのではなく、近隣の競合データや人口動態に基づき、5年後、10年後の家賃下落や修繕費の発生も織り込んだ、厳格なシミュレーションを行うべきです。経営開始後も、市況の変化に応じて家賃設定を見直したり、適切なタイミングでリフォーム投資を行ったりと、データに基づいた改善を継続することが、神奈川で長く成功し続ける秘訣です。



私たちは「建てて終わり」の会社ではありません。オーナー様の事業が30年後も成功していることを見据え、出口戦略(売却)まで含めた長期的な事業計画をご提案します。この「長期伴走型」の姿勢が、多くのオーナー様に選ばれる理由です。
アパート経営に興味を持っても、具体的に「何から始めればいいか分からない」という初心者は多いものです。土地から新築アパートを建てる場合、土地探しから入居開始まで、多くのステップを踏む必要があります。ここでは、全体像を掴んでいただくために、基本的な手順と流れを4つのステップで解説します。
まずは、ご自身の予算や投資戦略に基づき、「どのエリアで勝負するか」を決めます。横浜市・川崎市なのか、湘南・県央エリアなのか、どの沿線にするのかを絞り込みます。エリアが決まったら、信頼できる不動産パートナー(弊社Rielももちろんお手伝いします)と共に、条件に合う土地を探します。インターネットに出回る前の「未公開情報」を得ることが重要です。良い土地が見つかったら、その土地でどれくらいの規模の建物が建てられ、どれくらいの利回りが見込めるかを即座に試算(プランニング)します。
土地の目星がついたら、次は「建物のプランニング」です。その土地の法規制(容積率、建ぺい率など)を最大限に活かし、かつターゲット層に響く設計プランを作成できる建築会社を選定します。この段階で、複数の会社からプランと見積もりを取り、比較検討(相見積もり)することが重要です。弊社(Riel)のように、土地探しから設計・建築まで一貫して対応できる会社であれば、土地の特性を最大限に活かした「儲かる」プランを迅速にご提案できます。
土地と建物のプランが固まり、総事業費が見えたら、金融機関への「融資」の打診を行います。アパート経営の収益性を具体的に示した事業計画書を作成し、自己資金の割合や返済期間などを盛り込んだ資金計画を立てます。前述の通り、融資条件はキャッシュフローに直結するため、非常に重要なステップです。金利、期間、融資額(フルローンか、一部自己資金か)など、最も有利な条件を提示してくれる金融機関を選定し、融資の内定(または本承認)を得ます。
融資の目処が立ち、土地と建築の契約が完了すると、いよいよ着工です。建築確認申請などの行政手続きを経て、工事が始まります。木造アパートの場合、着工から竣工(建物完成)までの期間は、規模にもよりますが半年~10ヶ月程度が一般的です。建物が完成すると、行政の完了検査を受け、金融機関の融資が実行され、引渡しとなります。引渡し前から入居者募集を開始し、引渡しと同時に満室でスタート(竣工前満室)できるのが理想的な流れです。



この4つのステップで最も時間がかかり、かつ重要なのが「ステップ1:土地選定」です。良い土地はすぐに売れてしまいます。Rielにご相談いただければ、お客様のご希望条件を伺った上で、優良な土地情報が出た際に即座にご提案が可能です。スピード感が成功を左右します。
アパート経営の目的は、家賃収入を得るだけでなく、合法的な「節税」にあるという方も多くいらっしゃいます。特に高所得のサラリーマンや個人事業主にとって、アパート経営は有効な節税対策となり得ます。ここでは、税金面でのメリットを最大化するための基本的な知識を解説します。
アパート経営が軌道に乗り、不動産所得が一定額(一般的に900万円前後)を超えてくると、個人事業主のままよりも「法人化」した方が税率上有利になるケースがあります。個人の所得税は累進課税で最大45%ですが、法人税は税率が一定に近いためです。
まずは個人事業主として始める場合でも、「青色申告」は必須です。複式簿記での記帳が必要ですが、最大65万円の特別控除を受けられるため、節税効果は絶大です。また、アパート経営における最大の節税の仕組みが「減価償却」です。建物は年々価値が下がるという考え方に基づき、建築費用を法定耐用年数(例:木造22年)で分割し、毎年「減価償却費」として経費計上できます。これは実際には支出のない経費(帳簿上の赤字)のため、給与所得など他の所得と損益通算することで、所得税や住民税を圧縮できるのです。
節税効果は、お客様の現在の所得や資産背景によって全く異なります。弊社(Riel)では、単にアパートを建てるだけでなく、お客様一人ひとりの状況に合わせた「節税シミュレーション」もご提供しています。例えば、年収1,500万円のA様が新築木造アパートを建てた場合、減価償却費との損益通算により、初年度にどれくらいの所得税還付が見込めるか。また、5年後、10年後のキャッシュフローと税負担はどう変化するかを具体的に可視化し、最適な投資プランをご提案します。



節税目的でアパート経営を始める場合、特に「減価償却」の仕組みを理解することが重要です。新築木造は法定耐用年数が22年と短いため、毎年の減価償却費を大きく計上でき、高い節税効果が期待できます。Rielでは、提携税理士と連携し、お客様に最適な節税スキームもご提案可能です。
神奈川での新築アパート経営は、投資額が大きく、プロセスも複雑です。初心者が独力ですべてを成功させるのは至難の業と言えます。だからこそ、土地選びから建築、融資、そして満室運営まで、一貫してサポートできる「信頼できるパートナー企業」選びが最も重要になります。
私たち㈱Rielは、まさに「土地から新築アパート経営を始めたい」というお客様を専門にサポートする会社です。弊社の最大の特徴は、事業の川上から川下まで「ワンストップ」で支援できる体制にあります。
これらアパート経営のすべてを、Rielが窓口となってサポートします。
Rielが他社と決定的に違う点は、以下の3つの「こだわり」です。
机上の空論ではなく、Rielでは多くのオーナー様の成功をサポートしてきた実績があります。例えば、自己資金1,000万円からスタートし、Rielのサポートで川崎市内に1棟目を建築。安定したキャッシュフロー実績を武器に、3年後には2棟目の融資にも成功された会社員のB様。また、相続対策として湘南エリアにデザインアパートを建築し、満室経営を実現されたC様など、具体的な成功事例やオーナー様の「生の声」もご紹介可能です。ぜひご相談ください。



Rielは「アパートを建てること」がゴールではありません。「オーナー様がアパート経営で成功し、資産を築くこと」がゴールです。そのため、私たちは無理な営業は一切行いません。お客様の状況と目標に合わなければ、アパート経営をお勧めしないこともあります。それこそが、本当のパートナーとしての誠意だと考えています。
神奈川でのアパート経営は、他のどの投資よりも「安定性」と「資産性」に優れています。しかし、その成功は、物件価格や表面利回りといった単純な数字だけで決まるものではありません。神奈川で成功するためには、「いかに良い土地を仕入れるか」「いかにニーズに合う設計をするか」「いかに長期的な経営戦略を描くか」という3つの要素が不可欠です。
神奈川のアパート経営は、初心者にはハードルが高いと思われがちですが、ポイントさえ押さえれば成功確率は格段に上がります。その条件は以下の3つです。
この3つが揃えば、初心者でも神奈川で堅実な資産形成が可能です。
神奈川でのアパート経営は、正しい知識と戦略、そして何より信頼できるパートナーがいれば、決して難しいものではありません。もし少しでもご興味をお持ちでしたら、まずは弊社(Riel)の無料相談や資料請求をご利用ください。お客様の状況やご希望を伺いながら、神奈川で成功するための「あなただけの最適な投資計画」を、私たちが一緒に考え、ご提案させていただきます。最初の一歩を、ぜひRielと踏出しましょう。