超高利回りアパート投資の秘密
\\\知りたい方はこちら///

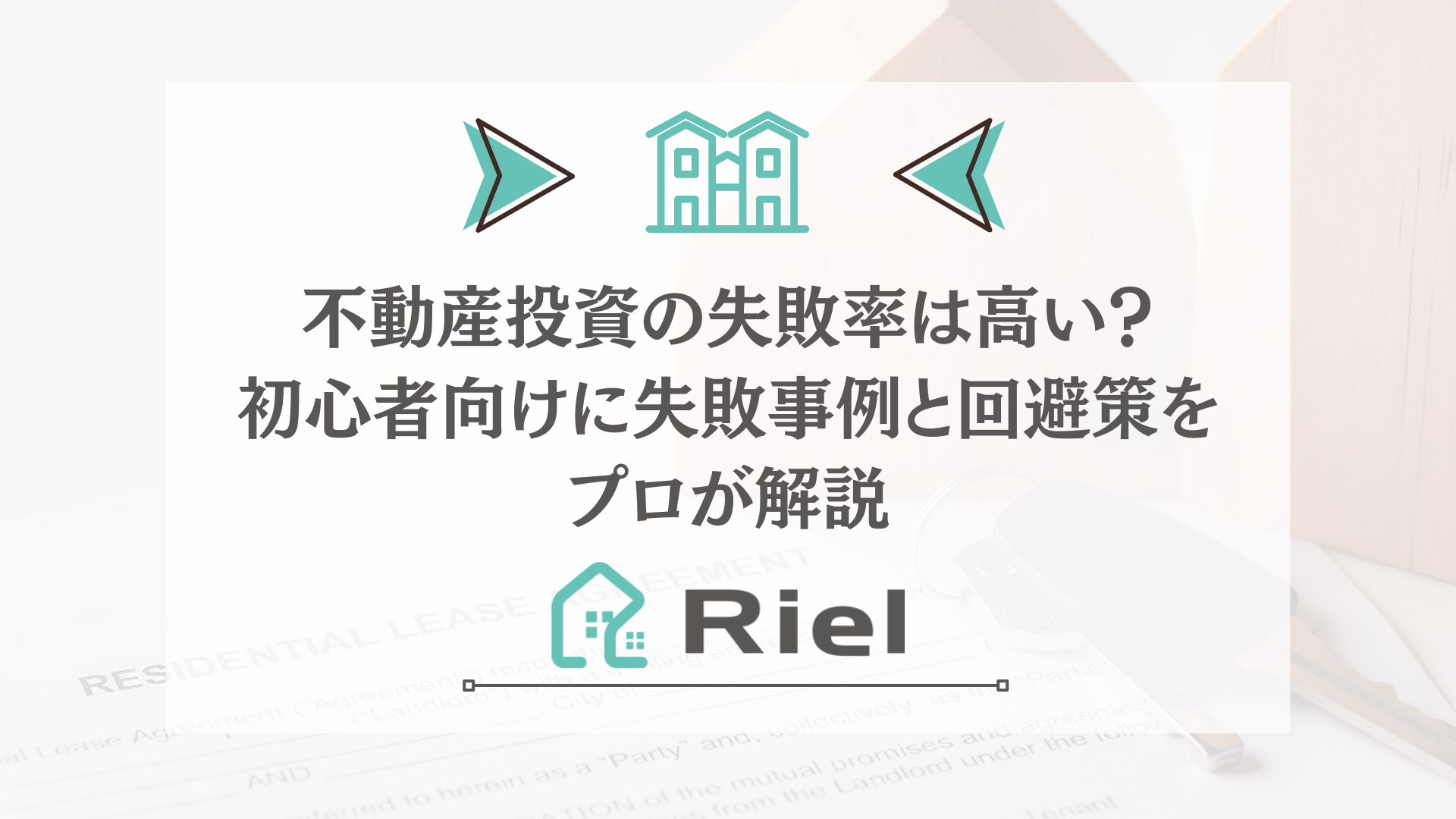
監修者

株式会社Riel 代表取締役
坂口 卓己(サカグチ タクミ)
宅地建物取引士として年間57棟の販売実績を誇り、東京都渋谷を拠点に新築アパートの企画開発から資金計画、満室運営、出口戦略まで一貫支援。豊富な現場経験と最新市況データを融合し、信頼とスピードを重視したサービスで投資家一人ひとりに最適な資産形成プランを提案する不動産投資のプロフェッショナル。
⇒詳細はこちら
不動産投資を検討する際、誰もが「本当に儲かるのか?」「失敗する確率はどのくらいか?」と不安になるかと思います。
本記事では、具体的な数値を引用し、その数字をプロとしてどう解釈すべきかを解説します。
まず大前提として、「失敗」という言葉を定義する必要があります。初心者が恐れる「自己破産」のような再起不能な失敗と、「一時的に赤字になった」という「失敗経験」は、天と地ほどの差があります。
この2つの視点から、信頼できる調査データを見ていきましょう。
不動産投資の「失敗経験」に関する最も有名な調査が、国内最大級の不動産投資情報サイト「健美家(けんびや)」によるものです。
【調査データ】
不動産投資サイト「健美家」が2020年に行った調査によると、収益物件を保有(または過去に保有)したことがある投資家のうち、40.7%が「不動産投資で失敗したことがある」と回答しています。
この「40.7%」という数字だけを見て、「約4割が失敗するのか…」と怖がるのは早計です。重要なのは、その「失敗の理由」の内訳です。
同調査で、失敗の理由(複数回答)として挙げられたトップ3は以下のものでした。
お気づきでしょうか。これらは「自己破産」のような致命的な失敗ではなく、「運営上の課題」や「購入時の見込み違い」です。つまり、この40.7%の多くは「想定外の赤字が出た」「思ったより儲からなかった」という「失敗経験」を指しています。
 Rielからのアドバイス
Rielからのアドバイス逆に言えば、これら3つの原因(空室・修繕・高値掴み)を潰すことこそが、失敗を回避する最短ルートであることを示しています。
次に、初心者が最も恐れる「ローンが返せず自己破産」という最悪のケースの確率を見てみましょう。
前述の通り、不動産投資家のみを対象とした自己破産の統計はありません。そこで、金融機関側が「貸したお金が返ってこない確率」を示すデータを参考にします。
【調査データ】
株式会社東京商工リサーチの調査によると、国内銀行111行の2025年3期決算における「金融再生法開示債権比率」は1.25%でした。
この1.25%という数値は、企業向け融資やカードローンなど、あらゆる貸出金全体を含んだ「不良債権比率」です。
一般的に、個人の住宅ローンやアパートローンは、事業性融資に比べて貸し倒れ率が非常に低い(=安定している)とされています。そのため、個人投資家が不動産投資ローンの返済で「破綻懸念先」以上に陥る確率は、この1.25%よりもさらに低いと推測できます。
これは、健美家の調査で「失敗経験40.7%」という数字が出たことと対照的です。「運営上の小さな失敗」は多くの人が経験する一方で、「破産」という致命的な失敗に至るケースは極めて稀(推定1%以下)である、というのが現実的な見方です。



なぜ破産する人が少ないのか?それは、金融機関が「絶対に返せる」と判断した相手(=属性の高い会社員など)にしか、アパートローンを融資しないからです。銀行は厳格な審査(返済比率)を行うため、構造的に破綻しにくいのです。 失敗とは「破産」ではなく、多くの場合「給与所得(本業の給料)から赤字を補填し続ける」状態を指します。
データから、不動産投資の失敗(=赤字状態)のほとんどが、「空室」「修繕」「高値掴み」の3つに起因することが分かりました。
では、どうすればこれらを回避し、「失敗経験がない」と回答した59.3%(100% – 40.7%)の側に入れるのでしょうか。私たちRielが推奨する「新築アパート経営」は、まさにこの3大リスクを潰すための戦略です。
失敗理由の第1位は空室です。これは「需要(ニーズ)がない立地」を選んだり、「需要に合わない間取り」を建てたりした場合に発生します。
【回避策】
Rielでは、まず「誰に貸すか(ターゲット)」を徹底的に分析します。その土地の賃貸需要(例:単身社会人、学生、カップル)を特定し、そのターゲットに100%響く間取りや設備を「逆算」して設計します。需要から設計することで、競合に対する圧倒的な優位性を確保し、空室リスクを最小化します。
失敗理由の第2位は修繕費です。これは特に「中古物件」で頻発します。購入直後に給湯器やエアコンの一斉交換、数年後に外壁塗装や屋上防水などで、数百万単位の現金が突発的に必要になり、一気にキャッシュフローが悪化します。
【回避策】
新築アパートを選択することは、このリスクに対する最も強力な回答です。新築であれば、主要な設備(給湯器、エアコン)には10年近い保証が付き、外壁や屋根も当面10年〜15年は大規模な修繕が不要です。「想定外」の出費がほぼ発生しないため、購入時のシミュレーション通りにキャッシュフローが安定します。
失敗理由の第3位は高値掴みです。これは、販売会社の「満室想定シミュレーション」を鵜呑みにしてしまうことで発生します。
【回避策】
私たちは、必ず「ストレステスト」を行います。
こうした最悪のケースでも、キャッシュフローが赤字転化しないか(=耐えられるか)を徹底的に試算します。この厳しいシミュレーションをクリアできる「適正な価格」の物件(土地)以外は、お客様にご提案しません。
「不動産投資の失敗率は40.7%」と聞くと不安になるかもしれません。しかし、その中身が「回避可能な運営課題」であり、致命的な「破産率」は1%にも満たない可能性が高いことがお分かりいただけたかと思います。
失敗率という漠然とした数字に振り回されるのではなく、失敗の「理由」を一つずつ潰していくこと。それこそが、不動産投資を成功に導く唯一の道です。Rielは、3大リスク(空室・修繕・高値掴み)を徹底的に排除した、堅実な新築アパート経営をサポートします。
不動産投資の「失敗率」に、公的な統計データはありません。なぜなら「何を失敗と呼ぶか」が、投資家の目的によって全く異なるからです。例えば、赤字化を失敗と呼ぶ人もいれば、目標利回りの未達を失敗と呼ぶ人もいます。数字に惑わされず、具体的な失敗事例とその原因を知ることが、成功への第一歩となります。
まず、ご自身にとっての「失敗の定義」を明確にすることが重要です。なぜなら、投資の目的によって「成功」の形が異なるためです。例えば、毎月のキャッシュフロー(手残り)を重視する人にとって、収支がトントン(収益ゼロ)の状態は「失敗」かもしれません。しかし、ローン返済による資産形成(含み益)を目的とする人にとっては「計画通り」と映るでしょう。あるいは、売却時に元本割れすること(キャピタルロス)を失敗と定義する人もいます。目的が定まらないと、どの数字を追うべきかも曖昧になってしまいます。
不動産投資の失敗の多くは、実は「購入時点」でほぼ決まっています。なぜなら、立地、物件価格、融資条件という最も重要な要素は、購入後に変更するのが極めて困難だからです。例えば、賃貸需要の乏しいエリアの物件を、相場より高い価格で、高金利のローンを組んでしまえば、どんなに運営を頑張っても挽回は難しいでしょう。逆に、購入前に「厳しめの収支シミュレーション」と「実勢家賃での需要調査」を徹底し、有利な融資条件を引き出すことが、失敗を避ける最大の防御策です。
初心者の失敗は、技術的な問題よりも心理的な要因から生じることが多いです。特に以下の3点には注意が必要です。
これらを防ぐには、常に最悪のケース(金利上昇、空室率20%など)を想定したシミュレーションを行い、客観的なデータを自ら取りに行く姿勢が求められます。
不動産投資の成功は「キャッシュフロー(手元に残る現金)」で測るべきです。会計上の「利益(黒字)」と、手元に残るお金は全く別物だと理解してください。この違いを理解していないと、帳簿上は黒字なのに手元の現金が足りなくなる「黒字倒産」のリスクに直面します。
いわゆる「黒字倒産」のリスクは、不動産投資にも存在します。これは、会計上の「経費」と、実際に出ていく「支出」が異なるために起こります。例えば、会計上の経費には「減価償却費(現金は出ない)」が含まれますが、ローンの「元本返済(現金は出る)」は経費になりません。結果として、減価償却費で帳簿上は黒字でも、元本返済額がその黒字額を上回り、手元の現金が減り続ける事態が起こり得ます。特にローン返済期間が短い場合に陥りやすいです。
購入前に提示された「想定利回り」が、運用後に「実質利回り」と大きくズレることは日常茶飯事です。これは、想定利回りが「満室」前提で、運営に必要な経費が甘く見積もられているためです。ズレの主な原因は、①想定より長い空室期間、②突発的な修繕費(給湯器の故障など)、③入居者募集のための広告費、④家賃の下落、などです。例えば、表面利回り8%でも、これらの経費や空室損を差し引くと、実質利回りが4%台になることもあります。



不動産経営は「事業」です
多くの初心者が、会計上の「利益」と手元の「現金」を混同して失敗します。不動産経営は「事業」です。会計上の利益ではなく、毎月いくら「現金」が手元に残るかを最重要視してください。このキャッシュフローこそが、予期せぬ修繕や空室からあなたを守る唯一の盾となります。
初めて一棟アパート経営に挑戦する方が陥りやすい、典型的な失敗パターンが5つあります。これらは全て、購入前の「計画の甘さ」が原因です。具体的な事例を知ることで、同じ轍を踏むリスクを大幅に減らせます。
最も典型的で深刻な失敗が、空室の長期化です。これは、そのエリアの「賃貸ニーズ」と、供給する「物件(間取り・家賃)」がミスマッチを起こしている証拠です。例えば、学生や単身者が多い駅前に、家賃の高いファミリー向け物件を建てても入居者は見つかりません。家賃が相場より少しでも高ければ、入居者は近隣の競合物件に流れてしまいます。
特に都心部の新築区分(ワンルーム)マンション投資で、この失敗が多発しています。これは、販売会社の利益が多く乗った高額な物件価格に対し、得られる家賃収入が見合っていないためです。管理費・修繕積立金・ローン返済を差し引くと、毎月数千円の赤字(持ち出し)になるケースは珍しくありません。「節税になる」という営業トークを鵜呑みにし、給与所得で赤字を補填し続けるのは、健全な「投資」とは言えません。
「30年一括借り上げ(サブリース)」の契約を過信し、経営破綻するケースです。ポイントは、契約書に「家賃の見直し」条項が必ず含まれている点です。実際には、築年数の経過や近隣相場の変動を理由に、数年ごとに賃料の減額交渉が入るのが一般的です。もしオーナーが赤字補填を前提とした高い保証賃料に依存していると、この減額要求に対応できず、一気に経営が行き詰まります。


節税(損益通算)だけを目的に不動産投資を始めると、将来的に行き詰まる可能性があります。なぜなら、節税効果はオーナーご本人の「給与所得の高さ」と「物件の減価償却費の大きさ」に依存するからです。もしご本人の給与が下がったり、役職定年を迎えたりすれば、節税効果は激減します。さらに、減価償却期間が終わると帳簿上の利益が急増し、逆に多額の税金を支払う「デッドクロス」状態に陥ることもあります。
購入時の収支シミュレーションが「甘すぎた」ために、返済に行き詰まるパターンです。特に「空室率」「修繕費」「家賃下落」の3点を見込んでいないケースが目立ちます。実際には、退去後の原状回復費や、給湯器・エアコンの交換費用が突発的に発生します。これらの「必ず起こる支出」を計画に織り込んでいないと、数年後に手元の現金が底をつき、ローン返済がきつくなります。
失敗を防ぐためには、原因を4つの視点で切り分けることが重要です。その4つとは「市場」「物件」「お金」「運用」です。多くの失敗は、これらのうち複数が絡み合って発生しています。
失敗の最大の原因は、多くの場合「市場(賃貸需要)の調査不足」です。そのエリアに「借りたい人」が実在しなければ、どんなに立派なアパートを建てても経営は成り立ちません。例えば、人口が減少している郊外や、すでに競合アパートが飽和状態のエリアを選んでしまうケースです。「土地が安かったから」という理由だけで決めず、その駅の乗降客数、近隣の大学や工場の有無、競合の空室状況などを客観的なデータで調べ上げることが不可欠です。


需要(市場)はあっても、提供する「物件」がそのニーズと合っていなければ失敗します。これが「物件選びのミス」です。例えば、学生街なのに、学生には高すぎる家賃の豪華な設備を導入してしまうケース。逆に、ファミリー層が多いエリアなのに、狭いワンルームばかりを供給してしまうケースです。中古物件の場合、デザインが古すぎたり、現代のニーズ(例:バス・トイレ別、インターネット無料)を満たせていなかったりすると、入居者は決まりません。


収支シミュレーションが甘く、リスクへの「備え」がない計画は失敗します。特に「金利上昇」と「自己資金の枯渇」への備えが重要です。例えば、変動金利でギリギリのキャッシュフローを組んでいると、金利が1%上昇しただけで収支が赤字転化する恐れがあります。また、突発的な修繕や数ヶ月の空室に耐えられるだけの「予備資金(手元キャッシュ)」を確保せずに全額を投資に回してしまうと、不測の事態が起きた瞬間に資金ショートします。
良い物件を選んでも、「運用(管理)」を軽視すると失敗につながります。運用とは、日々の清掃、クレーム対応、家賃滞納の督促、そして退去後の入居者募集(リーシング)活動を指します。例えば、管理委託費をケチって対応の悪い管理会社を選んでしまうと、共用部が汚れ、優良な入居者が退去していきます。特に、空室が出た際に迅速に、かつ広いネットワークで入居者を見つけてくれる「客付け力」のある管理会社を選ぶかどうかは、収益に直結する重要な判断です。


不動産投資の失敗は、購入前の「チェック」でその大半を防ぐことが可能です。初心者が最低限確認すべき項目を「需要」「収益」「資金」「運用」の4つの観点でリスト化しました。



「大丈夫だろう」という楽観論が最大の敵です
このチェックリストを「厳しすぎる」と感じるくらいが、初心者にとっては丁度良いスタートラインです。販売会社の「想定利回り」は、このチェックリストの項目を反映させると、必ず下がります。その「下がった後の現実的な数字」を見て、投資判断をしてください。「これくらい大丈夫だろう」という楽観論こそが、失敗への入り口です。
会社員の方は、社会的信用(属性)が高いため融資に強く、不動産投資で有利です。しかし、その「属性の高さ」が原因で陥る失敗もあります。「任せきり」の危険性や、本業の感覚で短期的な利益を求めすぎることなど。会社員ならではの強みを生かしつつ、誤解を解くことが重要です。
「自分は上場企業勤務だから(属性が良いから)融資も満額引けるし安心だ」と考えるのは早計です。金融機関は、あなたの属性(返済能力)を見て融資を実行しますが、実際に返済の原資となるのは「物件が生み出す家賃収入」です。どんなに属性が良くても、物件自体の収益性が低ければ、あなたの給与所得から赤字を補填し続けることになります。属性の良さは「良い条件で始めるための武器」であり、安全性を担保するものではないと心得え、必ず「貯金(予備資金)」というクッションを厚く持つべきです。
会社員の方は忙しいため「管理会社に完全にお任せしたい」と考えがちですが、「丸投げ」は非常に危険です。信頼できる管理会社に業務を「任せる」ことと、何も確認せず「丸投げ」することは全く違います。「任せる」とは、プロの業務を尊重しつつも、毎月送られてくる収支報告書に必ず目を通し、空室が続けば「原因と対策」を管理会社と協議する姿勢です。「丸投げ」とは、レポートも見ず、利益が出ているかどうかも把握していない状態です。あなたはあくまで「経営者」であるという意識を失ってはいけません。
不動産投資は、FXやデイトレードのように短期間で大きな利益を狙う投機ではありません。本質は、長期にわたって安定した家賃収入を得て、ローン返済と共に資産を築いていく「事業(ビジネス)」です。会社員の方が本業の感覚で「すぐに結果を出したい」と焦り、利回りだけを追って高リスクな中古物件に手を出すと、運営の手間や修繕費で疲弊してしまいます。最低でも10年、20年という時間軸で「長く続ける」ことを前提に、無理のない、安定志向の物件(例:新築アパート)から始めるべきです。
20代から不動産投資を始めるのは、非常に賢明な戦略です。最大の武器は「時間」です。自己資金や属性(勤続年数)の弱さを、「長期の融資期間」と「複利効果」という時間の力でカバーできます。早く始めるほど、雪だるま式に資産を増やせる可能性が高まります。
20代の最大の強みは、金融機関から「最長の融資期間(例:35年)」を引き出せることです。融資期間が長ければ、毎月の元本返済額は少なくなります。その結果、手元に残るキャッシュフロー(手残り)が厚くなり、経営の安定性が劇的に高まります。例えば、50歳の人が20年ローンしか組めない物件でも、25歳なら35年ローンが組め、月々の返済額を大幅に圧縮できるのです。また、早くローンを完済できれば、その後の人生で家賃収入だけを受け取る「年金」として活用できる期間も長くなります。
20代は一般的に自己資金(頭金)が少ないのが弱点です。この場合、絶対に「フルローン」や「オーバーローン」ありきで投資を始めてはいけません。物件価格の1割〜2割の自己資金を貯めることを最初の目標にしてください。頭金があれば、①金利交渉で有利になり、②返済比率が下がり、③経営の安全性が高まるからです。例えば、まず500万円を貯める。それを頭金に5000万円のアパートを建て、そこで得たキャッシュフローと給与所得を合わせて、次の頭金を貯めて2棟目に進む。この「小さく始めて着実に広げる」という堅実なステップが、若さを生かした王道戦略です。
20代は投資経験が浅いため、効率的な情報収集が鍵となります。その近道は「信頼できる相談相手」と「具体的な実例」から学ぶことです。本やネットの情報は玉石混交です。重要なのは、実際にアパート経営に成功している先輩オーナー(大家)や、Riel(リエル)のように土地探しから建築、管理まで一貫して手がけ、具体的な「実例」と「数値」を公開している誠実なパートナーを見つけることです。机上の空論ではなく、成功例や失敗例といった「生きた情報」に触れることが、何よりの近道となります。
不動産投資には、区分マンション、中古一棟、新築アパートなど、様々な種類があります。「どれが一番儲かるか」ではなく「どれが自分の目的に合うか」で選ぶことが重要です。それぞれにメリットとデメリット(リスク)が存在します。
物件タイプ別の比較表
| タイプ | メリット | デメリット(リスク) |
| 区分マンション | ・少額から可能 ・流動性が高い(売りやすい) | ・運用の自由度が低い ・キャッシュフローが出にくい |
|---|---|---|
| 中古一棟 | ・表面利回りが高い | ・修繕リスク(突発的支出)大 ・融資期間が短い |
| 新築アパート | ・修繕リスクが低い(当面) ・融資期間が最長 ・間取りを最適化できる | ・中古より利回りは低い ・初期投資額が大きい |


区分マンション(ワンルームなど)は、一棟ものに比べて価格が安く、少額から始められるのが最大のメリットです。また、取引が活発なため、売りたい時に売りやすい「流動性の高さ(出口の取りやすさ)」も魅力です。しかし、デメリットは「運用の自由度が低い」ことです。外壁塗装や共用部の修繕は、すべて管理組合の決定に従う必要があり、自分の意思で物件の価値を高める施策(例:エントランスの改修)が打てません。
中古の一棟アパートやマンションは、新築に比べて物件価格が安いため、高い「表面利回り」を期待できるのが魅力です。しかし、初心者が手を出すにはリスクも大きいです。最大のリスクは「修繕費」です。購入直後に、屋根の防水や給湯器の一斉交換など、数百万円単位の突発的な支出が発生する可能性があります。また、法定耐用年数が短いため、金融機関の融資期間も短くなり、月々のローン返済額が重く、キャッシュフローが出にくいという難点もあります。
Riel(リエル)が推奨する新築アパートは、初心者にとって最もリスクとリターンのバランスが取れた手法です。最大のメリットは、購入後10年〜15年は「大規模な修繕リスクがほぼ無い」ことです。これにより、キャッシュフローの計画が非常に立てやすくなります。また、新築は入居者に最も人気があり、高い家賃でも決まりやすいため、安定した運営が可能です。特に、土地から企画して建てる場合、そのエリアの賃貸需要に合わせた最適な間取りを「設計」できるため、長期的な競争力を維持できます。


私たちRiel(リエル)が実践する、土地から新築アパートを建てる進め方は、失敗リスクを徹底的に排除するプロセスに基づいています。単に建物を売るのではなく、長期的な「経営の成功」をゴールに設定しています。そのために、需要の逆算と、厳しいリスクテストを何よりも重視します。
失敗しない新築アパート経営は、一貫した流れ(フロー)で進める必要があります。
Rielでは、この5ステップすべてをワンストップでサポートし、各段階でのリスクを最小化します。
Rielの戦略の核は「誰に貸すか(ターゲット)」を最初に決めることです。ターゲットを決めれば、必要なものが全て「逆算」で決まります。例えば、ターゲットを「近隣の病院に勤める看護師(女性単身者)」に設定します。すると「オートロックと宅配ボックスは必須」「間取りは1Kより広めの1LDK」「家賃相場は8万円まで」といった具体的な仕様と家賃が導き出されます。この「需要からの逆算」を行うことで、「建てたはいいが、誰にも刺さらない」という最悪の失敗を防ぎ、長期的に選ばれ続ける物件を作ることができます。


立てた事業計画が、どれだけの「ストレス」に耐えられるかを必ず試算します。これが「ストレステスト」です。Rielでは、最低でも2つのパターンをシミュレーションに加えます。①「金利上昇リスク」:現在、変動金利は低水準ですが、将来的に1%〜2%上昇した場合でも、キャッシュフローが赤字転化しないか。②「家賃下落・空室リスク」:築年数の経過と共に家賃が10%下落した場合や、空室率が20%に悪化した場合でも、返済が滞らないか。この最悪の状況でも耐えられる計画こそが、失敗しないための「安全弁」となります。





新築アパート経営の「設計できる」という強み
新築アパート経営の最大の強みは、この「逆算設計」ができることです。中古物件は「すでにあるもの」に自分を合わせる投資ですが、Rielの土地から建てる新築は「需要があるもの」をゼロから創り出す投資です。「誰に貸すか」を決め、そのターゲットに100%響く物件を設計できる。このスタート時点の優位性が、長期的な失敗率を劇的に下げるのです。
不動産投資は「事業」であり、法律と税金の知識は必須です。建築基準法や税法(減価償却など)の無理解は、融資不可や追徴課税といった致命的な失敗に直結します。「知らなかった」では済まされないため、経営者として最低限のルールは必ず押さえる必要があります。
土地や建物を買う前に、法的な規制を必ず確認します。特に重要なのが「建築基準法」です。
「減価償却費」を経費計上し、不動産所得を赤字にすることで、給与所得と「損益通算」し、節税する手法があります。しかし、これは万能ではありません。第一に、節税効果はご本人の給与所得(所得税率)が高いほど大きく、所得が低いと効果は薄いです。第二に、減価償却費は「借り物の経費」です。償却期間が終われば経費が急減し、税金が急増する「デッドクロス」を迎えます。節税のために意図的に赤字経営(キャッシュフローがマイナス)を続けるのは本末転倒です。
Riel(リエル)では「フルローン(自己資金ゼロ)」でのスタートを推奨していません。予備資金がないため、一度の空室や修繕で破綻するリスクが極めて高いからです。安全な目安は、「物件価格の10%〜20%の頭金」+「購入時諸経費(物件価格の7%〜10%)」+「予備資金(半年分の返済額)」です。例えば5,000万円の新築アパートなら、最低でも1,000万円程度の自己資金は用意したいところです。
高い利回り(例:表面10%)を追い求めることよりも、「経営を続けられる数字」を作ることの方が100倍重要です。高利回り物件は往々にして高リスク(例:築古、地方)であり、運営が安定しないからです。Rielが重視するのは、ローン返済後の「キャッシュフロー(手残り)」です。たとえ実質利回りが5%でも、長期の融資を組むことで、毎月5万円、10万円のキャッシュフローが安定して残る計画。こうした「続けられる数字」を設計することが、失敗しないための鍵です。
はい、あります。日本全体の人口は減少していますが、それは「一様」に減るわけではありません。今後は「都市部への一極集中」と「利便性の高い立地への集中」が加速します。具体的には、
①東京圏(特に23区や主要駅)、②地方の中核都市(政令指定都市など)、③それらの都市の中でも「主要な沿線の駅近」です。
こうした「人が集まり続ける場所」を選定すれば、安定した賃貸経営は十分に可能です。
はい、全く問題なく売却できます。不動産売買のほとんどは、ローン残債がある状態で行われます。プロセスは、「売却価格」で「ローン残債」を一括返済し、諸経費を引いた残りが、オーナーの手残り(売却益)となる仕組みです。失敗は、「売却価格」が「ローン残債」を下回ってしまう(=オーバーローン)状態の時です。これを防ぐには、①購入時に高値掴みをしないこと、②ローンの元本返済を着実に進めること、③資産価値が落ちにくい立地を選ぶことが重要です。
不動産投資の「失敗率」は、他人が決める数字ではなく、ご自身の「準備」によっていくらでも下げられます。失敗のパターンは決まっており、その多くは購入前の計画とシミュレーションで回避可能です。「楽観視」を捨て、チェックリストに基づき「検証」し、キャッシュフローに「ゆとり」を持つこと。Riel(リエル)は、土地から最適解を設計する堅実な新築アパート経営を通じて、皆様の「失敗しない」資産形成をサポートします。