超高利回りアパート投資の秘密
\\\知りたい方はこちら///


監修者

株式会社Riel 代表取締役
坂口 卓己(サカグチ タクミ)
宅地建物取引士として年間57棟の販売実績を誇り、東京都渋谷を拠点に新築アパートの企画開発から資金計画、満室運営、出口戦略まで一貫支援。豊富な現場経験と最新市況データを融合し、信頼とスピードを重視したサービスで投資家一人ひとりに最適な資産形成プランを提案する不動産投資のプロフェッショナル。
⇒詳細はこちら
土地を資産として所有されている方、あるいは新たに土地からアパート経営をお考えの方へ。その成功の鍵は、9割が「立地選定」で決まると言っても過言ではありません。本記事では、私たちRielが実践する、感覚ではなくデータに基づいた立地選定のフレームワークを公開します。マクロな視点からミクロな視点へと段階的に深掘りし、長期的に安定した収益を生み出すためのエリア選定術を、具体的な注目エリアと共にご紹介します。
成功する立地選定には、広い視野から狭い視点へと段階的に絞り込むフレームワークが不可欠です。なぜなら、感覚的な判断を排し、客観的なデータに基づいてエリアの将来性を見極めることが、長期安定経営の礎となるからです。具体的には、まず首都圏全体の需給(マクロ)を俯瞰し、次いで沿線や駅の力(メソ)で有望エリアを絞り込み、最後に現地の詳細な環境(ミクロ)で最終判断を下します。この3段階の分析こそ、失敗しないアパート経営の羅針盤となります。
【立地選定 3つのステップ】
まず、首都圏全体の人口動態と賃貸需要のバランスを把握することが、立地選定の確かな第一歩です。長期的に人口が増加し、賃貸ニーズが高いエリアに投資することで、安定した入居率が見込めるためです。特に単身者向けアパートを建築する場合、若年層の転入超過が多いエリアは非常に有望と言えるでしょう。例えば、総務省の統計を見ても、東京都への転入超過は依然として高く、神奈川県や埼玉県も堅調に推移しています。こうした大きな人の流れを捉え、どの都県に投資のポテンシャルがあるかを見極めることが重要です。
次に、マクロ分析で絞り込んだ都県の中から、具体的な沿線と駅を評価していきます。ここで重要なのが「沿線力」と「駅力」です。入居者は日々の通勤・通学の利便性を最も重視するため、都心へのアクセスが良い路線や、快速が停車する駅、複数路線が乗り入れる乗換駅、座って通勤できる始発駅などは、いつの時代も高い人気を誇ります。例えば同じ沿線でも、快速停車駅と各駅停車のみの駅とでは、賃貸需要に大きな差が生まれます。この「メソ」の視点で、将来にわたって価値が落ちにくい駅を選び抜くことが肝要です。
最終段階では、候補となる駅周辺の土地を「ミクロ」の視点で厳しくチェックします。入居者が毎日歩く「駅からの徒歩分数」は、募集時の競争力に直結する最重要項目です。一般的にワンルームでは徒歩10分以内が目安となります。さらに、スーパーやコンビニまでの距離といった「生活導線」、夜道の明るさや安全性、そして意外と見落としがちな「地形(坂道や高低差)」も、日々の暮らしやすさを左右します。机上のデータだけでは分からない現地での体感を通じて、本当に住みやすい土地かどうかを最終判断することが成功の鍵です。
 Rielからのアドバイス
Rielからのアドバイス物件情報に記載の「徒歩1分=80m」には、信号の待ち時間や坂道の上り下りは含まれていません。必ずご自身の足で、朝の通勤時間帯と夜の帰宅時間帯の2回、駅から物件まで歩いてみてください。特に女性目線で「夜、この道を一人で歩いても安心か」をチェックすることが、将来の入居者の安心感に繋がり、物件の競争力を高める重要なポイントになります。
アパート経営の成否は、人の流れを安定的に生み出す「需要核」をいかに捉えるかにかかっています。需要核とは、そのエリアの賃貸需要を支える源泉となる施設や場所のことです。これが存在することで、景気の波に左右されにくい安定した入居者確保が期待できます。例えば、大学や大規模病院、オフィス街、大型商業施設、再開発エリアなどがこれにあたります。需要核を起点にエリアを絞り込むことこそ、確実な経営への最短ルートなのです。
エリアの賃貸需要を具体的に分析するには、「誰が」「どこから来て」「どこへ向かうのか」という“人の流れ”を読み解くことが欠かせません。例えば、大規模な大学キャンパスがあれば、学生や教職員という安定した需要が見込めます。また、大きな病院があれば看護師などの医療従事者が、オフィス街であれば単身のビジネスパーソンがメインターゲットとなります。さらに、街の魅力を一変させる「再開発」は、新たな雇用と居住者を呼び込む強力な需要核となります。これらの人の流れを的確に捉えることで、ターゲット層に響くアパート建築が可能になるのです。
アパート経営において、「駅からの徒歩分数」は物件の価値を左右する最も重要な指標の一つです。入居希望者が物件検索サイトで最初に設定する条件が「駅徒歩●分以内」であることからも、その重要性は明らかです。
では、具体的に徒歩分数が変わると、需要や家賃、そして経営の安定性にどのような影響が出るのでしょうか。私たちは、駅からの距離を以下の4つのゾーンに分けて分析しています。
このゾーンは、まさに「鉄板」とも言えるエリアです。
最も多くの賃貸物件が供給され、入居者からの需要も最も厚い、まさに賃貸市場の主戦場です。
入居者は利便性以外の「付加価値」を求めるようになります。
電車通勤を主としない、特定のターゲット層に絞った戦略が必要となるエリアです。
【各ゾーンの特徴まとめ】
| 徒歩分数 | ゾーンの呼称 | 主な入居者層 | 家賃・需要 | 投資家目線 |
| 1~5分 | プレミアムゾーン | 高所得者、多忙な単身者 | 家賃は高く、需要は盤石 | 最も安定的だが、土地取得費は高い |
|---|---|---|---|---|
| 6~10分 | 最有効ゾーン | 一般的な単身者、DINKS | 家賃は標準、需要は厚い | 競合が多く、物件の差別化が必須 |
| 11~15分 | 検討ゾーン | 学生、価格重視層 | 家賃は安め、需要は工夫次第 | 高利回りの可能性があるが、空室リスクも上昇 |
| 16分以上 | ニッチゾーン | 車・バイク利用者、地域就業者 | 家賃は低い、需要は限定的 | 高リスクであり、原則として推奨しない |



忘れてはならないのが、数字上の「徒歩分数」と入居者が感じる「体感距離」は違うという点です。同じ徒歩8分でも、「平坦で明るく、歩道が整備された道」と「急な坂道があり、夜は暗く、歩道のない道」では、入居者の印象は天と地ほど変わります。後者の場合、体感距離は12分以上に感じられ、敬遠される原因となります。物件の価値は、必ずご自身の足で歩き、道のりの快適性や安全性も含めて判断することが鉄則です。


日本の中心である東京都は、圧倒的な人口集中と賃貸需要を誇る最重要エリアです。単身者からファミリーまで多様なニーズが存在し、特に交通利便性の高いエリアは底堅い人気があります。私たちは、単なるブランドイメージだけでなく、再開発の将来性や都心へのアクセス時間を冷静に分析し、長期的に価値が維持されるエリアを厳選しています。Rielが注目する具体的なエリアを、その理由とともに解説します。
| 注目エリア分類 | 具体的な駅・地域 | 特徴 | 主なターゲット層 |
| 中央線・総武線 | 中野〜三鷹、錦糸町周辺 | 都心へのアクセス抜群。商店街が活発で生活利便性が高い。 | 学生、社会人単身者 |
|---|---|---|---|
| 多摩エリア拠点 | 立川、国分寺、多摩センター | 複数路線が乗り入れる交通の要衝。郊外の大学や企業へのアクセス拠点。 | 学生、地域就業者 |
| 再開発・大学集積 | 品川、高輪GW、有明、小金井 | 将来的な資産価値向上が期待できる再開発エリア。安定した学生需要。 | ビジネスパーソン、学生 |


新宿・東京といった巨大ターミナルへ直通する中央線・総武線沿線は、アパート経営において鉄板とも言えるエリアです。特に中野や高円寺、三鷹といった駅は、商店街の活気と都心へのアクセスの良さを両立しており、学生から社会人まで幅広い単身者需要を掴むことができます。また、錦糸町周辺も再開発が進み、商業施設とオフィス機能が集積するエリアへと変貌を遂げました。こうした中核駅は駅力が高く、賃料相場も安定しているため、初心者の方でも堅実な経営が期待できるでしょう。
都心から少し離れた多摩エリアも、戦略的な視点で見れば非常に魅力的な市場です。中でも、JR中央線・南武線・青梅線が交わる「立川」や、西武線との結節点である「国分寺」、そして多摩モノレールと私鉄が接続する「多摩センター」は、交通の要衝として高いポテンシャルを秘めています。これらの駅は、周辺の大学や企業への通勤・通学者のハブとなっており、安定した賃貸需要が見込めます。都心部に比べて土地価格が抑えられるため、高い利回りを実現しやすい点も大きなメリットです。
未来の価値を先取りするなら、再開発エリアと大学集積エリアへの投資は外せません。リニア中央新幹線の始発駅となる「品川・高輪ゲートウェイ」周辺は、国際的なビジネス拠点として街全体が大きく生まれ変わります。また、臨海副都心の「有明」エリアも、商業・イベント施設が集まり、人口増加が期待される注目株です。一方、東京学芸大学や東京農工大学などが集まる「小金井」周辺は、学生需要が非常に安定しています。こうした将来性のあるエリアに投資することで、大きな資産価値の向上が期待できるのです。
東京都に隣接し、独自の経済圏とブランド力を持つ神奈川県も、アパート経営の有望な舞台です。横浜や川崎といった大都市を抱え、都心へのアクセスも良好なため、東京のベッドタウンとして根強い人気を誇ります。沿線ごとの特色が豊かで、エリアによってターゲット層が明確な点も特徴です。Rielでは、利便性と居住環境のバランスに優れたエリアに注目しています。
| 注目エリア分類 | 具体的な駅・地域 | 特徴 | 主なターゲット層 |
| 東急線準主要駅 | 綱島〜妙蓮寺、鷺沼〜長津田 | 都心へのアクセスを維持しつつ、落ち着いた住環境と手頃な土地価格が魅力。 | 社会人単身者、DINKS |
|---|---|---|---|
| 新交通結節点 | 新横浜、羽沢横浜国大 | 新線開業により交通利便性が飛躍的に向上。将来性が高い。 | ビジネスパーソン、転勤者 |
| 湘南・横須賀ライン | 藤沢、辻堂、大船 | 生活利便性と湘南ブランドを両立。ターミナル駅としての機能も高い。 | 都心通勤者、地元就業者 |
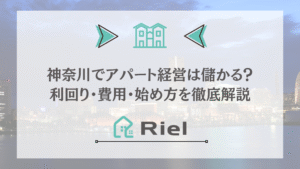
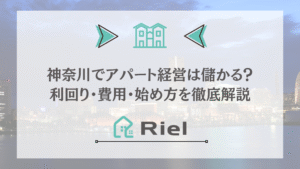
東急東横線と田園都市線は、都心へ向かう神奈川県の二大人気路線です。自由が丘や二子玉川といったブランド駅だけでなく、その周辺にある「準主要駅」にこそ投資妙味があります。例えば東横線の綱島~妙蓮寺エリアや、田園都市線の鷺沼~長津田エリアは、都心へのアクセスを維持しつつも、比較的土地価格が手頃で、落ち着いた住環境が魅力です。こうした駅は、生活利便性を重視する社会人単身者やDINKSから安定した支持を得ており、堅実なアパート経営を展開できます。
近年の路線延伸により、交通ネットワークが劇的に変化しているエリアは大きなチャンスを秘めています。東海道新幹線の停車駅である「新横浜」は、相鉄・東急新横浜線の開業により、都心へのアクセスが飛躍的に向上しました。周辺はオフィス街としての機能も高く、ビジネスパーソンの賃貸需要は非常に旺盛です。また、新駅「羽沢横浜国大」は、JRと相鉄の相互乗り入れで注目度が急上昇しています。こうした新たな交通結節点は、将来の資産価値向上が大いに期待される狙い目のエリアと言えるでしょう。
都心への通勤利便性と、湘南エリアならではのライフスタイルを両立できるのが、東海道線・横須賀線沿線の魅力です。複数路線が乗り入れるターミナル駅の「大船」や、駅直結の大型商業施設で人気の「辻堂」、そして江の島への玄関口でもある「藤沢」は、生活の利便性が非常に高いエリアです。平日と休日で人の流れが異なるため、観光関連の需要も一部見込めるのが特徴。安定した居住ニーズに加え、独自の魅力を求める層にもアプローチできる、ポテンシャルの高いエリアです。
東京の巨大なベッドタウンとして発展を続ける埼玉県は、堅実な賃貸需要が見込めるエリアです。池袋・新宿・渋谷・東京・上野など、都心の主要ターミナルへ直通する路線が充実しており、交通利便性は非常に高いと言えます。都心と比較して土地価格がリーズナブルなため、投資効率の観点からも魅力的な選択肢です。Rielでは、ターミナル駅の周辺と、都心へアクセスしやすい準急停車駅に注目しています。
| 注目エリア分類 | 具体的な駅・地域 | 特徴 | 主なターゲット層 |
| 主要ターミナル | 大宮、浦和、川口 | 県内有数の商業・業務集積地。都心へのアクセスは抜群で需要が厚い。 | 社会人単身者、ファミリー |
|---|---|---|---|
| 東武東上線 | 朝霞台、志木、ふじみ野 | 池袋へ好アクセス。家賃が手頃で若年層の単身者需要が旺盛。 | 学生、若手社会人 |
| 武蔵野線 | 南越谷、東川口、新三郷 | 沿線に大型商業施設や物流拠点が点在。地域内の雇用需要が強い。 | 地域就業者、ファミリー |


埼玉県内で圧倒的な存在感を放つのが「大宮」「浦和」「川口」の3都市です。新幹線も停車する県内最大のターミナル「大宮」、県庁所在地で文教地区としても名高い「浦和」、そして荒川を挟んで東京に隣接する「川口」。これらの駅は京浜東北線や埼京線、高崎線などが乗り入れ、都心へのアクセスは抜群です。駅周辺には商業施設やオフィスが集積し、単身者からファミリーまで幅広い賃貸需要が存在します。安定した経営基盤を築く上で、まず検討すべき中心的なエリアです。
池袋へ直通する東武東上線は、都心へ通勤・通学する単身者に人気の高い路線です。特に注目したいのが、準急や急行が停車する利便性の高い駅です。JR武蔵野線と乗り換え可能な「朝霞台」、大学のキャンパスも近く学生需要が厚い「志木」、そして再開発で住環境が向上した「ふじみ野」などは、その代表格です。これらの駅は、都心へのアクセスと手頃な家賃を両立できるため、若年層の入居者を安定して確保することが可能です。費用対効果の高いアパート経営を目指すなら、非常に魅力的な選択肢となります。
埼玉県を横断し、各路線を繋ぐ武蔵野線は、沿線に大規模な商業施設や物流施設といった「雇用核」が点在するのが特徴です。東武スカイツリーラインと交差する「南越谷」、埼玉高速鉄道との乗換駅「東川口」、大型商業施設が集積する「新三郷」周辺は、まさにその典型です。これらのエリアは、都心へ向かう需要だけでなく、地域内で働く人々の賃貸需要も取り込めるため、入居者層が多様化し、景気変動に強い安定した経営が期待できます。
東京の東側に位置し、多様な顔を持つ千葉県もアパート経営の有望エリアです。都心に隣接する利便性の高いエリアから、計画的に開発されたニュータウン、国際的なイベントが集まるベイエリアまで、それぞれの地域に明確な強みがあります。成長著しいつくばエクスプレス沿線や、再開発が進むエリアなど、将来性に着目した投資戦略が有効です。
| 注目エリア分類 | 具体的な駅・地域 | 特徴 | 主なターゲット層 |
| 都心近接ゾーン | 市川、本八幡、浦安 | 総武線快速や東西線直通で都心へ直結。実質的に都内と変わらぬ利便性。 | 都心勤務の単身者、DINKS |
|---|---|---|---|
| つくばエクスプレス | 流山おおたかの森、柏の葉 | 急速な人口増加と計画的な街づくりが魅力。将来性が非常に高い成長エリア。 | 子育て世代、都心通勤者 |
| 京葉線ベイエリア | 海浜幕張、新習志野 | ビジネス・イベント・商業機能が集積。職住近接ニーズが強い。 | 地域就業者、イベント関係者 |


千葉県の中でも、都心へのアクセス時間を最も重視するなら、総武線快速停車駅や東京メトロ東西線沿線が第一候補となります。江戸川を越えてすぐの「市川」、都営新宿線も利用できる「本八幡」、そして東西線で大手町へ直通の「浦安」は、実質的に都内と変わらない利便性を誇ります。これらのエリアは、都心勤務の単身者やDINKSから絶大な人気があり、高い賃料水準と稼働率を維持することが可能です。土地価格は高めですが、それに見合うだけの収益性が期待できるでしょう。
近年の首都圏で最も成長著しい路線の一つが、つくばエクスプレス(TX)です。特に「流山おおたかの森」と「柏の葉キャンパス」は、計画的な街づくりによって、商業施設、オフィス、大学、公園などがバランスよく配置され、子育て世代を中心に急速な人口増加を続けています。こうした街の成長は、そのまま賃貸需要の増加に直結します。現在はファミリー層が中心ですが、将来的に単身者需要も拡大する可能性を秘めています。将来性を見据えた先行投資として、非常に魅力的なエリアです。
東京湾岸エリアを走る京葉線沿線は、ビジネスとレジャーの両面で強い需要を持つユニークなエリアです。幕張新都心の中心である「海浜幕張」は、大規模なオフィスビル群と国際展示場、アウトレットモールが集積し、就業者やイベント関係者の賃貸需要が豊富です。また、「新習志野」駅周辺も、大学のキャンパスや物流施設があり、安定した入居者が見込めます。計画的に整備された美しい街並みも魅力であり、職住近接を求める層から安定した支持を集めるエリアと言えます。
有望なエリアを絞り込んだら、その「沿線」と「駅」が持つ本当の実力を詳細に見極める必要があります。単に知名度やイメージだけで判断するのではなく、入居者の視点に立って、日々の利便性や将来性を客観的な指標で評価することが重要です。このプロセスを丁寧に行うことで、長期にわたって競争力を維持できる、真に価値のある立地を選び抜くことができます。
駅の力を測る具体的な指標として、まず「電車の利便性」が挙げられます。快速や特急の停車、複数路線への乗り換えが可能か、朝のラッシュ時に座れる始発列車はあるか、といった点は入居者にとって死活問題です。また、都心からの「終電時間」の遅さも、残業の多いビジネスパーソンや飲食業従事者にとっては重要な選択基準となります。さらに、駅を降りてからの「生活インフラ」も欠かせません。スーパーやコンビニ、ドラッグストア、飲食店などが駅前に充実しているかどうかが、街の暮らしやすさを決定づけます。
【駅の力を測るチェックリスト】
現在の状況だけでなく、将来の市場環境を“先読み”することも、プロの投資家には求められます。具体的には、対象エリアの「競合供給」の状況を調査し、アパートの供給過多に陥っていないかを確認します。周辺の「建設計画」を役所などで確認し、将来的に大型マンションや競合アパートが建設される予定がないかも重要です。そして、地域の不動産会社にヒアリングを行い、現在の「空室率」や賃料相場の動向を把握します。これらの情報を総合的に分析し、将来にわたって安定した賃貸経営が可能かどうかを判断するのです。
どのエリアに、どのような間取りのアパートを建てるかは、投資戦略の根幹をなす重要な判断です。エリアの特性とターゲットとする入居者層を正確に分析し、最適な組み合わせを見つけ出す必要があります。例えば、学生街にファミリー向け物件を建てても需要は見込めません。エリアの性格を深く理解し、それに合致した商品(アパート)を企画することが、成功への必須条件となります。
立地の特性によって、最適な間取り戦略は大きく異なります。駅からのアクセスが最優先される都心近接エリアでは、入居者の入れ替わりが早い「回転重視」の戦略が基本です。そのため、コンパクトなワンルームや1Kで、多くの入居者を確保し、稼働率を高めることが有効です。一方、大学や企業の集積地といった郊外の需要核エリアでは、一度入居すると長く住み続ける傾向があるため、「滞在年数重視」の戦略をとります。この場合、少し広めの1LDKなどを供給し、安定した長期入居を促すことが収益の最大化に繋がります。
| 比較項目 | 都心近接エリア | 郊外核エリア |
| 基本戦略 | 短期的な入居者の入れ替わりを前提とした「回転重視」 | 長期的な入居を促す「滞在年数重視」 |
|---|---|---|
| ターゲット層 | 通勤時間を最優先する単身者、DINKS | 学生、エリア内の企業就業者 |
| 最適な間取り | ワンルーム、1K(コンパクトで機能的) | 1LDK(やや広めで快適性を重視) |
| 収益のポイント | 高い賃料と高い稼働率の維持 | 長期安定入居による空室リスクの低減 |



どちらの戦略が良いという訳ではなく、ご自身の投資スタンスに合わせることが重要です。高い利回りを狙い、入退去管理の手間を厭わないなら「都心近接×回転重視」。手間をかけずに長期で安定したインカムゲインを狙うなら「郊外核×滞在年数重視」が向いています。ご自身の目標に合わせてエリアと間取りの戦略を組み立てましょう。
最終的な投資判断を下すためには、具体的な数値をシミュレーションすることが不可欠です。まず、周辺の類似物件をリサーチし、現実的な「想定賃料」を設定します。次に、エリアの需要動向から「想定稼働率」(一般的には95%以上を目指す)を見込み、年間の家賃収入を算出します。そして、将来物件を売却する場合の「出口利回り」も考慮に入れます。東京都心部は利回りが低くても資産価値が、埼玉・千葉では高い利回りが魅力、といった地域ごとの特性を理解し、自身の投資目標に合致するかを冷静に判断しましょう。
これまでの分析を経て、最終候補地に絞り込んだら、最後に「不動産経営に適さない致命的な欠陥がないか」を多角的にチェックします。見落としがちなリスクを洗い出し、長期にわたって安心して経営できる土地であることを確認するための最終防衛ラインです。このチェックを怠ると、将来思わぬトラブルに見舞われる可能性があるため、細心の注意を払って臨みましょう。
公的データで確認する項目
現地で五感を使って確認する項目
最終確認として、公的なデータを基にエリアの安全性を評価します。市区町村が公表する「人口動態」で、将来的に人口が極端に減少しないかを確認。また、企業の撤退など「雇用核」に大きな変化がないかをニュースなどでチェックします。予定されていた「再開発」が中止になっていないかも重要です。さらに、警視庁や県警が公表する「犯罪発生マップ」で地域の治安を確認し、最後に国土交通省のハザードマップで、洪水や土砂災害などの「ハザードリスク」が許容範囲内(閾値内)であるかを必ず確認してください。



ハザードマップで色が塗られている土地を完全に避ける必要はありません。重要なのは「リスクを正しく認識し、対策を講じること」です。例えば、浸水想定区域であれば、基礎を高くしたり、1階を駐車場にする設計にしたり、火災保険で水災補償を手厚くするなどの対策が考えられます。リスクを許容できるか、対策コストは見合うかを総合的に判断しましょう。
最後は、必ず現地に足を運び、五感を使って最終的な合否を判断します。地図上では分からない「徒歩分数」のリアルな体感(信号の待ち時間や坂道など)を確認します。土地の「前面環境」として、隣接する建物からの日照阻害、近隣の工場や飲食店からの「騒音・匂い」の有無をチェック。そして、最も重要なのが「夜間動線」です。女性の入居者を想定し、夜間に駅から物件まで歩いてみて、街灯の少なさや危険な場所がないかを確認します。これらのチェック項目で一つでも合否基準に満たない点があれば、その土地は見送る勇気も必要です。