超高利回りアパート投資の秘密
\\\知りたい方はこちら///


監修者

株式会社Riel 代表取締役
坂口 卓己(サカグチ タクミ)
宅地建物取引士として年間57棟の販売実績を誇り、東京都渋谷を拠点に新築アパートの企画開発から資金計画、満室運営、出口戦略まで一貫支援。豊富な現場経験と最新市況データを融合し、信頼とスピードを重視したサービスで投資家一人ひとりに最適な資産形成プランを提案する不動産投資のプロフェッショナル。
⇒詳細はこちら
アパート投資は将来の資産形成において非常に有効な手段ですが、「儲かる」というイメージだけで安易に始めると、思わぬ失敗につながるケースが後を絶ちません。本記事では、土地から新築アパートの建築・経営をサポートするプロの視点から、初心者が陥りがちな失敗のパターンとその具体的な回避策を徹底解説します。この記事を読めば、アパート投資で失敗しないための「正しい知識」と「具体的な行動計画」が明確になるでしょう。
アパート投資で失敗する最大の原因は、事前の「設計」不足にあります。多くの方は、魅力的な利回りや営業担当者の言葉を鵜呑みにし、事業計画の細部を詰めないままスタートしてしまいます。しかし、アパート経営はれっきとした事業です。市場調査から資金計画、運営戦略まで、あらゆるリスクを想定した緻密な設計がなければ、長期的な成功は望めません。
初心者が陥りやすい失敗の根源には、以下の3つのような大きな誤解があります。これらは一見正しく見えますが、それぞれにリスクが潜んでいるため、鵜呑みにするのは非常に危険です。
これらの思い込みを捨て、多角的に物件を評価することが失敗を避ける第一歩です。
アパート投資の成功と失敗は、まさに「設計力」で決まります。設計力とは、単に建物の間取りを考えることではありません。どの立地で、どんな入居者層をターゲットにし、どのくらいの家賃で、どのような資金計画で運営していくのか、という事業全体の計画を具体的に描く力です。この設計が甘いと、空室や家賃滞納、予期せぬ修繕費など、様々な問題に対応できなくなります。成功者は例外なく、購入前にこの事業設計を徹底的に行っています。
ここでは、私たちが現場で目の当たりにしてきた、アパート投資のリアルな失敗ランキングTOP10をご紹介します。まずは全体像をご覧ください。
【アパート投資・失敗ランキング】
これらの落とし穴は、誰にでも起こりうるものばかりです。一つひとつの原因と対策を理解し、ご自身の計画に潜むリスクがないか、事前にチェックしていきましょう。
アパート投資における失敗で最も多いのが、賃貸需要のない立地を選んでしまうことです。人口減少が進む日本では、エリアによって需要の差が拡大しています。特に、駅から遠い、周辺に生活利便施設がないといった場所は、将来的に空室率が悪化するリスクが非常に高いと言えるでしょう。実際に、総務省の調査でも賃貸用住宅の空室は増加傾向にあります。目先の価格や利回りに惑わされず、長期的な視点で人が集まり続ける場所かを見極めることが何よりも重要です。
 Rielからのアドバイス
Rielからのアドバイス人口動態などのマクロデータ分析はもちろん重要ですが、私たちはそれ以上に「自分の足で歩いて確かめること」を重視しています。例えば、夜道に街灯は十分あるか、坂道はきつくないか、スーパーの品揃えはターゲット層に合っているかなど、データには表れない「住みやすさ」を入居者は敏感に感じ取ります。成功する大家さんは、例外なく現地調査の達人です。
物件の立地が良くても、そのエリアの入居者ニーズと間取り・設備が合っていなければ入居者は決まりません。例えば、単身者向けエリアなのにファミリータイプの間取りだったり、学生街なのにインターネット無料設備がなかったりするケースです。このようなミスマッチは、長期的な空室の直接的な原因となります。設計段階でその土地のターゲット層を明確に定め、彼らが求める広さ,設備,デザインを的確に反映させることが、満室経営の鍵を握るのです。


自己資金を少なく見せようと、物件価格の100%を超える「オーバーローン」を組むのは非常に危険です。当初はキャッシュフローがプラスでも、金利が上昇した途端に返済額が増え、収支が赤字に転落する可能性があります。特に変動金利で借り入れる際は、将来的な金利上昇を必ず想定しておくべきです。金融庁も金利変動リスクについて注意喚起しています。借入額は物件価格の8〜9割に抑え、金利が2%上昇しても耐えられる資金計画を立てることが、安定経営の鉄則です。
アパート経営では、経年劣化による修繕が必ず発生します。外壁塗装や屋上防水、給湯器の交換など、10年以上のスパンで大規模な出費が必要です。このための修繕費を毎月積み立てていないと、いざという時に数百万円単位の出費が突然発生し、キャッシュフローが一気に悪化してしまいます。多くの初心者は、月々の家賃収入ばかりに目を奪われ、将来の支出を軽視しがちです。長期修繕計画を立て、計画的に資金を確保しておくことが不可欠となります。



「修繕積立金は、家賃収入の5%を“聖域”として別口座に確保してください」と、私たちはいつもお伝えしています。例えば家賃収入が月50万円なら、2.5万円は最初から無かったものとして積み立てるのです。このひと手間で、10年後には300万円が貯まります。これにより、大規模修繕の際に慌ててローンを組むといった事態を避けられ、精神的にも安定した経営が可能になります。


優れた管理会社は満室経営のパートナーですが、質の低い会社に任せると空室が埋まらず、資産価値を大きく損ないます。客付け能力が低い、入居者からのクレーム対応が遅い、清掃が行き届いていないといった状況は、退去の増加と新規入居の機会損失に直結します。手数料の安さだけで選ぶのは絶対にやめるべきです。管理会社の実績や担当者の対応をしっかり見極め、任せっきりにせず、定期的にコミュニケーションを取って運営状況を把握する姿勢が重要になります。



管理会社を選ぶ際は、担当者に「今、このエリアで空室を埋めるための具体的なアイデアを3つ教えてください」と質問してみてください。即座に的確な答え(例えば、特定のポータルサイトへの掲載強化、ADの付け方、競合との差別化設備など)が返ってくる会社は信頼できます。逆に、曖昧な返事しかできない場合は、客付け能力に疑問符がつきます。


「家賃保証」という言葉に惹かれてサブリース契約を結ぶ方は多いですが、その契約内容を正しく理解していないと失敗します。サブリース契約は、未来永劫同じ家賃が保証されるものではありません。多くの場合、2年ごとの見直しで賃料が減額されたり、入居状況が悪化すれば中途解約されたりするリスクがあります。契約書に記載されている「借地借家法」の条文は、貸主(オーナー)よりも借主(サブリース会社)を保護する側面が強いことを認識しておくべきです。
地方の築古物件などに見られる「表面利回り15%以上」といった数字は、一見非常に魅力的です。しかし、その裏には高い空室リスク、多額の修繕費、入居者属性の問題などが隠れていることがほとんどです。利回りの高さは、リスクの高さと表裏一体と考えなければなりません。目先の数字に踊わされず、なぜその利回りが高いのかという理由を深く分析し、隠れたリスクをすべて洗い出した上で、実質的な収益性を冷静に判断することが求められます。


家賃滞納や入居者間の騒音トラブルは、アパート経営において避けられない問題です。これらの問題への対応が遅れると、他の優良な入居者の退去につながるなど、被害が拡大してしまいます。特に家賃滞納は、発覚後すぐに督促を行い、法的な手続きも視野に入れた迅速な対応が不可欠です。自主管理の場合は、これらの対応をすべて自分で行う必要があります。専門的な知識と経験を持つ管理会社に委託することが、リスクヘッジの観点からも賢明な選択と言えるでしょう。
当初の計画になかった追加投資が重なり、資金繰りを圧迫するケースも少なくありません。例えば、購入後に発覚した雨漏りの補修、入居付けのために行った想定外のリフォーム、近隣に新築競合物件ができたことによる家賃下落対策の設備投資などです。これらの追加投資は、当初の利回り想定を大きく狂わせます。物件購入時には、ある程度の予備費を確保しておくとともに、将来起こりうるリスクを予測し、資金計画に織り込んでおく慎重さが必要です。
「アパート投資は節税になる」という側面だけを過度に期待して始めると、本末転倒な結果を招きます。確かに、建物の減価償却費などを計上することで、会計上の赤字を作り、給与所得などと損益通算して所得税・住民税の還付を受けられる場合があります。しかし、それはあくまで会計上の話です。実際のキャッシュフローまで赤字になってしまっては、何のために投資をしているのか分かりません。節税は副次的な効果と捉え、まずは事業として黒字化を目指すべきです。
優良物件を見つけることと同じくらい、買ってはいけない「危険な物件」を見抜く力は重要です。ここでは、初心者が特に注意すべき3つのシグナルを解説します。これらの特徴を持つ物件は、将来的に大きな問題を引き起こす可能性が高いため、避けるのが賢明です。
同じ最寄り駅でも、物件までの道のりが大きく異なります。線路沿いや幹線道路沿いの騒音、急な坂道の上、夜道が暗く人通りが少ない場所、スーパーやコンビニまでが遠いといった「ミクロ立地」の悪さは、入居者に敬遠される大きな要因です。地図上では分からなくても、実際に歩いてみると印象が全く違うことはよくあります。必ず曜日や時間を変えて現地を訪れ、住む人の目線で周辺環境を厳しくチェックすることが大切です。
建築基準法に違反している「違法建築」や、建築当時は適法だったが現在の法律には適合しない「既存不適格」の物件には手を出してはいけません。これらの物件は、金融機関からの融資が受けられない、または非常に厳しくなるだけでなく、将来の売却や建て替えの際に大きな制約が生じます。特に、建ぺい率や容積率がオーバーしている物件は、知らずに購入すると深刻なトラブルに発展しかねません。役所調査を徹底し、法的にクリーンな物件を選ぶことが大前提です。
物件の物理的な欠陥である「瑕疵(かし)」、特に雨漏りは、修繕に多額の費用がかかるだけでなく、建物の寿命を縮める深刻な問題です。さらに、給湯器やエアコンといった設備がすべて交換時期を迎えている場合、購入直後に数百万円単位の出費が発生するリスクがあります。中古物件の場合は、専門家による建物状況調査(インスペクション)を実施し、隠れた瑕疵がないか、主要な設備の更新履歴はどうかを詳細に確認することが、購入後の失敗を防ぐために不可欠です。
瑕疵(かし)とは?
売買対象物に隠された、通常の注意では発見できない欠陥や不具合のこと。法律上、売主は買主に対して責任を負う。
アパート経営の成否は、物件を取得する前の「企画」段階で8割が決まると言っても過言ではありません。誰に、どのような価値を提供して住んでもらうのか。このターゲット設計が明確であればあるほど、満室経営の確度は高まります。感覚ではなく、データと仮説に基づいた企画の型を構築しましょう。
ターゲット設計の第一歩は、想定する入居者の人物像、すなわち「ペルソナ」を具体的に言語化することです。例えば、「○○駅周辺に勤務する20代後半の単身女性、年収400万円、通勤は電車で30分以内を希望し、自炊もするためスーパーが近いことを重視する」といったレベルまで具体的に描きます。このペルソナの生活動線や価値観を深く理解することで、本当に求められる立地や間取り、設備が見えてくるのです。
設定したペルソナに基づき、競合物件に勝てる間取りと設備を設計します。例えば、単身者向けでも、単なるワンルームではなく、独立洗面台や広めの収納、ワークスペースを確保することで差別化が可能です。また、近年のライフスタイルの変化により、無料Wi-Fiや宅配ボックスは必須設備となりつつあります。さらに、木造アパートで問題になりがちな遮音性について、高遮音床材を採用するなど、入居者の満足度を高める投資が、長期的な安定経営につながります。
入居者のニーズに応えることは重要ですが、やり過ぎは禁物です。ターゲット層の家賃負担能力を超えた「過剰スペック」な設備は、投資コストを増大させ、利回りを圧迫するだけです。逆に、競合と比較して見劣りする「過少スペック」は、空室の直接的な原因となります。重要なのは、そのエリアの家賃相場とターゲット層のニーズを正確に把握し、費用対効果を見極めながら、最適なスペックの「線引き」を行うことです。
アパート投資の成功は、レバレッジ効果を最大化する「融資」をいかに上手に活用するかにかかっています。しかし、借り方を間違えれば、一瞬で経営を破綻させる諸刃の剣にもなります。ここでは、金融機関の視点を理解し、安全かつ効果的な資金計画を立てるための要点を解説します。
金融機関が融資審査で重視するのが、DSCR、LTV、返済比率の3つの指標です。これらの数値を意識し、空室率や家賃下落を想定してもなお返済に余裕がある「安全域」を確保した資金計画を立てることが、破綻しないための絶対条件となります。各指標の目安は以下の通りです。
| 指標名 | 内容 | 金融機関が評価する安全域の目安 |
| DSCR (借入金償還余裕率) | 家賃収入が年間返済額の何倍かを示す。値が大きいほど返済の安全性が高い。 | 1.2倍 以上 |
|---|---|---|
| LTV (総資産有利子負債比率) | 物件価格に対する借入金の割合。値が低いほど健全性が高い。 | 80% 以下 |
| 返済比率 | 満室想定家賃収入に占める年間返済額の割合。値が低いほど余裕がある。 | 50% 以下 |
金利タイプ(変動か固定か)の選択は、キャッシュフローに大きな影響を与えます。それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、ご自身の投資戦略やリスク許容度に合わせて最適な組み合わせを選択することが重要です。
| 金利タイプ | メリット | デメリット(リスク) | こんな人におすすめ |
| 変動金利 | ・借入当初の金利が固定より低い ・市場金利が下がれば返済額も減る | ・市場金利が上がると返済額が増える ・将来の返済額が不確定 | 手元資金に余裕があり、金利上昇にも対応できる方 |
|---|---|---|---|
| 固定金利 | ・返済期間中の金利・返済額が変わらない ・将来の資金計画が立てやすい | ・変動金利より当初の金利が高い ・市場金利が下がっても返済額は変わらない | 安定したキャッシュフローを重視し、リスクを避けたい方 |
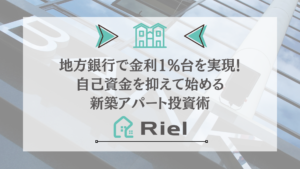
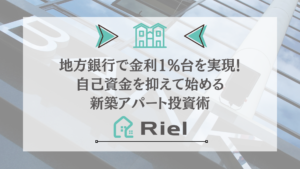
アパート経営では、空室や突発的な修繕など、予期せぬ事態に備えておくことが極めて重要です。そのための備えが「手元流動性」、つまりすぐに使える現金です。一般的には、少なくとも年間家賃収入の3ヶ月〜半年分は常に確保しておくべきとされています。キャッシュフローに余裕が出た際に、安易に繰り上げ返済をするのではなく、まずはこの手元流動性を厚くすることを優先する「繰上げ返済しない勇気」も、時には必要になることを覚えておきましょう。
アパートは建てて終わりではありません。長期にわたってその価値を維持し、安定した収益を生み出し続けるためには、計画的な修繕が不可欠です。購入前に建物全体のライフサイクルコストを把握し、具体的な修繕計画を立てることが、将来のキャッシュフロー悪化を防ぐ鍵となります。
アパート経営では、経年劣化による大規模修繕が必ず発生します。事前にこれらの更新時期と概算費用をリストアップし、長期的な資金計画に織り込んでおくことで、計画的な経営が可能になります。
| 経過年数(目安) | 主な更新・修繕項目 | 費用目安(例:総戸数8戸のアパート) |
| 10年~15年 | ・給湯器、エアコンの交換 ・インターホン、共用灯の更新 ・室内設備の交換 | 150万円 ~ 300万円 |
|---|---|---|
| 15年~20年 | ・外壁の塗装、シーリングの打ち替え ・屋根、屋上の防水工事 | 300万円 ~ 600万円 |
| 20年~30年 | ・給排水管の更新 ・共用廊下、階段の長尺シート張替え | 200万円 ~ 400万円 |
※上記はあくまで一般的な目安であり、建物の仕様や劣化状況によって費用は変動します。
長期修繕計画に基づき、毎月の家賃収入から一定額を修繕積立金として確保する仕組みを作りましょう。家賃収入の5%〜10%程度を一つの目安とすると良いでしょう。そして、実際に修繕工事を行う際は、必ず複数の業者から相見積もりを取ることが重要です。これにより、工事内容の妥当性や費用の適正価格を比較検討でき、無駄なコストを削減できます。業者任せにせず、自身で判断基準を持つことが大切です。
入居者の退去時に発生する原状回復費用は、経営における変動費の一つです。この費用を抑え、品質を安定させるためには、使用する壁紙や床材、設備などをあらかじめ「標準仕様」として決めておくことが有効です。これにより、発注の効率化や材料のまとめ買いによるコストダウンが期待できます。また、入居者負担とオーナー負担の切り分けに関する国土交通省のガイドラインを理解し、トラブルを未然に防ぐこともコスト管理において重要です。
アパート経営の成功は、信頼できる管理会社というパートナーを見つけられるかどうかに大きく左右されます。しかし、数多くの管理会社の中から、本当に実力のある一社を見抜くのは容易ではありません。ここでは、管理会社を選ぶ際に必ずチェックすべきポイントをリストアップします。
本当に客付け力のある管理会社は、空室対策のプロセスを具体的に説明できます。募集広告をどの媒体に、どのような内容で出すのか(Plan)、その結果どのくらいの反響があったのか(Do)、反響に対して何件の案内、申込につながったのか(Check)、そして次の募集戦略にどう活かすのか(Action)というPDCAサイクルを回しているか確認しましょう。これらのデータを可視化し、定期的に報告してくれる会社は信頼できます。
周辺の競合物件や市場動向を的確に分析し、適正な募集賃料を提案できるかは、管理会社の腕の見せ所です。ただ単に相場を提示するだけでなく、なぜその賃料が妥当なのか、具体的な根拠を示せる会社を選びましょう。また、広告料(AD)やフリーレント(一定期間の家賃無料)といった入居促進策を、市況に合わせて効果的に使い分ける戦略設計ができるかどうかも、早期の空室解消につながる重要な能力です。
万が一のトラブルが発生した際に、迅速かつ適切に対応できる体制が整っているかは、非常に重要なチェックポイントです。家賃滞納が発生した場合、どのような手順で督促を行うのか。騒音などのクレームには、何時間以内に対応するのか。最悪のケースである夜逃げが起きた場合、法的手続きを含めてどのように事を進めるのか。これらの一次対応フローが明確にマニュアル化されている会社は、リスク管理能力が高いと判断できます。


「30年一括借上」「家賃保証」といった魅力的な言葉で語られるサブリースですが、その仕組みを正しく理解しないまま契約すると、将来的に大きなトラブルを招く可能性があります。サブリースは決して万能の策ではありません。リスクを理解した上で、上手に活用することが求められます。
サブリース契約書で最も重要なのが、「賃料改定」と「中途解約」に関する条項です。多くの契約では、2年ごとに賃料を見直す権利がサブリース会社側にあり、周辺相場の下落や空室の増加を理由に、保証賃料が引き下げられる可能性があります。また、会社側から一方的に契約を解約できる条項が含まれていることもあります。契約前に、これらの条項を弁護士などの専門家も交えて精査し、リスクを正確に把握することが不可欠です。
サブリースには、大きく分けて「パススルー型」と「賃料固定型」があります。どちらのタイプがご自身の事業計画に適しているか、リスクの差を理解した上で慎重に検討する必要があります。
| 契約タイプ | 仕組み | オーナー側のメリット | オーナー側のリスク・注意点 |
| 賃料固定型 (保証型) | 空室状況に関わらず、毎月一定の賃料が保証される(相場の80~90%) | ・収入が完全に安定し、空室リスクがない ・資金計画が非常に立てやすい | ・収益の上限が低い ・2年ごとの賃料見直しで減額される可能性が高い |
|---|---|---|---|
| パススルー型 (実績連動型) | 入居者が支払った実質家賃から、一定の手数料(5~15%)が差し引かれる | ・満室時は収益が高くなる ・賃料固定型より手残りが多くなる可能性がある | ・空室が発生すると、その分収入が直接減少する ・収入が毎月変動する |
サブリース契約中の物件を売却しようとすると、価格が大幅に下がってしまう可能性があります。なぜなら、次の買い手は、サブリース会社に支払う手数料分だけ収益性が低い物件として評価するからです。また、サブリース契約が引き継がれることを嫌がる買主も少なくありません。将来的な売却(出口戦略)を視野に入れるのであれば、サブリースに頼らない、自立した経営ができる物件を選ぶことが、資産価値を維持する上で非常に重要です。
アパート投資と税金は切っても切れない関係です。税務知識の有無は、最終的な手残りキャッシュフローに大きな差を生みます。しかし、節税効果ばかりを追い求めると、投資本来の目的を見失いかねません。ここでは、経営者として最低限知っておくべき税務の基本と注意点を解説します。
減価償却は、建物の取得費用を法定耐用年数にわたって経費として計上できる仕組みで、アパート投資における節税の要です。この減価償却費などによって不動産所得が赤字になった場合、給与所得など他の所得と合算(損益通算)することで、所得税や住民税を圧縮できます。ただし、木造など耐用年数が短い構造ほど、減価償却期間が終わると急に税負担が増える「デッドクロス」を迎えるため、長期的な税務シミュレーションが欠かせません。
事業規模が大きくなってきたら、個人事業主のまま続けるか、法人を設立するかの判断が必要になります。法人化すると、自身への役員報酬が給与所得控除の対象になったり、経費として認められる範囲が広がったりするメリットがあります。一方で、法人設立・維持のコストもかかります。また、建物の消費税還付については税制改正で年々厳しくなっています。これらの判断は、個々の所得状況や事業規模によって最適な選択が異なるため、税理士などの専門家と相談することが不可欠です。
アパート投資にかかる税金は、所得税だけではありません。所得に応じて課される住民税、事業規模によっては事業税、そして物件を所有しているだけで毎年かかる固定資産税・都市計画税があります。これらの税金は、キャッシュフローを確実に圧迫するコストです。特に固定資産税は、収益状況にかかわらず発生するため、決して無視できません。収支計画を立てる際は、これらの税金を必ず経費として織り込み、実質的な利回りを計算することが重要です。


理論だけでなく、実際の失敗事例から学ぶことは非常に有益です。ここでは、初心者が陥りやすい3つの典型的な失敗ケースを取り上げ、どこに問題があり、どうすれば防げたのかを具体的に検証します。他人の失敗を自分ごととして捉え、同じ轍を踏まないようにしましょう。
Aさんは、都心の新築ワンルームマンションを「節税になる」と勧められ、フルローンで購入しました。しかし、管理費や修繕積立金、固定資産税などのランニングコストが想定以上にかさみ、家賃収入からローン返済を差し引くと、毎月2万円の赤字に。原因は、購入前に甘いシミュレーションを鵜呑みにし、詳細なコストを精査しなかったことです。購入前に、あらゆる支出を洗い出し、現実的な利回りを自分で計算する癖をつけることが失敗回避の鍵です。
Bさんは、国内で給与所得を得ながらアパート経営を行い、損益通算による節税メリットを享受していました。しかし、急な海外転勤で非居住者となったため、国内の給与所得がなくなり、損益通算ができなくなりました。結果、日本国内では不動産所得に対する所得税だけを納税することになり、節税効果が完全に消滅。ライフプランの変化を想定していなかったことが原因です。将来の転勤や転職の可能性も考慮し、節税だけに依存しない事業計画を立てるべきでした。
Cさんは、地方の新築アパートをサブリース契約付きで購入。「30年間家賃保証」という言葉を信じ、安定収入を期待していました。しかし、わずか2年後の契約更新時に、近隣の家賃相場が下落したことを理由に、保証賃料を10%も引き下げられてしまいました。ローン返済額は変わらないため、キャッシュフローは一気に悪化。契約書の賃料改定条項を軽視していたのが失敗の原因です。サブリースは「固定」ではなく「変動」するものと認識し、減額リスクを織り込んだ上で資金計画を立てる必要があります。
デューデリジェンスとは、投資対象の価値やリスクを詳細に調査することです。感覚や営業トークに頼らず、客観的なデータと自身の目で徹底的に調べ上げることが、失敗しない物件購入の絶対条件。ここでは、プロが実践する最低限の調査項目をご紹介します。
レントロール(賃貸借条件一覧表)からは、現在の入居者の属性、契約期間、賃料などを読み解き、安定性を評価します。過去の募集図面を見れば、賃料の変遷や募集期間が分かり、物件の競争力を推測できます。可能であれば、管理会社から直近の募集時の反響データ(問い合わせ数や内見数)を入手しましょう。これらの客観的データは、その物件の「本当の実力」を教えてくれる貴重な情報源です。
物件の購入前には、必ず管轄の役所で詳細な調査を行います。建築基準法や都市計画法上の制限、前面道路の種類、上下水道などのインフラ整備状況などを確認し、将来の建て替えや増改築に支障がないかをチェックします。また、近隣で大規模なマンション建設や商業施設の開発計画がないかも重要です。開発計画は賃貸需要を高めるプラス要因にも、強力な競合の出現というマイナス要因にもなり得ます。
デューデリジェンスの最後は、自分の足で稼ぐ「マイクロマーケット分析」です。物件から徒歩10分圏内にある競合アパートの外観、ゴミ置き場の状況、空室の有無などをくまなく調査します。さらに、スーパー、コンビニ、駅までの動線を実際に歩き、住人目線での住みやすさを体感します。この地道な調査を通じて、データだけでは見えない「この場所で、この物件が勝ち残れる筋道」を具体的に描くことができれば、投資の成功確率は格段に高まります。
アパート投資で失敗する人には、いくつかの共通した思考や行動のパターンが見られます。もし、ご自身に当てはまる点があれば、すぐに意識を改めることが重要です。ここでは、代表的な3つの特徴と、それを克服するための具体的な方法(矯正メソッド)を解説します。
「なんとなく良さそう」「営業担当者がいい人だから」といった感覚的な理由で、数百万円、数千万円の投資判断を下してしまうのは非常に危険です。アパート経営は、すべての判断を客観的な数字に基づいて行うべき事業です。矯正メソッドは、どんな些細なことでもエクセルなどの表計算ソフトを使って、数字でシミュレーションする習慣をつけること。利回り、キャッシュフロー、税金などをすべて数値化し、論理的に考える癖をつけましょう。
表面利回りの高さだけに目を奪われ、その裏に潜む空室リスクや修繕リスク、立地のリスクなどを軽視してしまうタイプです。高利回りには必ず理由があります。この特徴を矯正するには、物件情報を一つ見つけたら、その物件の「最悪のシナリオ」を必ず考える習慣を持つことです。「もし空室が半分になったら?」「もし大規模修繕が今発生したら?」と、リスクを意図的に深掘りすることで、物事を多角的に捉える力が養われます。
一度物件を購入したら、あとは管理会社に任せきりで、不動産市況や税制改正などの新しい情報を学ぼうとしない人は、環境の変化に対応できず失敗しがちです。アパート経営は、常に学び続ける姿勢が求められます。これを矯正する最も簡単な方法は、不動産投資に関する専門書を月に1冊読む、信頼できる不動産会社のセミナーに定期的に参加するなど、具体的な行動目標を立てることです。インプットとアウトプットを繰り返すことで、経営者としてのスキルが向上します。
これまでの内容を元に、アパート投資を始める前に必ず確認すべき項目をチェックリストにまとめました。物件の検討段階から契約直前まで、このリストを使って一つひとつ漏れなく確認することで、失敗のリスクを大幅に減らすことができます。ぜひ保存してご活用ください。
アパート投資は、物件を購入して終わりではありません。むしろ、購入はスタート地点です。市況や金利、自身のライフプランの変化に合わせて、保有し続けるのか、より有利な条件のローンに借り換えるのか、あるいは売却して利益を確定するのか、最適な「出口戦略」を常に考えておくことが重要です。
売却を判断する際の基本的な考え方は、NOI(Net Operating Income:純営業利益)をそのエリアの期待利回りで割り戻して、想定される売却価格を算出することです。例えば、年間のNOIが500万円で、周辺の取引利回りが5%であれば、売却価格の目安は1億円となります。この価格がローン残債を大きく上回るタイミングや、これ以上の賃料上昇が見込めないと判断した時が、売却の一つのタイミングと言えるでしょう。
現在よりも低い金利のローンに借り換えることができれば、月々の返済額を圧縮し、キャッシュフローを改善できます。特に、購入時よりもご自身の属性(年収や金融資産など)が向上している場合や、物件の収益実績が安定している場合は、より有利な条件で借り換えられる可能性があります。ただし、借り換えには手数料などの諸費用がかかるため、それらのコストを考慮してもメリットがあるかどうかを慎重にシミュレーションする必要があります。
保有を継続する場合でも、ただ漫然と持ち続けるのではなく、経営状況を測るためのKPI(重要業績評価指標)を設定することが重要です。例えば、「入居率95%以上を維持する」「3年以内にキャッシュフローの累計をプラスにする」といった具体的な目標です。これらのKPIを定期的にチェックし、目標達成が困難になったり、市場環境が大きく変化したりしたタイミングで、改めて売却や借り換えを含めた出口戦略を見直すべきです。
最後に、アパート投資を検討している初心者の方からよく寄せられる質問にお答えします。多くの方が同じような疑問や不安を抱えています。ここでの回答が、あなたが一歩を踏み出すための後押しになれば幸いです。
現在の金利は歴史的に見ても依然として低い水準にあり、融資を活用する投資家にとっては有利な環境が続いていると言えます。しかし、将来的な金利上昇のリスクは常に意識しておく必要があります。重要なのは、「金利が低いから買う」のではなく、「金利が上昇しても十分に利益を出せる優良物件を、このタイミングで買う」という視点です。金利環境だけに左右されず、物件そのものの収益性を見極めることが本質です。
表面利回りは、年間の満室想定家賃を物件価格で割っただけの単純な指標です。一方、実質利回りは、そこから管理費、修繕積立金、固定資産税、火災保険料などの運営経費を差し引いた純利益で計算します。この差は、物件の構造や築年数、管理内容によって大きく異なりますが、一般的には表面利回りから1.5%〜3%程度低くなることが多いです。投資判断は、必ず実質利回りをベースに行うようにしてください。
一概に「いくらから」という正解はありませんが、初心者が失敗しにくい始め方として、まずは総額5,000万円〜1億円前後、4〜8戸程度の規模からスタートすることをお勧めします。この規模であれば、金融機関の融資も比較的受けやすく、1戸や2戸の空室が出てもキャッシュフローが即座に破綻するリスクを抑えられます。まずはこの規模で経営の経験を積み、成功体験を元に徐々に規模を拡大していくのが王道のステップです。
アパート投資で失敗しないためには、正しい「順番」で計画を進めることが何よりも重要です。思いつきや感情で動くのではなく、以下の論理的なステップを踏むことで、リスクを限りなくゼロに近づけることができます。
壮大な計画も、小さな一歩から始まります。まずは明日から、この3つのアクションを始めてみましょう。①興味のあるエリアの物件を、不動産ポータルサイトで検索し、週末に内見の予約を入れてみる。②管理会社に電話して、特定の物件の現在の反響状況を聞いてみる。③ご自身の現在の資産状況を洗い出し、自己資金としていくら投入できるかをまとめた資金表を作成・更新する。この小さな行動の積み重ねが、大きな成功へとつながっていきます。
本記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます。アパート投資の失敗を避け、成功への道を歩むためには、信頼できるプロのパートナーを見つけることが不可欠です。
株式会社Rielでは、土地探しから新築アパートの企画・建築、そして完成後の管理運営までをワンストップでサポートしております。お客様一人ひとりのご状況や目標に合わせ、複数の建築プランや資金計画、管理プランを同時に比較検討いただくことが可能です。机上の空論ではない、現場のリアルな情報に基づいたご提案をお約束します。
私たちの役割は、単にアパートを建てることではありません。お客様と共に、長期的に安定した収益を生み出し続ける「失敗しない投資計画」を共同で設計するパートナーであると考えています。無料の個別相談では、お客様の疑問や不安に一つひとつ丁寧にお答えしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。あなたの理想のアパート経営を実現するため、私たちが全力でサポートいたします。