超高利回りアパート投資の秘密
\\\知りたい方はこちら///


監修者

株式会社Riel 代表取締役
坂口 卓己(サカグチ タクミ)
宅地建物取引士として年間57棟の販売実績を誇り、東京都渋谷を拠点に新築アパートの企画開発から資金計画、満室運営、出口戦略まで一貫支援。豊富な現場経験と最新市況データを融合し、信頼とスピードを重視したサービスで投資家一人ひとりに最適な資産形成プランを提案する不動産投資のプロフェッショナル。
⇒詳細はこちら
不動産投資の王道ともいえる「マンション投資」と「アパート投資」。どちらも魅力的な選択肢ですが、その特性は大きく異なります。これから新築アパート投資をお考えの皆様が最適な一歩を踏み出すためには、両者の違いを正確に理解し、ご自身の目的や資金計画に合った投資手法を見極めることが不可欠です。本記事では、アパート投資のプロの視点から、初期費用から出口戦略まで、両者の違いを徹底的に比較・解説します。
マンションとアパート、この二つの投資対象の違いを理解することが不動産投資成功の第一歩です。これらは構造や規模、そして投資単位によって明確に区別されます。まずは、それぞれの基本的な定義と、投資の仕方である「区分所有」と「一棟所有」の境界線をしっかりと押さえ、ご自身の投資戦略の土台を築きましょう。違いを把握することで、どちらがよりご自身の目標に適しているかが見えてきます。
実は、「マンション」と「アパート」を区別する法的な定義は存在しません。しかし、不動産業界では建物の構造や階数によって明確に使い分けられています。一般的に、木造(W造)や軽量鉄骨造(S造)で2~3階建ての共同住宅を「アパート」と呼びます。一方、「マンション」は鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)や鉄筋コンクリート造(RC造)といった頑丈な構造で、3階建て以上の建物を指すのが通例です。この構造の違いが、後述する耐用年数や建築コスト、遮音性などに大きく影響してくるため、投資対象を見極める上での根源的な違いと認識しておきましょう。
【アパートとマンションの一般的な違い】
| 比較項目 | アパート | マンション |
| 法的定義 | 明確な定義はなく、不動産業界の通例による区別が一般的 | 明確な定義はなく、不動産業界の通例による区別が一般的 |
|---|---|---|
| 主な構造 | ・木造(W造) ・軽量鉄骨造(S造) | ・鉄筋コンクリート造(RC造) ・鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) |
| 主な階数 | 2階建て~3階建てが中心 | 3階建て以上の中高層建築物が中心 |
| 法定耐用年数 | ・木造:22年 ・軽量鉄骨造:19~34年<br>(→減価償却が早く、短期の節税効果が高い) | ・RC造/SRC造:47年 (→減価償却が緩やかで、長期保有に向く) |
| 建築コスト | 坪単価が比較的安く、総額を抑えやすい | 坪単価が高く、建築費は高額になる傾向がある |
| 遮音性・耐火性 | マンションに比べて劣る傾向があるが、近年の建築技術で大きく向上している | コンクリート壁のため、遮音性・耐火性に非常に優れる |
| デザイン・間取り | 設計の自由度が高く、個性的な物件も作りやすい | 構造上の制約から、画一的な間取りになりやすい傾向がある |
| 投資スタイル | 建物全体を所有する「一棟投資」が主流 | 1室単位で所有する「区分投資」が主流 |
| 主な立地 | 郊外の住宅街から駅近まで、幅広いエリアで建築可能 | 利便性の高い都市部や駅近の土地に建てられることが多い |
不動産投資は、建物の所有形態によって「区分投資」と「一棟投資」に大別されます。区分投資とは、マンションの一室を購入して運用する方法です。対して一棟投資は、アパートやマンションを丸ごと一棟購入し、運用する手法を指します。一般的に、木造や軽量鉄骨造のアパートは建築コストが比較的安価なため一棟で取引されることが多く、RC造のマンションは高額になるため一室単位の区分で取引されるのが主流です。つまり、「アパート投資≒一棟投資」「マンション投資≒区分投資」と捉えられがちですが、RC造の一棟マンションも存在します。この境界線を理解することが重要です。

ここでは、マンション投資とアパート投資の主要な違いを要約して比較します。初期費用、収益性、コスト、リスクという投資の根幹をなす4つの観点から、それぞれの特徴を明らかにします。このサマリーを通じて、ご自身がどちらの投資スタイルにより魅力を感じるか、大枠を掴むことができるでしょう。これから不動産投資を始める方にとって、最も重要な意思決定の基盤となる部分です。
【アパート投資 vs マンション投資 総合比較表】
| 比較項目 | アパート投資(一棟) | マンション投資(区分) |
| 【初期費用・融資】 | ||
|---|---|---|
| 物件価格帯 | 高額になりやすい(数千万~数億円) | 比較的少額から可能(数百万円~数千万円) |
| 自己資金の目安 | 物件価格の1割程度~。土地の価値が高ければフルローンも狙える | 物件価格の2~3割程度を求められることが多い |
| 融資のポイント | 事業性融資。土地の担保価値と事業計画が重視される | 住宅ローンに近い。個人の属性(年収・勤務先等)が重視される |
| 【収益性・キャッシュフロー】 | ||
| 表面利回り | 高い傾向。地方や郊外では10%を超える物件も珍しくない | 低い傾向。都心部では3~5%台が中心 |
| キャッシュフロー | 減価償却費が大きく、税引き後の手残りを多くしやすい | 経費が安定しているが、利回りが低いため手残りは少なめ |
| 節税効果 | ◎(非常に高い) 木造22年という短い法定耐用年数で、多額の減価償却費を計上可能 | △(限定的) RC造47年と法定耐用年数が長く、単年の減価償却費は少ない |
| 【維持管理コスト】 | ||
| 管理の手間 | 多い。建物全体の管理(共用部清掃、修繕計画等)が必要 | 少ない。共用部は管理組合が行うため、専有部の管理に集中できる |
| コストの裁量権 | 高い。管理会社や修繕業者を自由に選定でき、コストを最適化できる | 低い。管理費や修繕積立金の額は、管理組合の総会決議で決まる |
| 大規模修繕 | 自己計画・自己資金で準備が必要。自由度は高いが計画性が求められる | 修繕積立金として毎月強制的に徴収。手間はないが費用は高騰しがち |
| 【リスク・流動性】 | ||
| 空室リスク | 分散できる。1戸空室になっても収入はゼロにならないが、エリア需要がなくなると全滅リスクも | 集中する。1戸が空室になると収入はゼロになる |
| 売却のしやすさ | △(やや低い) 価格が高額なため、買い手は不動産投資家や法人に限られやすい | ◎(高い) 価格が手頃で、投資家だけでなく実需(自分で住む)層もターゲットになる |
| 出口戦略 | ・収益物件として投資家へ売却 ・土地としてデベロッパー等へ売却 | ・収益物件として投資家へ売却 ・居住用物件として個人へ売却 |
初期費用は、アパート一棟の方が高額になる傾向があります。ただし、金融機関からの評価は大きく異なります。アパート一棟投資は土地も所有するため担保価値が高く評価され、LTV(総資産価値に対する負債比率)を高めに設定できる、つまりフルローンに近い融資を受けられる可能性があります。一方、区分マンションは物件価格が手頃な反面、担保評価が建物に偏るため、金融機関によっては自己資金比率を2~3割求められることも少なくありません。金利は個人の属性や物件の収益性によりますが、事業性の高いアパートローンの方が金利はやや高めに設定される傾向にあります。
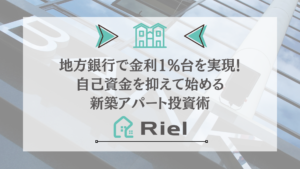
収益性は、一般的にアパート投資の方が高くなる傾向にあります。新築アパートは建築コストを抑えられるため、高い表面利回りを実現しやすいのです。キャッシュフロー(手残り)も、減価償却費を大きく計上できる木造アパートの方が、税引き後では有利に働くケースが多く見られます。一方、マンションは都心の一等地に建てられることが多く、家賃が安定している反面、物件価格が高く利回りは低めです。返済比率は、融資額が大きくなるアパートの方が高くなる傾向があるため、空室時のキャッシュフロー悪化に対する感応度(影響度)はアパートの方が高いと言えるでしょう。

維持管理コストの考え方は、両者で根本的に異なります。区分マンションの場合、管理費や修繕積立金を毎月管理組合に支払うため、手間はかかりませんが、金額の決定権はありません。一方、アパート一棟投資では、管理会社への委託料や修繕費、保険料などをすべて自分でコントロールする必要があります。自由度が高い反面、計画性が求められます。特に大規模修繕は、マンションが積立金から拠出されるのに対し、アパートは自己資金で計画的に準備しなくてはならない点が大きな違いです。税金面では、土地の割合が大きいアパートの方が固定資産税は高くなる傾向があります。

リスクの性質と流動性(売却のしやすさ)はトレードオフの関係にあります。アパート一棟は複数戸あるため、1戸の空室が収入全体に与える影響は限定的ですが、エリアの需要がなくなると全滅のリスクも抱えます。区分マンションは1戸しかないため、空室になれば収入はゼロです。流動性では、物件価格が手頃な区分マンションの方に買い手が見つかりやすく、売却しやすいと言えます。しかし、アパート一棟は土地という資産価値が残るため、収益物件としてだけでなく、土地として売却する選択肢も持てる点が強みです。賃料下落リスクは、競合の多いアパートの方がやや高いとされています。
不動産投資の成功は、収益構造をどれだけ深く理解しているかにかかっています。家賃収入の源泉となる「稼働率」、物件広告でよく見る「利回り」のカラクリ、そして税金計算に欠かせない「減価償却」。これら3つの要素は、マンションとアパートで大きく特性が異なります。この章では、それぞれの違いを深掘りし、あなたの事業計画をより盤石にするための知識を提供します。
収益の基本は「家賃単価 × 戸数 × 稼働率」です。マンションは駅近の好立地に多く、単身者やDINKSなど比較的高い家賃を許容できる層をターゲットにするため、家賃単価は高く設定できます。稼働率も安定しやすい傾向があります。一方、アパートは郊外の住宅街にも建築可能で、学生やファミリー層など、より広い需要層を取り込めます。家賃単価はマンションに劣りますが、建築コストを抑えられるため、土地値の安いエリアでも十分に事業が成り立ちます。重要なのは、そのエリアの需要層を見極め、彼らが求める間取りと家賃設定ができるか、という点に尽きます。
表面利回り(年間家賃収入 ÷ 物件価格)は、アパートの方が高く出る傾向にあります。しかし、投資判断で本当に重要なのは、運営経費を差し引いた実質利回りです。このギャップを生む最大の要因は、維持管理コストです。区分マンションは管理費・修繕積立金が固定でかかるため、表面利回りからの下落幅が読みやすいのが特徴です。一方、アパートは修繕計画や管理委託料を自分で決めるため、オーナーの裁量で経費が変動します。特に、購入時のシミュレーションで修繕費や原状回復費を甘く見積もると、後々実質利回りが大幅に悪化するため、注意が必要です。
税効果を最大化する上で、減価償却は極めて重要です。建物は年々価値が減少するとみなされ、その減少分を経費として計上できます。この計算の基となる法定耐用年数が、構造によって大きく異なります。国税庁の定めでは、以下の通りです。
| 構造の種類 | 主な用途 | 法定耐用年数 | 特徴と投資への影響 |
| 木造 (W造) | アパート、戸建て | 22年 | 【特徴】 建築コストが安く、設計の自由度が高い。 【投資】 耐用年数が短いため減価償却が早く、短期的な節税効果が最も高い。中古の場合、融資期間が短くなる傾向がある。 |
|---|---|---|---|
| 軽量鉄骨造 (S造) | アパート、小規模店舗、倉庫 | ・鋼材の厚さ3mm以下:19年 ・鋼材の厚さ3mm超~4mm以下:27年 | 【特徴】 木造より強度があり、品質が安定しやすい。 【投資】 木造と同様に減価償却が比較的早く、節税効果を狙いやすい。アパート投資で最も一般的な構造の一つ。 |
| 重量鉄骨造 (S造) | マンション、商業ビル、工場 | ・鋼材の厚さ4mm超:34年 | 【特徴】 柱が少なく広い空間を作れる。耐久性が高い。 【投資】 RC造より耐用年数が短いため、節税と長期保有のバランスを取りたい場合に選択肢となる。 |
| 鉄筋コンクリート造 (RC造) | マンション、ビル | 47年 | 【特徴】 耐久性・耐火性・遮音性に優れ、物理的な寿命が長い。 【投資】 担保価値が高く、金融機関から長期の融資を受けやすい。耐用年数が長いため、年間の減価償却費は少なく節税効果は限定的。 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 (SRC造) | 大規模マンション、高層ビル | 47年 | 【特徴】 RC造に鉄骨の骨組みを加え、さらに強度を高めた構造。 【投資】 RC造と同様。資産価値が非常に高く、長期的な安定資産として保有するのに向いている。 |
| れんが造・石造・ブロック造 | 古い建物、倉庫 | 38年 | 【特徴】 非常に頑丈だが、現在の建築では稀。 【投資】 物件数は少ないが、耐用年数は重量鉄骨造より長い。融資や修繕の面で専門的な知識が必要になる場合がある。 |
※注:法定耐用年数は、税法上の減価償却費を計算するための年数であり、建物の物理的な寿命(実際に使用できる年数)とは異なります。
つまり、新築アパートはマンションの倍以上のスピードで減価償却できるのです。これにより、帳簿上の利益を圧縮し、所得税や住民税を大きく節税できる可能性があります。特に投資初期のキャッシュフローを重視する方にとって、アパート投資の大きなメリットと言えるでしょう。
不動産投資の収益を最大化するためには、コスト構造の理解が不可欠です。収入が同じでも、出ていく費用が異なれば手残りは大きく変わります。この章では、日々の運営で発生するランニングコスト、将来必ず必要になる大規模修繕、そして所有しているだけで課される税金や保険料について、マンションとアパートの違いを具体的に解説します。コストを制する者が、不動産投資を制するのです。
日々の運営コストであるランニング費は、その内訳が大きく異なります。
アパート一棟投資の主なランニング費
区分マンション投資の主なランニング費
アパートはオーナーの裁量でコストコントロールしやすい側面があります。
大規模修繕は、投資の成否を分ける重要なコストです。区分マンションでは、毎月の修繕積立金によって計画的に資金がプールされます。オーナーは個別の資金準備に追われることはありませんが、修繕の時期や内容は総会の決議に従う必要があり、昨今の建築費高騰で積立金が値上げされたり、一時金が徴収されたりするリスクも存在します。対してアパート一棟の場合は、完全に自己責任です。外壁塗装や屋上防水などの修繕計画を自ら立て、資金を準備しなければなりません。
【大規模修繕の考え方の違い】
| 比較項目 | 区分マンション投資 | アパート一棟投資 |
| 【資金準備】 | ||
|---|---|---|
| 方法 | 修繕積立金として、管理費と共に毎月強制的に徴収される。 | 自己資金で準備。家賃収入から計画的に積み立てるか、別途資金を確保する必要がある。 |
| 計画性 | 管理組合が作成する長期修繕計画に基づき、自動的に積み立てられる。 | オーナー自身が修繕計画を立て、必要な資金額を算出して準備する(自己管理)。 |
| 【実行と自由度】 | ||
| 意思決定 | 管理組合の総会決議で決定される。個人の意向は反映されにくい。 | オーナーの裁量で全てを決定できる。 |
| 工事内容・時期 | 長期修繕計画に沿って進められるため、時期や内容の変更は困難。 | 物件の状態やキャッシュフロー状況に応じて、柔軟に時期や内容を調整可能。 |
| 業者選定 | 管理会社が推薦する業者や、総会で承認された業者に発注される。 | 相見積もりを取るなどして、オーナーが自由に業者を選定できる。コスト交渉も可能。 |
| 【コストとリスク】 | ||
| コスト感覚 | 毎月の固定費として支払うため、一括での大きな支出感は薄い。 | 数百万円単位のまとまった支出となるため、キャッシュフローへの影響が大きい。 |
| 主なリスク | ・近年の建築費高騰による修繕積立金の値上げ** ・積立金不足による一時金の徴収** ・計画が実態と合っていない(質の低い工事など) | ・修繕計画の甘さや準備不足による資金ショート ・突発的な修繕に対応できない ・悪質な業者を選んでしまう |
| 投資家としての動き | 購入前に長期修繕計画と積立金の状況を精査することが重要。 | 物件の劣化状況を正確に把握し、現実的な修繕計画と資金計画を立てる管理能力が求められる。 |

火災保険や地震保険は、どちらの投資でも必須のコストです。保険料は建物の構造によって異なり、一般的に木造アパートの方がRC造マンションよりも高くなります。また、固定資産税・都市計画税も重要なランニングコストです。税額は「固定資産税評価額 × 税率」で決まりますが、この評価額は土地と建物の両方が対象です。そのため、土地の持ち分が大きいアパート一棟投資の方が、区分マンション投資よりも税額が高くなる傾向にあります。特に路線価の高いエリアにアパートを建てる場合は、税金の負担がキャッシュフローを圧迫しないか、事前のシミュレーションが不可欠です。
不動産投資には様々なリスクが伴いますが、その種類や影響度はマンションとアパートで異なります。一つの空室が経営に与えるダメージ、建物の構造や古さが引き起こす物理的なリスク、そして経済情勢の変化がもたらす金利の変動。これらのリスクプロファイルを正しく理解し、備えることが長期的に安定した収益を確保する鍵となります。ここでは、それぞれのリスクの性質と具体的な対策について解説します。
空室リスクの影響度は、所有形態によって全く異なります。例えば10戸あるアパートで1戸空室が出た場合、家賃収入の減少は10%です。しかし、区分マンションで空室が出ると、その瞬間に収入はゼロになります。この「0か100か」という性質が区分投資の最大のリスクと言えるでしょう。
【空室リスクのインパクト比較(詳細版)】
| 比較項目 | アパート投資(例:10戸一棟) | 区分マンション投資(1戸所有の場合) |
| 【1戸空室時の状況】 | ||
|---|---|---|
| 家賃収入の減少率 | ▲10% (家賃収入は90%維持される) | ▲100% (家賃収入はゼロになる) |
| キャッシュフローへの影響 | 収入は減るが、他の部屋の家賃でローン返済や経費をカバーできる場合が多い。 | 収入がゼロになり、ローン返済や管理費・修繕積立金を自己資金から持ち出す必要がある。 |
| 精神的負担 | 比較的軽微。「次の入居者をじっくり探そう」と、落ち着いて対応しやすい。 | 非常に大きい。「早く埋めないと赤字が膨らむ」という強いプレッシャーがかかる。 |
| 【リスクの性質】 | ||
| リスクの分散/集中 | 【リスク分散型】 複数戸あるため、1戸の空室が経営全体に与えるダメージは限定的。 | 【リスク集中型】 所有戸数が少ないため、その1戸の状況が経営の全てを左右する「0か100か」の状態。 |
| エリア需要低下の影響 | 周辺環境の悪化や競合の出現で、建物全体の空室率が連動して上昇するリスクがある。 | 影響を受けるのはその1戸のみ。 (※複数のエリアに物件を所有していれば、エリアリスク自体は分散できる) |
| 【空室対策】 | ||
| 対策の自由度と選択肢 | ・特定の部屋だけリフォームする ・部屋ごとに家賃設定を変える ・共用部を改善して建物全体の魅力を高める<br>など、多角的な対策が可能。 | ・その1室のリフォームや条件変更に限られる。 ・共用部の改善など、建物全体の価値向上に直接関与することはできない。 |
※注:この比較は「アパート一棟 vs 区分マンション1戸」を想定しています。区分マンションであっても、複数の物件を異なるエリアで所有することで、リスクを分散させることが可能です。
一方、アパートは複数戸あるため収入の平準化が図れますが、建物全体としての魅力が低下し、周辺に競合が増えると、全戸の賃料が下落するリスクを抱えています。
建物の物理的なリスクは、主に構造と築年数に起因します。RC造のマンションは、耐火性・耐久性・遮音性に優れており、台風や地震といった自然災害にも強いのが特長です。オートロックや防犯カメラなど、セキュリティ設備が充実している物件も多いです。一方、木造アパートは遮音性が課題となることがあり、入居者間の騒音トラブルのリスクは相対的に高まります。ただし、近年の新築アパートは建築技術が向上し、遮音材の導入や間取りの工夫で対策が施されています。また、給排水管など設備の更新リスクは、築年数が経過するほど、どちらの建物でも高まっていきます。

変動金利でローンを組む場合、金利上昇はどちらの投資においても共通のリスクです。特に、借入額が大きくなるアパート一棟投資の方が、金利上昇時の返済額増加インパクトは大きくなります。一般的に、無理のない返済負担率(家賃収入に占めるローン返済額の割合)は40~50%が目安とされます。これを超えると、空室や突発的な修繕が発生した際に、資金繰りが一気に悪化する可能性があります。購入前に、金利が1%~2%上昇した場合の返済額をシミュレーションし、それでもキャッシュフローがプラスを維持できるか、というストレステストを行っておくことが極めて重要です。
「不動産投資は立地がすべて」と言われるほど、物件の場所選びは成功を左右します。しかし、最適な立地はマンションとアパートで異なります。なぜなら、それぞれがターゲットとすべき入居者層が違うからです。都心の一等地を好む層、郊外の静かな環境を求める層。彼らのニーズを的確に捉え、それに合った建物と設備を提供することが、満室経営への最短ルートとなります。
マンションは、主に都市部の駅近に建設されます。交通利便性を最優先する単身のビジネスパーソンやDINKSなどが主な入居者像となり、多少家賃が高くても駅からの距離や設備のグレードを重視する傾向があります。一方、アパートは、駅から多少離れた郊外の住宅地にも建築可能です。主なターゲットは、広い間取りと手頃な家賃を求めるファミリー層や、大学・専門学校に通う学生などです。
【立地とターゲットの違い】
| 比較項目 | マンション(主に区分投資) | アパート(主に一棟投資) |
| 【立地戦略】 | ||
|---|---|---|
| 主な建設地 | 都市部の主要駅周辺、商業地に近いエリアなど、土地の資産価値が高い場所。 | 郊外の住宅地、大学・専門学校の周辺、工業団地の近くなど、特定の賃貸需要が見込める場所。 |
| 土地の選定 | 「駅からの距離」が最も重要な要素となる傾向が強い(点での勝負)。 | 駅距離だけでなく、周辺の生活環境(スーパー、学校、公園など)を含めた「面」でのエリア選定が重要になる。 |
| 【ターゲット戦略】 | ||
| 主な入居者像 | ・単身のビジネスパーソン ・DINKS(共働き・子供なし世帯) | ・ファミリー層 ・学生 ・単身者(広い部屋を好む層) |
| 入居者が重視する点 | ・通勤・通学の交通利便性 ・建物のステータス、セキュリティ ・設備のグレード | ・間取りの広さ、部屋数 ・家賃の手頃さ ・駐車場の有無、周辺の生活環境 |
| 【物件戦略】 | ||
| 家賃設定 | 高く設定しやすい。相場が安定しており、景気変動の影響を受けにくい。 | マンションに比べると低めに設定されるが、建築費を抑えることで高い利回りを狙える。 |
| 求められる間取り | 1K、1LDKなどのコンパクトな間取りが中心。 | 2LDK以上の広い間取りから、学生向けの1Kまで、ターゲットに応じて多様。 |
| 人気の設備 | ・オートロック、宅配ボックス ・浴室乾燥機、インターネット無料 | ・追い焚き機能、カウンターキッチン ・駐車場、インターネット無料、ペット可 |
| 【出口(売却)戦略】 | ||
| 売却時のターゲット | 投資家だけでなく、自分で住みたい実需層も有力な買い手となる。 | 主に他の不動産投資家や事業法人が買い手となる。 |
ターゲットとする入居者像が違えば、求められる間取りや設備も変わってきます。都市部の単身者向けマンションであれば、1Kや1LDKといったコンパクトな間取りで、オートロック、宅配ボックス、浴室乾燥機などの設備が人気です。一方、郊外のファミリー向けアパートでは、2LDK以上の広い間取りや、追い焚き機能付きの風呂、カウンターキッチンなどが喜ばれます。近年では、インターネット無料やペット可といった付加価値で差別化を図るアパートも増えています。重要なのは、その立地の需要に合致した「最適解」を提供することであり、過剰な設備はコスト増につながるため注意が必要です。
物件を手に入れた後、安定した収益を生み出し続けるためには、適切な運用と管理が不可欠です。入居者募集から日々のトラブル対応、退去時の手続きまで、その業務は多岐にわたります。区分マンションとアパート一棟では、これらの管理業務にどれだけオーナー自身が関わるかが大きく異なります。手間をかけずに安定を求めるのか、自らの裁量でコストと品質をコントロールするのか、ご自身のスタイルに合った運用方法を選ぶ必要があります。
物件の管理方法は、オーナー自身が行う「自主管理」と、専門の管理会社に委託する「管理委託」に大別されます。区分マンションの場合、共用部の管理は管理組合が行うため、オーナーが考えるのは専有部(室内)の管理のみです。多くの場合、管理会社に委託(家賃の5%程度が手数料相場)することで、ほぼ手間なく運用が可能です。一方、アパート一棟は建物全体の管理責任を負うため、自主管理は非常にハードルが高く、ほとんどのオーナーが管理委託を選択します。どちらを選ぶにせよ、信頼できる管理会社をパートナーに選ぶことが、運用の手間を減らし、安定経営を実現する鍵となります。
入居者の入れ替えは、必ず発生する重要な業務です。区分マンションでは、管理会社に任せれば募集から契約、退去時の立ち会いまで一括して行ってくれます。原状回復工事も、提携業者にスムーズに発注してくれるでしょう。アパート一棟の場合も管理会社に委託するのが一般的ですが、オーナーの関与度合いを高めることも可能です。例えば、リフォーム業者を自分で選定してコストを削減したり、次の入居者募集のための魅力的な内装を企画したりと、自らの裁量で物件の価値向上を図ることができます。この自由度の高さがアパート経営の面白みの一つです。
空室は、家賃収入の直接的な減少につながる最大のリスクです。空室が発生した場合、様々な対策を講じる必要があります。代表的な打ち手には以下のようなものがあります。
主な空室対策
区分マンションの場合、これらの判断はオーナー一人で行いますが、アパート一棟の場合は、空室の状況に応じて部屋ごとに戦略を変えるなど、より多角的な対策を打つことが可能です。
不動産投資の規模と成功は、金融機関からの融資をいかにうまく活用できるかに大きく依存します。物件価格が高額なため、自己資金だけで購入するケースは稀です。しかし、金融機関が投資用不動産ローンを審査する際の視点は、マンションとアパートで異なります。個人の返済能力に加え、物件そのものが持つ「事業性」や「担保価値」が厳しく評価されます。融資の違いを理解することが、資金計画を立てる上での第一歩です。
融資審査では、個人の属性(年収、勤務先、金融資産など)と物件の収益性・担保価値が総合的に評価されます。
【アパートローンとマンションローンの違い】
| 比較項目 | アパートローン(一棟) | マンションローン(区分) |
| 【融資の基本性格】 | ||
|---|---|---|
| 性格 | 【事業性融資】 賃貸経営という「事業」に対して融資を行う。 | 【個人向けローン】 個人の資産形成を目的としており、「住宅ローン」に近い性格を持つ。 |
| 主な取扱金融機関 | 地方銀行、信用金庫、信用組合、日本政策金融公庫、一部のメガバンクなど。 | メガバンク、地方銀行、ネット銀行など、住宅ローンを取り扱う多くの金融機関。 |
| 【審査の主要ポイント】 | ||
| 個人の属性 | 最低限の属性(年収、自己資金等)は必要だが、それ以上に事業計画の妥当性が重視される。 | 最も重視される。年収、勤務先、勤続年数、個人信用情報などが厳しく審査される。 |
| 物件の評価 | 最も重視される。 ・土地と建物の積算評価 ・家賃収入から算出する収益還元評価を総合的に判断する。 | 担保評価として考慮されるが、個人の返済能力が優先される傾向が強い。 |
| 【融資条件】 | ||
| 金利の傾向 | 比較的高め(1%台後半~3%台)。事業のリスクが金利に反映される。 | 比較的低め(1%台前半~2%台)。個人の信用力がベースとなるため。 |
| 融資期間の目安 | 法定耐用年数に大きく影響される。<br>(例:新築木造なら22年~30年程度) | 個人の年齢(完済時年齢)が重視され、耐用年数の範囲内で比較的長期(~35年)で組みやすい。 |
| 借入可能額(LTV※) | 土地の担保価値が高いため、フルローン(物件価格の100%)やオーバーローンも可能な場合がある。 | 自己資金(頭金)として物件価格の2~3割を求められることが多く、フルローンは難しい傾向。 |
| 【その他】 | ||
| 法人での借入 | 事業規模が大きいため、法人を設立して融資を受けることが一般的かつ有利な場合も多い。 | 個人名義での借入が一般的。 |
※LTV(Loan to Value)…物件価格に対する借入金の割合。
※注:上記は一般的な傾向であり、実際の融資条件は金融機関、経済情勢、個人の属性、物件の評価によって大きく異なります。
アパート一棟ローンは事業性が強いため、土地と建物を丸ごと担保とすることで大きな融-資枠を確保できる可能性があります。また、事業規模が大きくなるため、法人を設立して融資を受けることで、より有利な条件を引き出せるケースもあります。
ローン契約時には、団体信用生命保険(団信)への加入が条件となることがほとんどです。これにより、契約者に万一のことがあってもローン残債が保険で完済され、家族に資産を残すことができます。金銭消費貸借契約(金消契約)を結ぶ際には、金利タイプ(変動か固定か)、返済期間、手数料などを十分に確認する必要があります。特にアパートローンは、法定耐用年数から築年数を引いた期間が返済期間の上限となることが多いため注意が必要です。新築アパートであれば、木造でも22年、金融機関によっては最長35年の長期ローンを組むことが可能で、月々の返済負担を抑えることができます。
不動産投資は、物件を売却して利益を確定させる「出口戦略」まで考えて初めて完結します。購入時にどれだけ高い利回りを実現できても、売却時に買い手がつかなかったり、想定より低い価格でしか売れなかったりすれば、トータルのリターンは大きく損なわれます。マンションとアパートでは、主な買い手層や物件の評価方法が異なるため、売却のしやすさ(流動性)にも差が生まれます。購入前から、将来の出口を意識しておくことが重要です。
売却先と価格査定のロジックは、両者で明確に異なります。区分マンションの主な買い手は、実需(自分で住む)層や同じ個人投資家です。そのため、価格は近隣の類似物件の売買価格を参考にする「取引事例比較法」で査定されることが多く、相場が比較的把握しやすいのが特徴です。一方、アパート一棟の主な買い手は、事業として不動産経営を行う投資家や不動産会社です。価格は、その物件が生み出す収益を基に算出する「収益還元法」がメインとなり、利回りが査定額に大きく影響します。
【出口戦略(売却)の違い 詳細比較表】
| 比較項目 | アパート一棟 | 区分マンション |
| 【買い手と市場】 | ||
|---|---|---|
| 主な買い手層 | ・プロの不動産投資家(個人・法人) ・不動産ファンド、デベロッパー ・相続対策を考える資産家 | ・実需層(自分で住みたい個人・ファミリー) ・初心者を含む個人投資家 |
| 市場の規模 | 買い手層が専門家に限定されるため、市場は比較的小さい。 | 居住目的の一般層もターゲットになるため、市場は非常に大きく、買い手を見つけやすい。 |
| 流動性(売却のしやすさ) | △(やや低い) 価格が高額なため、買い手の探索に時間がかかることがある。 | ◎(高い) 価格が手頃で市場参加者が多いため、適正価格であれば比較的短期間で売却しやすい。 |
| 【価格査定と要因】 | ||
| 価格査定のหลัก | 【収益還元法】がメイン。 「その物件が将来どれだけ収益を生むか」で価値を算出する。土地の積算価格も考慮される。 | 【取引事例比較法】がメイン。 「同じマンションの別室や、近隣の類似物件がいくらで売れたか」で価値を算出する。 |
| 価格に影響する主な要因 | ・稼働率、レントロール(賃料一覧) ・建物全体の修繕履歴、管理状態 ・土地の形状、路線価、将来性 | ・部屋の内装、階数、方角、眺望 ・管理組合の財務状況、修繕履歴 ・同じマンション内での取引事例 |
| 【売却戦略】 | ||
| 売却前の価値向上策(バリューアップ) | ・空室を埋めて満室稼働にする ・賃料を適正価格へ引き上げる ・外壁塗装や共用部のリフォーム | ・キッチン、浴室などの水回りのリフォーム ・壁紙の張り替え、ハウスクリーニング ・家具を配置するホームステージング |
| 買い手の資金調達 | 買い手は事業性ローン(アパートローン)を利用。審査のハードルはやや高い。 | 買い手は住宅ローンを利用可能。審査のハードルが比較的低く、融資を受けやすい。 |
売却で成功を収めるには、タイミングと物件価値の向上が鍵となります。一般的に、不動産市場が活況で、金利が低い時期は高く売却しやすいタイミングです。また、売却前に「バリューアップ」を行うことで、より高い価格での売却が期待できます。区分マンションであれば、室内のリフォームやホームステージングが有効です。アパート一棟の場合は、空室を埋めて満室稼働にすること、外壁塗装や共用部のリニューアルで見た目を良くすること、さらには家賃を適正価格まで引き上げる(レントアップ)ことなどが王道のバリューアップ手法となります。
ここまで見てきたように、マンション投資とアパート投資にはそれぞれ異なる特徴とメリット・デメリットがあります。どちらが優れているということではなく、投資家自身の目的、資金力、リスク許容度、そして運用にかけられる手間によって、どちらが「向いている」かが決まります。この章では、代表的な3つの投資家タイプを挙げ、それぞれに最適な投資対象を提案します。ご自身の姿と重ね合わせながら、最適な選択を見つけてください。
このような方におすすめです。
意外に思われるかもしれませんが、少ない自己資金で資産規模を拡大していきたい方にはアパート一棟が候補となり得ます。アパートは土地の担保価値が高く評価されるため、金融機関によってはフルローンやオーバーローン(諸費用を含めた融資)が受けられる可能性があるからです。
このような方におすすめです。
特に区分マンションは、管理組合が存在するため建物全体の管理をお任せでき、オーナーは室内の管理に集中できます。都心の好立地物件を選べば、景気変動の影響を受けにくく、安定した賃貸需要が見込めるでしょう。
このような方におすすめです。
相続対策や節税を主な目的とする場合、アパート投資が非常に有効な選択肢となります。現金を不動産に変えることで、相続税評価額を大幅に圧縮できる効果があります。特に、アパート(貸家)とその敷地(貸家建付地)は、更地や自宅よりも評価額が低く計算されます。
不動産投資は大きな成功をもたらす可能性がある一方、知識不足や見通しの甘さから失敗に至るケースも少なくありません。しかし、失敗には共通のパターンが存在します。ここでは、初心者が陥りがちな3つの典型的な失敗例を挙げ、それを回避するための具体的な対策を解説します。先人たちの失敗から学ぶことで、あなたの投資成功確率を飛躍的に高めることができるでしょう。
【失敗パターン】
広告に記載されている「表面利回り」の高さだけで物件を決めてしまう。
【回避策】
必ず管理費や修繕費、税金などの運営コストを考慮した「実質利回り」で収支シミュレーションを行う。
【失敗パターン】
「新築だから当分修繕は必要ない」「この立地ならすぐに入居者が決まるはず」といった楽観的な見通しで計画を立てる。
【回避策】
家賃収入の5%程度は、将来の修繕費や空室損に備えてあらかじめ収支計画に織り込み、積み立てておく。
【失敗パターン】
「いつ、誰に、いくらで売るのか」を考えずに購入し、いざ売却したい時に買い手がつかず塩漬けになってしまう。
【回避策】
購入前に複数の売却シナリオを想定し、最悪のケースでも大きな損失を出さないかを確認しておく。
理論だけでなく、具体的な数字で比較することで、マンション投資とアパート投資の違いはより明確になります。ここでは、同じ自己資金を元手に、それぞれ代表的な物件に投資したと仮定し、金利上昇や稼働率低下といったストレスがかかった場合に、キャッシュフローがどう変化するのかをシミュレーションします。
仮に自己資金1,000万円で、5,000万円の新築アパート(借入4,000万円)と、2,500万円の区分マンション(借入1,500万円)を購入したとします。金利1.5%での当初のキャッシュフローは、利回りの高いアパートの方が多く残るでしょう。しかし、金利が1%上昇して2.5%になった場合、借入額の大きいアパートの方が返済額の増加インパクトは遥かに大きくなります。月々のキャッシュフローが赤字に転落する可能性も、アパートの方が高まります。
次に、稼働率が低下した場合の影響を見てみましょう。8戸あるアパートで稼働率が90%(約1戸空室)から80%(約2戸空室)に悪化した場合、家賃収入は10%減少します。一方、区分マンションで比較するために、同じ自己資金で2戸購入したと仮定します。2戸のうち1戸が空室になった場合、収入は50%減となります。このように、収入の安定性という面では、戸数が多いアパートの方が分散効果によってダメージを緩和できると言えます。
マンションかアパートかという選択に関わらず、優れた収益物件には共通する特徴があります。最終的な投資判断を下す前に、以下のチェックリストを使って、検討中の物件を多角的に評価することが失敗を避けるための鍵となります。
まず、レントロール(賃貸借条件一覧表)を入手し、現在の家賃設定が周辺の賃料相場とかけ離れていないかを確認します。相場より高すぎる場合、現在の入居者が退去した後、同じ家賃で貸すのは難しいかもしれません。逆に、相場より安ければ、将来的に家賃を上げる(レントアップ)余地がある優良物件の可能性があります。
建物の物理的な状態は、将来の修繕コストと入居者の満足度に直結します。最低限、1981年6月以降の「新耐震基準」で建てられていることを確認しましょう。給排水管の種類や更新履歴、断熱材の有無、隣戸との壁の厚さ(防音性)も重要なチェックポイントです。特にアパートでは、防音性能が入居者の定着率を大きく左右します。
そのエリアの将来的な賃貸需要を見極めることも不可欠です。自治体の都市計画などを確認し、将来の供給過剰リスクを評価します。逆に、鉄道の新駅開業や大型商業施設の再開発計画などがあれば、人口増加や家賃上昇が期待できます。また、大学や病院、大規模な工場(工業団地)など、安定した賃貸需要を生み出す「需要源」が近くにあるかどうかも、長期的に安定した経営を目指す上で非常に重要なポイントとなります。
ここでは、マンション投資とアパート投資を比較検討されているお客様から、私たちがよくお受けする質問とその回答をまとめました。
はい、狙えます。最近の新築アパートは、デザイン性の高い外観、充実した設備(インターネット無料、オートロック、宅配ボックスなど)、優れた断熱性や遮音性を備えた物件が増えています。立地や間取り、付加価値によっては、周辺の古いマンションよりも高い家賃で貸し出すことも十分に可能です。
一概にどちらが安全とは言えず、リスクの性質が異なります。区分マンションを異なるエリアに複数戸所有すれば、立地のリスク分散が図れます。一方、アパート一棟は一つの建物にリスクが集中しますが、複数戸あるため空室リスクは分散されます。また、土地という資産が残るため、最悪の場合でも土地として売却できるという安全性があります。
見極めのポイントは、過去の修繕履歴と長期修繕計画です。特に、給排水管の交換が適切に行われているか、修繕積立金が計画通りに貯まっているかは必ず確認しましょう。積立金が不足している場合、将来的に一時金の徴収や積立金の大幅な値上げが起こる可能性があります。
個人の所得税率が法人税率を超える水準、具体的には課税所得が900万円を超えるあたりが、法人化を検討する一つの目安となります。青色申告は、事業的規模(おおむねアパート10室以上)であれば65万円の特別控除が受けられるなど税制上有利です。初年度から青色申告承認申請書を提出しておくことをお勧めします。
マンション投資とアパート投資、二つの道を比較してきましたが、最終的な選択は一つの決まった正解があるわけではありません。重要なのは、ご自身の投資目的を明確にし、それに沿って資金計画から出口戦略までを一貫したストーリーとして描くことです。
以下のステップでご自身の投資計画を組み立ててみましょう。
【不動産投資の意思決定 6ステップ】
なぜ投資をするのか? 老後資金、節税、早期リタイアなど
自己資金はいくらか? 借入可能額は?
どのエリアで勝負するのか?
アパートか、マンションか? 新築か、中古か?
管理はどうするか? 空室対策は?
いつ、誰に、いくらで売却するのか?
この一連の意思決定プロセスにおいて、本記事で解説した収支シミュレーションや物件選びのチェックリストをぜひご活用ください。具体的な数字と客観的な基準で判断することが、成功への最短距離です。